《 馬込文士村散歩 》
●宇野千代の東京を歩く (戦前篇) 2001年9月15日 V02L05
(最終更新内容:小石川区林町62番地の写真を取り替え) |
 二回続けて「下山事件」を追いかけてきましたが、ここで少し休みまして、以前から再掲載をお約束していた「馬込文士村散歩」の第一回として”宇野千代の東京”を歩いてみたいと思います。宇野千代は明治30年11月、山口県岩国市生まれ。岩国高女卒後の大正10年、「脂粉の顔」でデビューし上京。作家の尾崎士郎、画家の東郷青児、北原武夫と同棲、結婚を繰り返し、「色ざんげ」や「別れも愉し」「おはん」「生きて行く私」で高い評価を受けています。平成8年98歳で死去。宇野千代の「私が建てた家」によると「何しろ、七十五歳になる現在までに、数えて見ると、十一軒建てた勘定になるからだ。」とあります。 二回続けて「下山事件」を追いかけてきましたが、ここで少し休みまして、以前から再掲載をお約束していた「馬込文士村散歩」の第一回として”宇野千代の東京”を歩いてみたいと思います。宇野千代は明治30年11月、山口県岩国市生まれ。岩国高女卒後の大正10年、「脂粉の顔」でデビューし上京。作家の尾崎士郎、画家の東郷青児、北原武夫と同棲、結婚を繰り返し、「色ざんげ」や「別れも愉し」「おはん」「生きて行く私」で高い評価を受けています。平成8年98歳で死去。宇野千代の「私が建てた家」によると「何しろ、七十五歳になる現在までに、数えて見ると、十一軒建てた勘定になるからだ。」とあります。
★左の写真が今回のテーマの「生きて行く私」、毎日新聞社版です。初版本ですと2万円以上するみたいですが、私のは残念ながら初版本ではありません。
|
《大正6年〜昭和14年》
| 年 月 |
歳 |
住居 |
その他 |
| 明治30年 |
0 |
山口県岩国市 |
生誕 |
| 大正6年 |
20 |
小石川駕籠町 |
藤村忠と上京、露路の奥にある女髪結いの二階に転居 |
| 大正8年 |
22 |
〃 |
藤村忠と正式に結婚 |
| 大正9年 |
23 |
札幌東一条大通り |
北海道拓殖銀行就職の為 |
| 大正10年1月 |
24 |
〃 |
「脂粉の顔」が時事新報の懸賞小説一等に当選 |
| 大正11年4月 |
25 |
東京に上京 |
中央公論5月号「墓を発く」の原稿で366円を貰う |
| 大正11年5月 |
25 |
本郷 菊富士ホテル |
尾崎士郎と同棲 |
| 大正12年 |
26 |
荏原郡馬込 |
馬込に家を建てる |
| 大正13年 |
27 |
〃 |
藤村忠と協議離婚、尾崎士郎と正式に結婚 |
| 昭和4年 |
32 |
世田谷区山崎1405 |
東郷青児と世田谷に転居 |
| 昭和5年 |
33 |
〃 |
尾崎士郎と離婚 |
| 昭和6年 |
34 |
世田谷区北沢2-196 |
淡島に白い家を建てる |
| 昭和9年 |
37 |
四谷区大番町104 |
四谷区大番町の仕舞家(しもたや)二階に転居 |
| 昭和14年4月 |
42 |
小石川区林町62 |
北原武夫と結婚 |
|
 <小石川駕籠町> <小石川駕籠町>
大正6年、宇野千代(20歳)は京都で一緒に住んでいた従兄弟の藤村忠(宇野千代は文中では全て藤村悟と書いている)が三高から東京帝大に進学するのに伴って、初めて東京に上京してきます。その時の事を宇野千代は「生きて行く私」の中で「さて、私たちが東京へ落ち着いたのは、小石川駕寵町の露路の奥にある、女髪結いの二階であった。悟の進学した東京帝大(東大の前身)は、そこから、眼と鼻のところにあったからである。しかし、その頃は故郷の家からの送金は、全く当てに出来なくなっていた、…最後には、本郷三丁目の角にあった、燕楽軒と言う西洋料理店の給仕女になったりした。…食事代のほかに、きまって卓子の上に、五十銭玉の大きな銀貨をぽんと一つおいて、そそくさと立ち去るのであった。その人が、電車道を距てて燕楽軒の真ん前にあった、あの、中央公論社の名編集長である、瀧田樗陰であろうとは、私は夢にも知らなかった。」とあります。宇野千代は燕楽軒でのアルバイトがこれからの人生の大きな岐路になった様です。芥川龍之介、久米正雄を見、今東光に、毎夜駕寵町の家の外まで送ってもらったりしています。
★左の写真は現在の本駒込2丁目、当時の小石川駕籠町付近です。戦災で焼けて、その上、町名も変わってしまっていて昔の面影はなにもありませんが、小学校の名前が”駕籠町小学校”になっており、僅かに面影を留めています。菊坂の入口左側に合った燕楽軒の建物も空襲で焼け、現在は”漆原ビル文京センター”となっています。本郷通りを挟んで丁度向かい側のビルの一階にスターバックス(Starbucks)が入っています。スタバでコーヒーを飲みながら本郷通りを眺めるのも一興ですね! |
 <尾崎士郎と馬込の家> <尾崎士郎と馬込の家>
大正8年8月藤村忠と正式に結婚、翌年卒業後、夫の札幌赴任に伴って(北海道拓殖銀行に勤める為)札幌に転居します。宇野千代の2回目の上京は大正11年4月です。夫を札幌に残して、単身、送ってある小説の件で東京本郷の中央公論社の滝田樗陰に会いに行きます。その時の事を「生きて行く私」では「東京へ着くと、私は真っ直ぐに、本郷の中央公論社へ行った。瀧田樗陰(編集長)は社にいた。三階まで駆け上がったので、私は息がきれた。「あの、あの、私のお送りした原稿は、着いてますでしょうか。もう、お読みになって下すったでしょうか」と言うその私の言葉も終わらない中に、樗陰は、そのときすぐ限の前に積んであった、六、七冊の雑誌の一冊を手にとって、ばさりと、私の限の前に投げ出し、「ここに出てますよ。原稿料も持って行きますか」と、まるで、怒ってでもいるように言ったものであった。忘れもしない、それは大正十一年の四月十二日であった。「中央公論」 の五月号に、私の小説『墓を発く』が載っている。私はぶるぶると足が僕えた。眼の前に投げ出された、この夥しい札束は何であろう。あとで正気に帰ったとき、その札束が私の書いた原稿百二十二枚の報酬である三百六十六円だと知ったとき、私は腰も抜けるほどに驚いたものであった。」とあります。このあと宇野千代は三百六十六円を持って岩国の実家までもどり、ふただび東京の中央公論社まで戻ってきます。「瀧田樗陰は社にいた。はかに先客が二人あった。「これは奇遇だ」と言って、その一人が立ち上がった。それは私も名前くらいは知っていた評論家の、室伏高信であった。「宇野さん、この男は時事新報の懸賞小説で二等になった尾崎士郎ですよ」と、もう一人の若い男を指して、言うではないか。」と尾崎士郎との決定的な出会いがあり(夫を札幌に残したままですが!)、又これが、これからの宇野千代の波乱に富んだ人生の始まりでもあったわけです。このあと二人はしばらくの間、尾崎士郎が下宿していた「菊富士ホテル」に同棲します。その後、二人は大森海岸の小さな宿屋や、白田坂の坂下にある下宿屋、山王の森の中にある家、大森と蒲田の間にある鉄道線路の脇の家などに引っ越していましたが、都新聞 学芸部長の上泉秀信の紹介で荏原郡馬込(現在の大田区南馬込4丁目)に家を建てて移っていきます(大正12年のことです)。
★右の写真の坂の途中の右側辺りが、宇野千代と尾崎士郎が荏原郡馬込(現在の大田区南馬込4-28-11)に建てた所です。当時の家の事を宇野千代は「私が始めて建てた家は藁葺き屋根であった。大森馬込の大根畑の中に建てた。…そんな家でも、ちょっとした工夫はしてあった。南向きに大きな出窓のある六畳の部屋が一間、残りの空間を広い叩土にして、北側に厠がある。…そのたった六畳一間の部屋で、二人の人間が暮していたのである。尾崎士郎と一緒だった。そこで寝起きもし、食事もし、仕事もした。どうしてそれが出来たのか、いまでは信じられない。満でいうと、そのとき私は二十三歳であった。二、三年経った。大根畑の隣地の丘にあった家が火事で焼けた。その焼け跡を借りて、また一軒建てた。必要だからではない。ちょっと建てて見たかったからである。今度の家は赤い屋根の洋館であった。」とあります。大森駅からはかなり遠くて、山王から岡を二つほど越えて20分以上は歩くと思います。昔の人は良く歩きますね、今ではタクシー以外では行けない距離です。今は親類の方が住まわれている様で、宇野の表札が掛かっています。 |
 <東郷青児と世田谷区淡島の白い家> <東郷青児と世田谷区淡島の白い家>
昭和4年には尾崎士郎と分かれ、東郷青児と生活を始めます。「生きて行く私」の中では「扉をあけると、一眼でそれと分かる東郷青児が、首に白い棚帯を巻いたままで出て来た。「仲間が大ぜいいるんですよ。どうですか。一緒にこれから、僕の家まで来ませんか」と言ったと思うと、そのまま、通りかかった車に私を乗せて、走り出したではないか。その夜、私が世田谷の東郷の家に住みついて、そのまま、馬込には帰って釆なかった」。とあります。東郷青児はこの年の初めに情死事件を起こしており、そのために首に白い包帯を巻いていたわけです。東郷とも劇的な出会いでしたが、この出会いも長くは続かなかった様です。昭和9年になると宇野千代は四谷区大番町の仕舞家(しもたや)の二階に転居します。今の信濃町駅の近くです。
★左の写真の左奥に宇野千代と東郷青児が建てた”淡島の白い家”が保存されています。現在は持ち主が変わりましたが、下記の通りそのまま保存されている様です。「あの淡島の家は、抵当などにも入っていたのを、織元の名家である京都の帯の龍村が肩代わりをしてくれて、いまでも、そっくり昔のままの形で、あの大きな黒塗りの円卓子もサンルームも、中二階のあるアトリエも、残しておいてくれている、と言うのであった。」とあります。写真でははっきり見えませんが、左手の方にある家がそのようです。ぜひとも一般公開して欲しいですね。 |
 <北原武夫と小石川区林町> <北原武夫と小石川区林町>
昭和11年 北原武夫と雑誌スタイルを創刊、昭和14年4月1日 北原武夫と結婚 小石川区林町62番地に転居します。「北原武夫と私とは、年齢が十歳も違っていた。私が四十二歳のとき、北原は三十二歳であった。この反対のことは普通であっても、女の方が十歳も齢上、と言うことは、言うまでもなく、大変なことである。それでもなお、平気で、北原と結婚出来ると考えていたとは、何と言うことであろう。実を言うと私は、この年齢のことなど、一度として考えたことはなかった。それはど、北原を愛するのに急であった。いや、愛するのではない。愛している、と自分自身が思い込んでいるのに急だった。」とあります。
★右の写真は当 時の小石川区林町62番地、写真の坂を登って左側に入った所辺りです。現在の文京区千石2−9付近で、当時の家は不明ですが、高台にあり眺めがいいところだったようです。戦災に逢わず焼け残った地域ですが、ここも駕籠町と同じく町名 が変わっています。変わっていないのは小学校の名前だけです。当時の面影がある建物も少なくなっています。(写真と下記の地図はV01から更新されています。正確な番地が分かりましたので写真を撮り直し、地図を改版しました。)
次回は宇野千代の戦中、戦後の住まいを追います。次回を乞ご期待下さい。
|
宇野千代の住居の変遷−1−
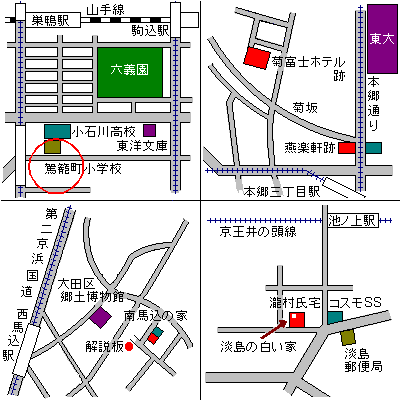
宇野千代の住居の変遷−2−
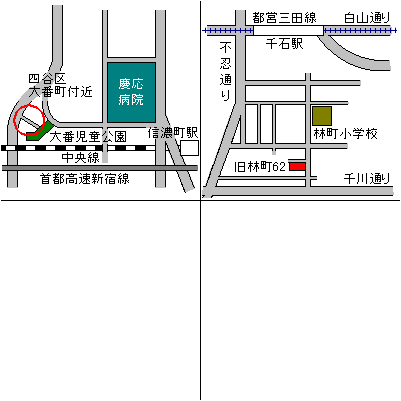
【参考文献】
・家:(日本の名随83)作品社、宇野千代
・生きて行く私:中央公論社、宇野千代
・新日本文学アルバム:新潮社
・ねんじんだより:大田区立馬込図書館
・馬込文士村:大田区立郷土博物館
【住所紹介】
・淡島の白い家:東京都世田谷区代沢3-19-3
・南馬込の家:東京都大田区南馬込4-28-11
・燕楽軒跡:東京都文京区本郷4-37-13 漆原ビル文京センター
●宇野千代の札幌時代を歩く 2001年12月15日 V02L01 |
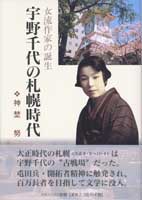 今週は北海道が”どか雪”だそうで、雪ということで札幌を取り上げてみたいと思います(あまり関係ないかな!)。宇野千代は大正9年に夫 藤村忠が東京帝国大学卒業後、北海道拓殖銀行に就職したのに従い札幌に引っ越してきます。宇野千代の「生きて行く私」では「さて、悟が帝大を卒業する一、二カ月前のことであった。駕寵町の女髪結いの二階へ、私たちを訪ねて来た一人の客があった。高森の分家の伯父に当たる人であったが、開墾時代に北海道へ渡って、新聞事業を起こし、成功した男であった。……私たちの北海道行きは決まった。伯父のおいて行った金は、質屋その他の借金を整理し、なお、充分に二人の旅費まで賄うことが出来た。悟は卒業の翌日、東京を発ち、私はこまごました仕事を片付けて、あとから発った。」とあります。女髪結いの二階に訪ねてきた人は北海道タイムス支配人中津井高助で、「生きて行く私」では夫 藤村忠は新聞社に勤めたことになっていますが、本当は北海道拓殖銀行に就職しています。夫の名前も本では藤村悟となっていますが、本名は藤村忠です。このことを宇野千代は「私の最初の良人であり、私の従兄である藤村忠(私ほこの藤村忠と言う名前を、これまでのところ、凡て藤村悟と書いて来た。どうして、そう書いて来たのか、と言うことは私には分からない。これは嘘であるのに、私は嘘を書いた。私の生涯の間で、この人にだけは相済まぬことをした、と言う思いが、せめて、名前を伏せることで、私の気持ちが分かって貰える、とでも思ったのか。勤め先を新聞社と書いたのも、実ほ銀行であった)」。と書いています。夫を裏切った負目から、夫の名前も含めて正直に書けなかったのかと思っています。 今週は北海道が”どか雪”だそうで、雪ということで札幌を取り上げてみたいと思います(あまり関係ないかな!)。宇野千代は大正9年に夫 藤村忠が東京帝国大学卒業後、北海道拓殖銀行に就職したのに従い札幌に引っ越してきます。宇野千代の「生きて行く私」では「さて、悟が帝大を卒業する一、二カ月前のことであった。駕寵町の女髪結いの二階へ、私たちを訪ねて来た一人の客があった。高森の分家の伯父に当たる人であったが、開墾時代に北海道へ渡って、新聞事業を起こし、成功した男であった。……私たちの北海道行きは決まった。伯父のおいて行った金は、質屋その他の借金を整理し、なお、充分に二人の旅費まで賄うことが出来た。悟は卒業の翌日、東京を発ち、私はこまごました仕事を片付けて、あとから発った。」とあります。女髪結いの二階に訪ねてきた人は北海道タイムス支配人中津井高助で、「生きて行く私」では夫 藤村忠は新聞社に勤めたことになっていますが、本当は北海道拓殖銀行に就職しています。夫の名前も本では藤村悟となっていますが、本名は藤村忠です。このことを宇野千代は「私の最初の良人であり、私の従兄である藤村忠(私ほこの藤村忠と言う名前を、これまでのところ、凡て藤村悟と書いて来た。どうして、そう書いて来たのか、と言うことは私には分からない。これは嘘であるのに、私は嘘を書いた。私の生涯の間で、この人にだけは相済まぬことをした、と言う思いが、せめて、名前を伏せることで、私の気持ちが分かって貰える、とでも思ったのか。勤め先を新聞社と書いたのも、実ほ銀行であった)」。と書いています。夫を裏切った負目から、夫の名前も含めて正直に書けなかったのかと思っています。
<当時の札幌>
大正7年(1918)は蝦夷地が北海道と改められた明治2年から数えて満50年になっています。この年に開道50年記念事業として北海道博覧会が開催されています。また大正7年4月には東北帝国大学農科大学が北海道帝国大学と改められています。大正7年には札幌の人口は10万8千人となっています。 |
 <中津井家> <中津井家>
札幌に着いた宇野千代は間借りできるまでということで、中津井家の離れに落ち着きます。「札幌の伯父の家は、南三条の一角にある、宏壮な邸宅であった。私たちは一先ず、この邸の離れに落ち着き、悟ほそこから伯父の新聞社に出勤した。……「千代さん、これが私の足袋ですよ。よく見てごらんなさい。私はこの足袋を、十三年も穿いていたんですよ」と言って、伯母が私に見せてくれた足袋がどんなものであったか。十三年も穿いた、と言うことであったが、その足袋は汚れてはいなかった。幾十回となく洗い晒したものであっただろうのに、汚れてはいなかった。」と中津井家の様子を書いています。宇野千代は60年後に再び札幌を訪れ、中津井家の有った場所を訪ねます。『「あの、十三年も穿いた足袋と言う、あの中津井の伯母の、養子になったと言う人が見つかったんですよ。すぐそこの、北二条西一丁目の角で、中国料理をやっているんですよ」と言う。……清華園ほ小ぎれいな店であった。何よりも、料理が旨かった。食後、ゆったりとした気持ちで、店のそとへ出たのであるが、ふと見ると、その北二条西一丁目の街角が、いま始めて見たところではなく、確かに見覚えのあるところであったような、不思議な気がした。そうだ。ここはあの昔、中津井の、あの大きな邸のあったところだったのだ、と気がつくと、私はちょっとの間、胸が迫るような思いで、そこに立ち疎んだ。』とあります。現在では清華園もなくなり、交差点の角地は空き地になっています。60年後に負目を追いながらここを訪れた宇野千代は感慨深いものが有ったのではないでしょうか。
★左の写真が中津井家が有った所です。交差点の角地で、南三条とありますが、北二条西一丁目一番地が正確な番地です。どうも正確に覚えていなかったようです。今は角地は空き地でその先にはコンピニのローソンがあります。
|
 <松島安吉家> <松島安吉家>
宇野千代は中津井家に一週間ほど間借りしたあと、北海道タイムス支配人中津井高助の部下である松島安吉家に間借りします。「やがて、私たちは東一条の大通りの、すぐ裏手にある露地の奥に間借りをした。悟はそこから伯父の新聞社に出勤したが、その悟の留守の間に、私は何をしたか。私たちの間借りをした部屋は、六畳が畳、二畳が板敷きになって続いていて、その家の、玄関のすぐのところにあった。その部屋のすぐ奥に、大家が住んでいたが、間に、間仕切りのガラス障子があって、いつでも、そのガラス障子を開けたてしては、何かと、私たちの世話をやいてくれたものであった。」とあります。ここでも勤め先が新聞社になっています。ここから北海道拓殖銀行本店へは歩いていけますね。
★右の写真のラーメン屋と隣の結納のお店及び駐車場の所が松島安吉家が有った所です。”東一条の大通り”とありますが、このような場所はなく、正しい番地は南一条西五丁目一番地です。どうも宇野千代は札幌の事は思い出しだ くないようですね。
|
 <北海道拓殖銀行> <北海道拓殖銀行>
宇野千代の夫、藤村忠が勤めたのが北海道拓殖銀行本店です。残念ながら拓銀はもうありませんでした。拓銀は平成9年(1997)9月に北海道銀行との合併計画が破談になったことによりその年の11月破綻しています。北海道内の支店を、札幌に本店のある北洋銀行に譲渡するとともに、北海道以外の支店は中央信託銀行に譲渡しています。ビル自体は残っているのですが、入口の銀行名が変わってし まっています。 入口の柱の所にカンバンを取った跡がまだ残っています。
★左の写真が大通り公園と西四丁目の札幌駅前通りの交差点に有る旧北海道拓殖銀行ビルです。
|
 <古い一軒家> <古い一軒家>
宇野千代はバイトに仕立物をしますが、そのお金で頼母子講をしています。「私の仕立物で得た金は、頼母子講の掛け金になった。毎月、寄り合いがあって、その席で籤を引くのであったが、三カ月目に、思い掛けない大金が、私の手に落ちたのであった。旨い仕組みになっていたもので、その講中には、いまで言う不動産屋とも言うべき男がいて、私はその男の世話で、一軒の家を買い取る、と言う破目になったのであった。……その家ほ東十一条と言う、この通りの一番外れにあった。そんなに遠いところへ越して行くのだと分かったとき、良人の悟はどんな顔をしたか。たぶん、悟は、いつでも私の言うことには、それがどんなに突拍子もないことであっても、文句を言わない、と言うその習慣通りに、一緒に行くことになったのだと思う。」とあります。ここの家が宇野千代が生涯で初めて自分で買った家になりました。このあと十数軒の家を建てていきます。
★右の写真が宇野千代の家が有ったところです。ここでも番地が違います。東十二条とありますがこの番地は存在しません。どこの場所も番地か全然あっていませんね、どうしてでしょうか。正確には大通東七丁目十二番地です。写真を見ていただくと分かりますが現在の岩瀬医院と左隣の駐車場辺りだと思います。
このあと宇野千代は時事新報の懸賞小説に応募し、大正10年1月「脂粉の顔」で第一位を獲得します(一位の賞金は二百円)。ちなみに二位は二人目の夫の尾崎士郎でした。原稿料のうま味にきずき、その年の3月、滝田樗陰の中央公論社に原稿(「墓を発く」)を送りますが、4月になっても返事がこないため、上京し滝田樗陰に会いに行く決心をするわけです。4月12日札幌を出発します。この日が札幌の最後の日になります。この後の話はこちらを見てください。
|
|
「宇野千代の札幌」地図
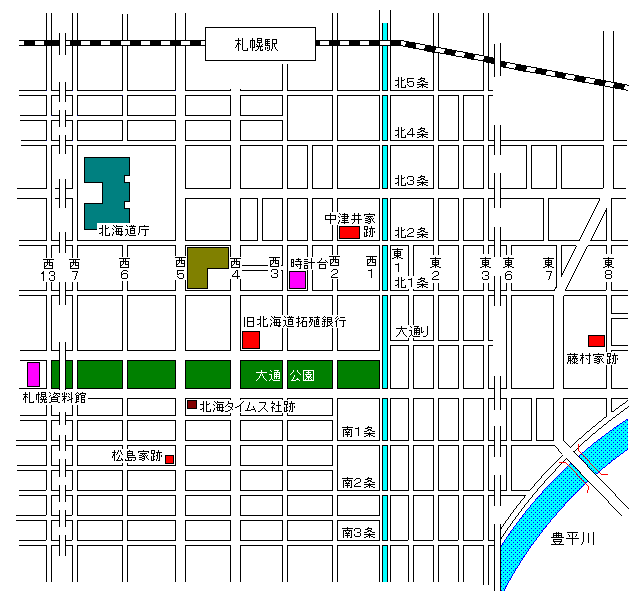
|
【参考文献】
・宇野千代の札幌時代:神埜努、共同文化社
・生きて行く私:中央公論社、宇野千代
・新潮日本文学アルバム:新潮社
|
| ●宇野千代の東京を歩く (戦中・戦後篇) 2001年10月13日 V02L02 |
| 今週は前回の戦前編から引き続いて戦中・戦後を歩いてみます。宇野千代は昭和14年4月1日に北原武夫と結婚しましたが、この二人の関係を追いながら宇野千代の戦中・戦後を追いかけてみたいと思います 。宇野千代が”わたし、あたなが好きよ”と良く言うのは有名ですが、「生きて行く私」の中で「私たちはよく一緒に映画を見に行った。しかし、私は映画を見てはいなかった。北原の傍に腰掛けて、その美しい横顔を、穴のあくはど見詰めているのが、習慣であった。」、とあり、宇野千代の好きという事がどういう事かよく分かりますね、北原武夫がいかに美男子だったかをよく表現しています。 |
《昭和19年〜没まで》
| 年 月 |
歳 |
住居 |
その他 |
| 昭和19年 |
47 |
熱海 |
熱海に疎開 |
| 昭和19年 |
47 |
栃木県下都賀郡壬生町 |
北原の実家の壬生に疎開 |
| 昭和20年 |
48 |
荏原郡馬込 |
東京に戻る |
| 昭和25年 |
53 |
中央区木挽町7-3-13 |
木挽町に転居 |
| 昭和26年 |
54 |
港区南青山3-8-5 |
青山南町に転居 |
| 昭和34年 |
62 |
〃 |
スタイル社倒産、木挽町の家を処分 |
| 昭和39年 |
67 |
〃 |
北原武夫と離婚、尾崎士郎没 |
| 昭和41年 |
69 |
〃 |
那須に土地を購入 |
| 昭和47年 |
75 |
〃 |
北原武夫没 |
| 平成8年6月11日 |
98 |
〃 |
港区の虎の門病院で死去 |
|
 <東武宇都宮線壬生駅> <東武宇都宮線壬生駅>
戦争が激しくなると、小石川区林町から熱海に疎開します。「生きて行く私」では「その年の春、私たちは熱海の来宮駅の近くにある、或る別荘の一室を借りて疎開した。秋になって、つい、その近くに谷崎潤一郎が疎開して来ていて、しばしば、潤一郎自身が私たちのところへまでやって釆たので、私はこの大先輩を迎えて恐催し、何を話題にしたものかと狼狽し熱海に来たのは私たちの方が早かった。食糧の入手については、私たちの方が大先輩であったので、私はその日から、鶏肉、じゃがいも藷、白米、鰤の切り身などが手に入るたびに、谷崎家に通報した。この非常時に、そんなことの出来るのが自慢であったとは、何と言うことか。」とあります。谷崎潤一郎は昭和19年4月、熱海市西山の別荘に家族とともに疎開してきます(上記では秋と書いてありますが)。昭和20年5月には岡山県津山市移っていますので、僅か一年ほどですが宇野千代一家の直ぐ側にいたわけです。しかしながら熱海も安全ではなくなってきた為、夫 北原の実家壬生に疎開する事にします。「やがて、戦争はますます苛烈さを加え、熱海にいるのも危険だ、そう思われたときであった。私たちは折角来た熱海から、北原武夫の郷里である栃木県の壬生へ、またもう一度疎開した。」壬生という所は宇都宮市と栃木市の間でJR線からは離れており、東武日光線で浅草から準急で栃木駅まで行き、宇都宮線乗換で一時間半くらい掛かります。
★左の写真が北原武夫の実家が有った東武宇都宮線壬生駅です。浅草から東武日光線快速で栃木駅まで約1時間(準急だと2時間位掛かります)、そこで宇都宮線(なんと単線でした)に乗り換えて10数分で壬生駅です。駅前は何もなく、ただタクシーが数台待っているだけでした。駅前の通りも人通りがほとんどなく淋しい限りです。 |
 <中央区木挽町> <中央区木挽町>
終戦後二人は、スタイル社の編集部があった四谷区大番町の家が空襲で焼けていたため、宇野千代が昔、尾崎士郎と一緒に住んでいた馬込の家に引っ越します(所有権は宇野千代にあったようです)。そして昭和21年二人はすぐにスタイル社を復活させます。本も最初の頃は売れに売れて事務所も最初は有楽町、次には銀座に構えることが出来た様です。この当時の事を「生きて行く私」では「木挽町の焼け跡を歩いていると、ほんの一、二軒、新しい料理屋風の家の建っている間に、ちょっとした空き地があった。ひょっとしたら、そこは、戦前に、誰それと言われた名のある芸者が、人力車に乗って往来していた街であったか。そこの空き地を、私が買うことに決めたのは、その日の中であった。…金ほいくらかかっても宜かった。その頃、一流の建築士と言われていた、佐藤武夫のデザインで、当時の金で、坪当たり二十五万円と言うことであった。こんなに金をかけた家は、日本中にないと言われた。」とあります。戦後の活字に飢えていた頃の雑誌は飛ぶ様に売れ、儲かって仕方がなかったのではないでしょうか。
★右の写真が昔の地番で木挽町7−3辺り、現在の番地では銀座7−15付近です。木挽町は何度も町名が変わっており、木挽町七丁目から東銀座七丁目と変わり、現在の銀座七丁目に変わっています。写真では丁度BMWが停まっている辺りで、向こうの角から4軒目の筈ですが、共同ビルになっており、丁度ビルの入口辺りと思われます。隣は小料理屋さんなので昔と雰囲気は変わっていませんね。 |
 <銀座五丁目> 2002/11/04 追加 <銀座五丁目> 2002/11/04 追加
銀座に一番館が持っていた借地権を借り受けます。その当時のことを、「一番館はそのとき、四十坪ほどの地面の借地権を持っている。……二十万円を出していれるなら、四十坪を折半して、二十坪は私に渡す。そうゆうのであった。……二、三ヵ月のあとに、木造本建築の建物がそこに出来上がり、私たちは馬込の丘の家から、銀座に引っ越してきた。」、と書いています。よっぽと景気がよかったのですね。
★左の写真が銀座五丁目、電通通りの現在の一番館のビルです。現在は全て一番館のビルになっています。昔は右側の半分がスタイル社のビルだったようです。 |
 <港区南青山> <港区南青山>
最初は快調に売れていたスタイルでしたが、競争雑誌が続々発刊されるに従って売れなくなってきます。そんなときに大きな事件が起こります。「銀座の事務所の入り口から、どかどかと七、八人の洋服を着た男たちが乱入した。「そのまま、そのまま、そこに坐っていて下さい。動かないで下さい」と大声を上げて、おおぜいの社員たちを制止しながら、階下の台所の棚、二階の編集室の机の抽出しから、女事務員たちのハンドバッグの中、裏口のごみ箱の蓋まで開けて、何か探し始めた。国税庁から、不意に査察に釆た男たちだと言うことが、あとで分かった。」とあり、スタイル社が脱税で捕まったのです。借金の返済の為、戦後の景気の良かったときに買い求めた家々を次々に売ります(熱海東山の別荘、木挽町の住居、壬生の実家等)。それでもスタイル社は倒産します。最後に残ったのが青山南町の路地の奥の百坪に建てた小さな家でした。
★左の写真が現在の港区南青山3−8です。右側のビルが宇野ハイツでオフィス宇野が入っています。昔は南青山の路地の奥だったのですが、今は一等地ですね。 |
 <北原武夫の墓> <北原武夫の墓>
北原武夫の実家は栃木県下都賀郡壬生町にあ り、上記にも書いた通り電車では東武宇都宮線の壬生駅です。既に実家はなく駅近くの興光寺にお墓がありますので訪問してきました。北原武夫については「栃木の文学史」によると「北原武夫は昭和十年文芸復興と呼ばれた時代以降、雑誌『文芸』に発表された心理小説『妻』(昭十三・十一) によって芥川賞候補に挙げられ、高見順、太宰治らと並んで文壇の注目を集めた新進作家で……父北原信明は旧壬生藩士の子として生まれ、後に軍医となり、各地に勤務し、小田原で軍籍を離れ開業医となった。武夫はこの小田原で明治四十年に生まれ、ここで育ち、旧制小田原中学から、医家を継ぐべく旧制新潟高校の理科に進んだが、父に抗して中退。慶大に再入学して国文科を卒えている。…彼はスタイル社の負債整理のために昭和二十七年、壬生の家を売却し、完全に父祖の地と絶縁しなくてはならなくなった。現在では北原・宇野夫妻の思い出を語る人々も絶え果てた。」とあります。上記のように昭和27年までは実家もあったようですが、スタイル社の借金のため実家を売却したため、壬生にあるのはお墓のみになった様です。また「生きて行く私」のなかで宇野千代は北原武夫の墓参りにいきます。「私は急に、北原の墓詰りに行く気になり、那須から、その田舎の寺へ廻った。もう、七回忌だ、と思ったのかも知れない。北原の墓ほ、栃木県壬生町の興光寺にある。…興光寺はじきに分かった。…真ん中に、北原家代々の墓と書いた、大きな墓があった。…そこの左側の片隅に、ほんの三寸(約九センチ)角ほどの小さな墓があって、法名ではなく、北原美保子の墓、とあるのも、三十何年か前と同じである。…美保子と言うのほ、北原の最初の妻の名前である。肺結核で、二十にも足らぬ若さで死んだ人で、北原の初期の作品に『妻』と言うのがあるが、その作品の主人公の名前であった。」とあります。
★右の写真が興光寺にある北原家 のお墓です。左の小さいお墓が上記に宇野千代が書いている北原武夫の最初の妻、北原美保子のお墓です。お墓は興光寺の裏にあるのですが、私が訪問したときは丁度お寺の幼稚園の運動会の時で大変な人出でした。お寺の方に聞けなかったので自分で探したのですが、もう一つ北原家というお墓があり(こちらのほうがお寺の近くにあった)大変でした。場所は裏の道路の近くにあります。
|
|
宇野千代の戦後の地図
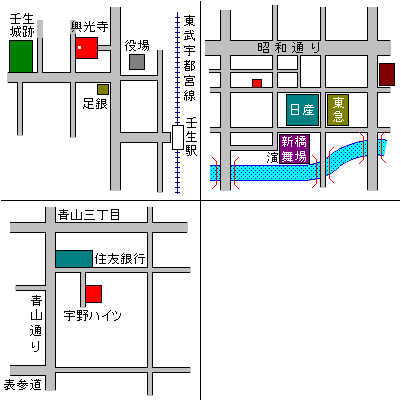
|
【参考文献】
・栃木の文学史:栃木県文化協会
・生きて行く私:中央公論社、宇野千代
・新潮日本文学アルバム:新潮社
【住所紹介】
・興光寺:栃木県下都賀郡壬生町通町7-13
|
|