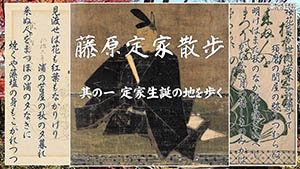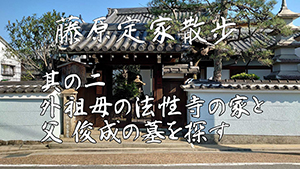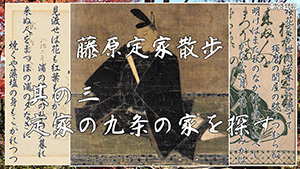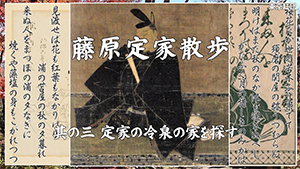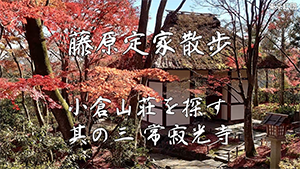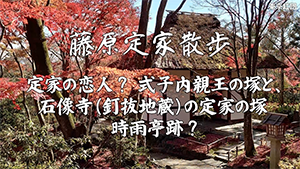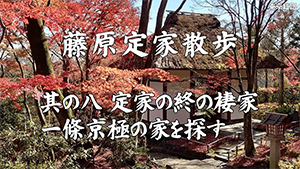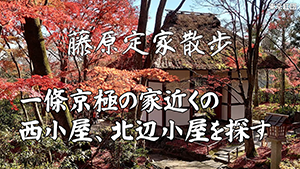<藤原定家散歩 其の一 定家生誕の地を歩く>
今回から藤原定家散歩です。生誕の地から順に歩いていきます。定家は平安時代末期から鎌倉時代初期の貴族で、歌道における御子左家の支配的地位を確立。日本の代表的な歌道の宗匠として永く仰がれてきた。2つの勅撰和歌集「新古今和歌集」「新勅撰和歌集」を撰進したほか、秀歌撰に「定家八代抄」があり「小倉百人一首」も撰じています。定家自身の作で百人一首に収められているのは、「来ぬ人を まつほの浦の夕凪に 焼くや藻塩の 身もこがれつつ」いいですね!(ウイキペディア参照)
<定家の住まいの移り変りを中心とした略年譜>
応保二年(1162) 0歳 父 俊成の五条宅で生まれる (左京五条四坊十三町)
治承四年(1180) 19歳 2月14日 父の五条宅火事により北小路成実朝臣宅に移る
5月23日 法性寺の外祖母の家華亭に移る
(父 俊成は北小路成実朝臣宅のあとは「新玉津神社」のある烏丸の俊成屋敷に移ったとおもわれます)
(藤原定家 村山修一 略年譜参照)
<新玉津島神社(にいたまつしまじんじゃ)>(京都市の説明看板より)
この神社は、文治2年(1186)後鳥羽天皇の勅旨により、藤原定家の父で平安末期から鎌倉初期の歌人として 名高い藤原俊成が、五條大路(現在の松原通)烏丸から室町にかけての自分の邸宅地に、和歌山県 和歌浦の玉津島神社に祀られている歌道の神「衣通郎姫」を勧請したことに由来する。… ちょうどその年、木曽義仲が京に攻め入り、平家一門は都落ちするが、門下の一人である平忠度は、 危険を顧みずこの屋敷に引き返し、「一首を選び、千載和歌集に載せたという。 さざなみや志賀の都はあれにしをむかしながらの山ざくらかな
<俊成社(しゅんぜいしゃ)>(京都市の説明看板より)
この社は平安時代(794年~1185年)末期 から鎌倉時代(1185年~1333年)初期にかけ、 当代一の歌人といわれた藤原俊成卿を祀る。元久元年(1204年)11月30日、九一歳の天 寿を全うした後、町民が民家の裏に祀ったと伝承さ れる。俊成卿の本邸宅は、五条大路(現在の松原通)の 鳥丸小路から室町小路に及び、そのため卿は五条 三位と呼ばれていた。
寿永二年(1183年)「千載和歌集」を撰集せ よとの後白河院の院宣が、俊成卿に伝えられ、時あ たかも木曽義仲が延暦寺に入ったとの報に、平家 公達の都落ちが始まっていた。
平清盛の弟平忠度も、鳥羽のあたりまで落ちて いたが、どうしても、自らの秀歌から一首でも、この 「千載和歌集」に採歌してほしいという想いを抑え 切れず、俊成卿の五条の家まで引き返し、秀歌の 巻物を差し出した。俊成卿は、「ゆめゆめ粗略にはいたしません。 お疑いのないように。」と返答した。千載和歌集は 丈治四年(1188年)に完成し、その中の一首は、 俊成卿の歌の境地を示している。
世の中よ道こそなけれおもひ入る 山の奥にも鹿ぞ鳴くなる 京 都 市
★写真は「藤原定家散歩」の表紙です。専用の表紙を作ってみました。背後は二尊院の参道で、小倉山がはっきりみえます。動画は途中から常寂光寺に変ります。詳細は写真をクリックしてYouTubeを見て下さい。
写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。


二版2021年1月20日 <V01L01> 其の二 外祖母の法性寺の家と俊成の墓を探す
三版2021年2月17日 <V01L01> 其の三 定家の九条の家を探す
四版2021年3月3日 <V01L01> 其の四 定家の冷泉の家を探す
五版2021年3月30日 <V01L01> 其の五 定家の小倉山荘を探す Ⅰ 厭離庵
六版2021年4月20日 <V01L01> 其の六 定家の小倉山荘を探す Ⅱ 二尊院
七版2021年4月27日 <V01L01> 其の七 定家の小倉山荘を探す Ⅲ 常寂光寺
八版2021年5月25日 <V01L01> 其の八 定家の恋人 式子内親王の墓と、石像寺(釘抜地蔵)の定家の塚
九版2021年6月8日 <V01L01> 其の九 定家の終の棲家、一條京極の家を探す
十版2021年6月23日 <V01L01> 其の十 定家の一條京極邸近くの西小屋、北辺小屋を探す
今回から藤原定家散歩です。生誕の地から順に歩いていきます。定家は平安時代末期から鎌倉時代初期の貴族で、歌道における御子左家の支配的地位を確立。日本の代表的な歌道の宗匠として永く仰がれてきた。2つの勅撰和歌集「新古今和歌集」「新勅撰和歌集」を撰進したほか、秀歌撰に「定家八代抄」があり「小倉百人一首」も撰じています。定家自身の作で百人一首に収められているのは、「来ぬ人を まつほの浦の夕凪に 焼くや藻塩の 身もこがれつつ」いいですね!(ウイキペディア参照)
藤原定家散歩 其の二です。治承四年(1180)2月14日の五条宅火事の後、一時 北小路成実朝臣宅に移ります。この場所については、北小路は分かりますが詳細は不明のため、その次に移った法性寺の外祖母の家華亭と、近くにある父 俊成のお墓を探します。ただ、法性寺の外祖母の家華亭については詳細の場所はよく分かりませんでした。父 俊成のお墓については詳細の場所が分かっていましたが探すのが大変でした。
法性寺については延長3年(925)藤原忠平の創建と伝えられています。 藤原氏の寺として栄えますが、その後衰退し現在も法性寺は有りますが、小さなお寺となています。
「京都市の地名_日本歴史地名体系_27_平凡社」を参照すると 当時の法性寺は北は法性寺大路(現伏見街道)一の橋(泉涌寺道) 南は稲荷山(現伏見区)、西は鴨川、東は東山山麓という広大な 地域です。「法性寺御領山指図」を参照しているようです。
<法性寺(ほっしょうじ)>(説明看板)
大悲山一音院法性寺と号する。浄土宗西山禅林寺派の寺である。 当地は延長三年(924)藤原忠平が公家恒例被行脚読経の寺として 建立した寺院(旧法性寺)があった所である。旧法性寺は、創建後 も藤原家の氏寺として栄え、藤原忠通(法性寺入道)の時には、広大な 寺域に大伽藍を構え、京洛21ヶ寺一刹に数えられていた。しかし 以後の兵火により、堂宇は悉く消失してしまった。 当寺は、明治維新以降、旧名を継いで再建されたもので、本堂に安置する 千手観世音菩薩像(国宝)は、旧法性寺の潅頂堂の本尊と伝えられ、 「厄除観世音」の名で知られている。 京都市
★写真は現在の法性寺です。詳細は写真をクリックしてYouTubeを見て下さい。
写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。
藤原定家散歩 其の三です。定家は文治2~3年頃から九条家(五摂家のひとつで九条兼実の頃)に仕へたようで、九条に住んだのは、色々な本を紐解くと建久2年以降ではないかとおもわれます。場所は九条のみしか分からないのですが、その上で探してみました。
<「平安京提要」より>
【九条四坊十一町】
「地名辞典」は、平安時代末期のこの町が藤原頼輔の九条邸(北家)であった 可能性を指摘している。女婿の藤原兼実の九条第 (九条四坊十二町)の北側に頼輔の九条邸北家が あったというからである。また、建久末年ごろ (1199ごろ)から藤原定家が住んだ九条家 をこの町に想定する説もある。
【九条四坊十二町】
平安時代末。藤原(九条)兼実の本邸である九条第が存在したと推定される。(「玉葉」治承二年一〇月二九日・寿永二年七月二一 日条)。兼実が伝領する以前は、兼実の父忠通の 邸宅であったらしい(「山槐記」仁平二年三月一一 日条)。
★写真はタイトルです。詳細は写真をクリックしてYouTubeを見て下さい。
写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。
藤原定家散歩 其の四です。中京区寺町通二条上ルに「此附近藤原定家京極邸址」という石碑がありますが、これが高倉家や冷泉家と呼ばれた家ならば、話は簡単なのですが、単純ではなさそうです。この碑は京都市の「いしぶみを探す」の説明では“定家の京極邸は平安京左京二条四坊十三町にあったと伝える。その邸地より,定家は京極中納言と称された。”とあります。
<「平安京提要」>
【二条四坊三町】
鎌倉時代初期、藤原定家とその子為家は、「冷泉家」「高倉家」と呼ばれた邸宅を所有していた。 (『明月記』建仁二年三月七日・同三年二月一七日・一二月一日条)。この両者は同一の邸宅であった 可能性が高く、その位置は左京二条四坊三町説と五町説とがある。ここでは前者の説に従っておきたい。
【二条四坊十三町】
この町に歌人藤原定家の京極第があったという説があり(『山城名勝志』巻三)、 中京区寺町通夷川下ルにはそれを示す石碑が建てられている。これは、定家の邸宅のうち、一条京 極にあった京極第と、冷泉高倉にあった冷泉家が混同されたためであって、正しくない。
<藤原定家の研究 石田吉貞>
定家の家として多くの書には、二篠の北、京極の西とあるが、それは冷泉の家と 次に逑べる京極の家とが別であることを知らず、兩者を一つにしてしまったもので、明かに誤である。この家の位置は、「詠歌大概抄講談密註」に「北は冷泉裏門今の竹屋町是也南二條表門」とあるのが大體正しいやうであり、 今の二條城の東北に當る。前に記した如く、定家の家として多くの書には、二篠の北、京極の西とあるが、それは冷泉の家と 次に述べる京極の家とが別であることを知らず、兩者を一つにしてしまったもので、明かに誤である。
★写真はタイトルです。詳細は写真をクリックしてYouTubeを見て下さい。
写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。
藤原定家散歩 其の五です。今回は定家の小倉山荘を探します。定家の小倉山荘の場所については諸説あり、決定的なものはありませんが、紅葉を愉しみながらゆっくり訪ねたいと思います。
定家の小倉山荘はいったい何処にあったのか、下記の三案で考えます。
1.厭離庵(えんりあん)のところ
2.二尊院(にそんいん)の南
3.常寂光寺(じょうじゃっこうじ)の北
最初は 1.厭離庵(えんりあん)を訪ねます。
<厭離庵(えんりあん)>ウイキペディアより
京都府京都市右京区にある臨済宗天龍寺派の寺院(尼寺)。山号は如意山。本尊は如意輪観音。 藤原定家が小倉百人一首を編纂した小倉山荘跡にある寺として知られており、境内には書院の他、時雨亭・柳の水(硯の水)、定家塚や定家の嗣子である為家の墓が残されている。また、紅葉の名所としても知られており、秋の紅葉シーズンに限り一般公開がされている。 厭離庵の所在地は、鎌倉時代初期の公家・藤原定家の山荘跡と伝えられる。しばらくして荒廃し、江戸時代初期には定家・為家塚が残るのみとなっていたが、元文元年(1736年)の頃、定家の子孫である公家の冷泉家がわずかに残っていた土台石をもとに修復し、霊元天皇が『厭離庵』という号を授けて、白隠禅師の弟子の霊源が開山したのに始まるという。 その後、安永元年(1772)に覚雄山大福田宝幢禅寺(鹿王院)の末庵となったり、次いで明治20年(1887)1月に大覚寺に属するなどしたが再び荒廃する。明治43年(1910)に白木屋社長の大村彦太郎 (10代)が佛堂と庫裡を建立し、山岡鉄舟の娘である素心尼が住職となって以後は尼寺になる。
★写真はタイトルです。詳細は写真をクリックしてYouTubeを見て下さい。
写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。
藤原定家散歩 其の六です。今回も定家の小倉山荘を探します。定家の小倉山荘の場所については諸説あり、決定的なものはありませんが、紅葉を愉しみながらゆっくり訪ねたいと思います。
定家の小倉山荘はいったい何処にあったのか、下記の三案で考えます。
1.厭離庵(えんりあん)のところ
2.二尊院(にそんいん)の南
3.常寂光寺(じょうじゃっこうじ)の北
今回は、2.二尊院(にそんいん)を訪ねます。
<二尊院(にそんいん)>ウイキペディアより
京都市右京区嵯峨にある天台宗の寺院。山号は小倉山。寺号は華台寺。詳しくは小倉山二尊教院華台寺(おぐらやま にそんきょういん けだいじ)、二尊敎院華臺寺と称する。二尊院の名は、本尊の「発遣の釈迦」と「来迎の阿弥陀」の二如来像に由来する。総門を入った「紅葉の馬場」と呼ばれる参道は、紅葉の名所として知られる。また奥には小倉百人一首ゆかりの藤原定家が営んだ時雨亭跡と伝わる場所がある。また、小倉あん発祥の地として伝わる。 時雨亭跡 - 藤原定家の小倉山荘「時雨亭」跡とされる場所。定家が小倉百人一首を作成した場所とされている。当院の南にある常寂光寺にも時雨亭跡とされる場所がある。平安時代初期の承和年間(834 - 847)嵯峨天皇の勅により円仁(慈覚大師)が建立したと伝わる。以後荒廃するが、鎌倉時代初期に法然の高弟だった第3世湛空らにより再興され、天台宗・真言宗・律宗・浄土宗の四宗兼学の道場となったが、中でも浄土宗の勢力が強く、嵯峨門徒の拠点となった。また、湛空は土御門天皇と後嵯峨天皇の戒師を務めている。 嘉禄3年(1227)に起こった嘉禄の法難の際には、法然の遺骸を天台宗の僧兵から守るために法然廟所から二尊院まで六波羅探題の武士団らに守られながら遺骸が移送された。…
★写真はタイトルです。詳細は写真をクリックしてYouTubeを見て下さい。
写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。
藤原定家散歩 其の七です。今回も定家の小倉山荘を探します。定家の小倉山荘の場所については諸説あり、決定的なものはありませんが、紅葉を愉しみながらゆっくり訪ねたいと思います。
定家の小倉山荘はいったい何処にあったのか、下記の三案で考えます。
1.厭離庵(えんりあん)のところ
2.二尊院(にそんいん)の南
3.常寂光寺(じょうじゃっこうじ)の北
今回は、3.常寂光寺(じょうじゃっこうじ)を訪ねます。
<常寂光寺(じょうじゃっこうじ)>ウイキペディアより
京都府京都市嵯峨にある日蓮宗の寺院。山号は小倉山。旧本山は、大本山本圀寺(六条門流)。百人一首で詠まれる小倉山の中腹の斜面にあって境内からは嵯峨野を一望でき、境内の庭園には200余本のカエデが植えられており、秋は全山紅葉に包まれる。 平安時代に藤原定家の小倉山荘「時雨亭」があったと伝わる地である。 安土桃山時代末の文禄5年(1596)に小笠原秀政の母で日野輝資の養女である延壽院が開基となり、日蓮宗大本山本圀寺第16世日禎が隠棲の地として当山を開いた。その常寂光土のような風情から常寂光寺の寺号が付けられたとされる。 歌人でもある日禎に小倉山の麓の土地を寄進したのは角倉了以とその従兄弟の角倉栄可である。境内は第2世日韶(日野輝資の子)の時代に小早川秀秋らの助力を得て、整備が行われた。
★写真はタイトルです。詳細は写真をクリックしてYouTubeを見て下さい。
写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。
藤原定家散歩 其の八です。今回は千本今出川近くにある、定家の恋人と云われている式子内親王の塚と、石像寺(釘抜地蔵)の定家の塚(時雨亭跡?)を訪ねます。伝説としてはとても面白いです!あまり真実とは思えませんので、そのつもりで見て頂ければとおもいます。
<般舟三昧院 都名所図会>
般舟三昧院は今出川通糸屋町の西にあり、宗旨〔天台、真言、律、浄土〕兼学にして、禁裏内道場と称す。開山は 恵篤上人善空と号し、字は敬川謚は円慈和尚といふ。本尊は阿弥陀仏の座像にして慈覚大師の作なり。帝王歴代の神牌 を安置す。後土御門院の御塔は本堂の西にあり。式子内親王の塚。〔当寺にあり。定家葛の墳と云ふ。むかし此地定家 卿の別荘なり、門前の辻子を定家の辻子といふ。当院初は伏見里指月にあり、文禄三年此地に移す〕
<式子内親王(しょくし/しきし(のりこ)ないしんのう 久安5年(1149)- 建仁元年(1201))
日本の皇族。賀茂斎院。新三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人。後白河天皇の第3皇女。母は藤原成子(藤原季成の女)で、守覚法親王・亮子内親王(殷富門院)・高倉宮以仁王は同母兄弟。高倉天皇は異母弟にあたる。萱斎院、大炊御門斎院とも呼ばれた。法号承如法。
定家は治承5年(1181)正月にはじめて三条第に内親王を訪れ、以後折々に内親王のもとへ伺候した。内親王家で姉の竜寿の小間使いである家司のような仕事を行っていた。定家の日記「明月記」にはしばしば内親王に関する記事が登場し、特に薨去の前月にはその詳細な病状が頻繁な見舞の記録と共に記されながら、薨去については一年後の命日まで一切触れないという思わせぶりな書き方がされている。これらのことから、両者の関係が相当に深いものであったと推定できる。(ウイキペディア参照)
石像寺(しゃくぞうじ)(釘抜地蔵)説明看板より>
正しくは光明遍照院石像寺という浄土宗の寺院で「釘抜地蔵」「くぎぬきさん」として親しまれている。
鎌倉時代初期の歌人・藤原定家、家隆が住んだ所ともいわれており、定家らの墓と伝えるものがある。
★写真はタイトルです。詳細は写真をクリックしてYouTubeを見て下さい。
写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。
藤原定家散歩 其の九です。今回は藤原定家の終の棲家(住処)、一條京極の家を探します。定家60歳前後のこととおもいます。
村山修一さんの「藤原定家」では
“さて一条京極の家は一条京極梅忠社の北に位置し、承久(1219~)以後移って以来、死ぬ まで定家はここを本拠とした。”
とあり、正確な移転時期は難しそうです。場所については、一条京極なので、一条通の上、東京極通の東であることがわかりますが、東京極通の東は平安京の条里からは外れており、正確な場所を探すのは難しそうです。
<明月記>
“安貞元年十一月七 日 「南隣梅忠社北群盗入ル」”
とあるので、梅忠社の北にあることがわかります。
<平家物語 巻第一 御輿振>
“さる程に山門の大衆、国司加賀守師高を流罪に処せ られ、目代近藤判官師経を禁獄せらるべき由、奏聞 度々に及ぶといへども、御裁許なかりければ、日吉の 祭礼を打ち止めて、安元三年四月十三日の辰の一点 に、十禅師、客人、八王子、三社の神輿、飾り奉っ て、陣頭へ振り奏る。さがり松、きれ堤、賀茂の河 原、糺、梅ただ(梅忠社)、柳原、東北院の辺に、白大衆、神 人、宮仕、専当、満ち満ちて、いくらといふ数を知らず。”
とあるので、梅忠社は東北院の北にあるのが分かるのですが、 梅忠社や東北院の位置から定家の一條京極の家を探すのは無理そうなので、もう一冊参考図書を見てみます。
<高橋康夫さんの「京都中世都市史研究 (思文閣史学叢書)」>を参照
定家邸の西の小路は東京極大路末、定家邸は一条京極より一軒挟んで北、定家邸の北は転法輪辻子(武者小路)(詳細の説明は長くなるので省きます)
これでだいたいの場所が分かります。あとはYouTubeを見て下さい。
★写真はタイトルです。詳細は写真をクリックしてYouTubeを見て下さい。
写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。
<藤原定家散歩 其の十 西小屋、北辺小屋を探す>
藤原定家散歩 其の十です。今回は村山修一さんの「藤原定家」では、”洛中の邸宅はこのほか方違のために臨時に宿泊する程度の小さなものがニ~三あったらしい。“とありましたので、この西小屋、北辺小屋を探します。方違えとは、外出または帰宅の際、目的地に特定の方位神がいる場合に、いったん別の方角へ行って一夜を明かし、翌日違う方角から目的地へ向かって禁忌の方角を避けたようです。
<方違え(かたたがえ、かたちがえ(ウイキペディア参照)>
陰陽道に基づいて平安時代以降に行われていた風習のひとつ。方忌み(かたいみ)とも言う。 外出や造作、宮中の政、戦の開始などの際、その方角の吉凶を占い、その方角が悪いといったん別の方向に出かけ、目的地の方角が悪い方角にならないようにした。 外出または帰宅の際、目的地に特定の方位神がいる場合に、いったん別の方角へ行って一夜を明かし、翌日違う方角から目的地へ向かって禁忌の方角を避けた。
<西小屋について>
「明月記」寛喜3年(1231)3月28日条
廿八日、甲寅、朝天陰、雨間降、巳時蒼天忽霽、夕日殊 鮮、夜深宿西小屋、[轉法輪辻子南、富小路まへ、小輔入道密々寄宿屋請受、]待鷄鐘之間 聞前聲令見一條面、行幸松明見云々、遅々如何、不經 幾程鐘聲忽報、即歸宅付寢之後、宰相來宿云々、
<辺小屋が難題>
「明月記」を参照するのですが、富小路等の路の具体的な名前が書かれていません。 村山修一さんの「藤原定家」では “「北辺小屋」というのは京極邸からさほど離れていず、東北院・近隣の祭礼行事 河崎惣社が近くにあって毎年夏には宗教的な娯楽行事が催され、そのざわめきが 邸の中まで聞えてきた。”
これでだいたいの場所が分かります。あとはYouTubeを見て下さい。
★写真はタイトルです。詳細は写真をクリックしてYouTubeを見て下さい。
写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。