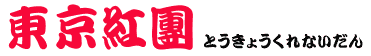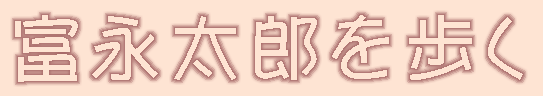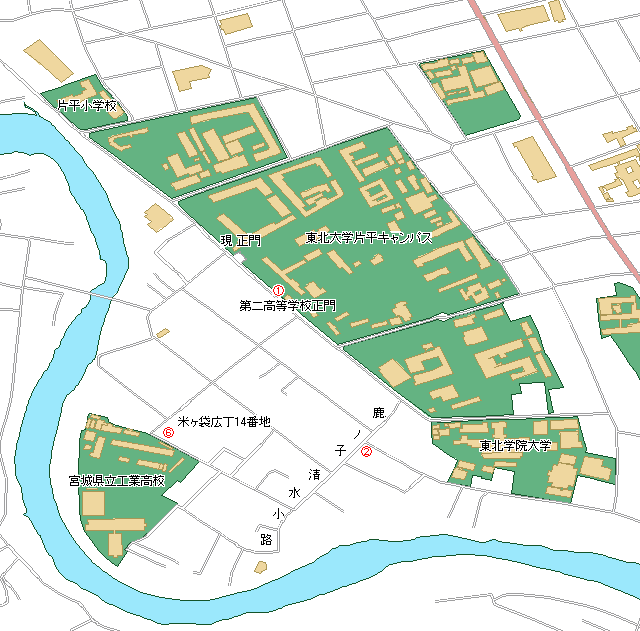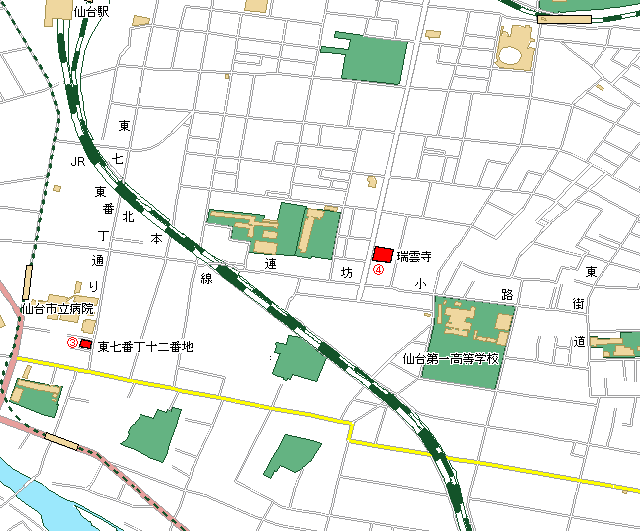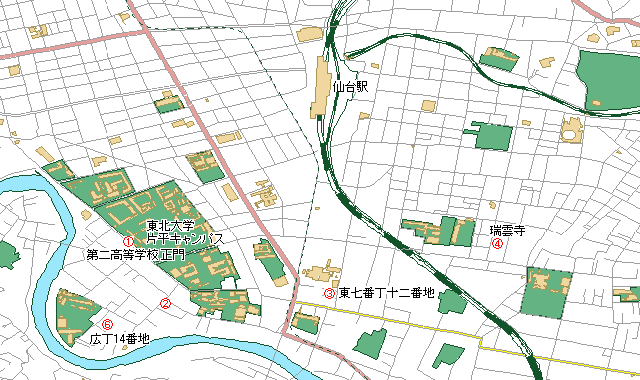大正八年九月、富永太郎は東京府立第一中学校から第二高等学校に入学します。旧制高等学校とは、明治27年(1894)の「高等学校令」で高等中学校の名称が高等学校に変更された以降の官立高等学校のことをいいます。当初は全国に八校の高等学校が設立されます(第一高等学校が東京、第二高等学校が仙台、第三高等学校が京都、第四高等学校が金沢、第六高等学校が岡山、第七高等学校造士館が鹿児島、第八高等学校が名古屋)。大阪と福岡、広島が設立されず弘前や水戸等は後になって設立されています。当初、高等学校は専門学部4年、大学予科(後に本科)3年制に分かれており、京都の第三高等学校には大学予科がありませんでした(後に開設)。そのため、旧帝大に入るための大学予科のある第二高等学校を多くの生徒が受験したようです(第一高等学校は難しく、他は遠かった!!)。「…第二高等学校の創立は明治二十年の四月にまでさかのぼる。 明治十九年四月「中学校令」が発布されて、全国を五区に分画し、毎区に一つの高等中学校を設置することになった。その結果、同年十一月に高等中学校設置区域が定められて、宮城・福島・岩手・青森・山形・秋田の東北六県をもって第二区が編成され、ついで十二月、第二区の高等中学校は仙台に置かれることに決定した。…… 本校舎の敷地は、すでに二十一年二月十四日に仙台市片平丁元陸軍省用地に定められていたので、この年の七月十一日から新校舎の建築に着手した。翌年七月十九日に至って新築校舎中、本館が落成し本省から仮交付を受けた。…… 門は赤レンガの角柱一対で、扉がなく、鉄鎖一本を渡すだけのものであるが、跨いだ者は未だかつて一人もなかった。この門はその後、北六番丁に運ばれて、武道寮の正門となっていたが、現在は富沢分校内、二商記念館前に移されてある。終戦後、二高の三神峯移転当時の学生が、大八車で運んだのである。…… 明治二十七年(一八九四)六月二十五日に、「高等学校令」が発布されて、各高等中学校はそれぞれ高等学校と改称されることになった。そこで本校も第二高等学校と改称するにいたった。新制の高等学校は専門の学科を教授するところであって、あわせて大学に入学するもののために大学予科を設けることになり、七月十二日、二高には医学部および大学予科(一部・二部)が置かれた。大学予科に三部が設けられたのは、三十一年六月になってからである。ところが、この学制改革において、京都の第三高等学校には大学予科が設けられなかったので、大学入学を希望する同校の生徒七八名が、二高に転学してきた。…」。 今以上に当時は受験が大変だったようで、競争倍率が5〜7倍あったそうです。高等学校は全国で八校しかないですから当然です。No高等学校の定員と旧帝大の入学定員がほぼ同じだったようで、No高等学校に入りさえすれば旧帝大には簡単に入れたようです。太宰が弘前高等学校から東京帝大に入ったのも分かりますね。
★左上の写真は東北大学片平キャンパスにある旧制第二高等学校正門です。第二高等学校は元々片平丁(下記の地図参照)の東北大学片平キャンパスにあり、後に北六番丁に移っています。正門も北六番丁に移ったのですが、昭和43年に東北大学片平キャンパスの元の位置に戻されました。