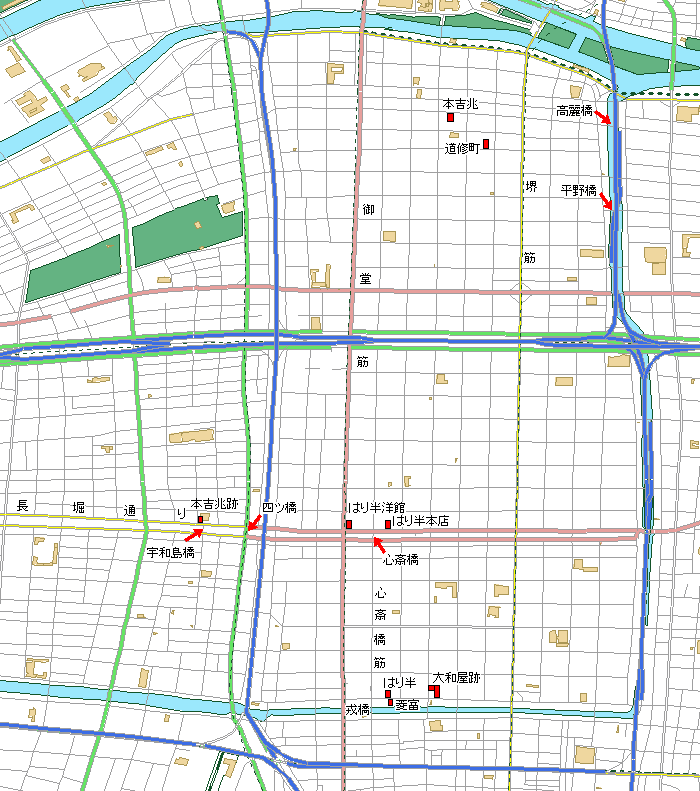ここ大阪でも昭和10年代の有名なお店が登場しています。まず最初は「播半」です。明治十年(1877)頃に心斎橋の北話で創業した大阪でも由緒ある料亭です。西宮から少し山手に入った甲陽園近くにも店を出し、戦前は大阪市内三店と甲陽園の四店で営業されていました。心斎橋の北詰に二店あったりしたのですが、大阪のお店は戦災で全て焼けています。戦後も甲陽園の店だけは残っていましたが、昨年に廃業され、跡地にはマンションが建つ予定になっています(反対運動が盛んです)。「本吉兆」のように戦後大阪市内でお店を開いていればこのご時世でも生き残れたかもしれません。
「…幸子は考えて、まだ滞在が長びくのであったら、旅館へ移る方がよいかも知れない、浜屋と云う家は行ったことはないけれども、そこの女将はもと大阪の播半の仲居をしていた人で、亡くなった父もよく知っていたし、自分も「娘さん」時代から顔見知りの仲であるから、始めての旅館へ泊るようなものではあるまい、…」。
「細雪」に書かれている「播半」は心斎橋北詰のお店だとおもいますが、北話には西と東に二店ありました。本店が東側のお店です。
★左の写真は心斎橋北話を撮影しています(左端が心斎橋筋です)。最も、心斎橋は欄干だけで川は埋め立てられて残っていませんが!
「…義兄の本当の腹の中は、大阪で父の法事をすればどうしても華美になり、無駄な費えが懸るのを恐れたのであろうと、幸子は察していた。何しろ父は芸人を晶眉にした人なので、三回忌の時迄は俳優や芸妓などの参会者も相当にあり、心斎橋の播半での精進落ちの宴会は、春団治の落語などの余興もあって、なかなか盛大に、蒔岡家花やかなりし昔を偲ばせるものがあった。それで、辰雄はその時の負担に懲りて、去る昭和六年の七回忌には案内状などもずっと内輪にしたのだけれども、矢張年忌を忘れずにいたり、聞き伝えたりして来る人々が多かったために、予定したように地味にする訳に行かなくなり、最初は料理屋での 宴会を止めてお寺で弁当を出すつもりにしていたのが、結局又播半へ持って行くことになってしまった。…」
「播半」について調べるには、女将であった乾御代子さんが書かれた「御代女おぼえがき」という本が一番いいとおもいます。下記に「はり半」の所在を記載しておきます。下記の記載以外に江戸橋支店と堀江店があったようです。