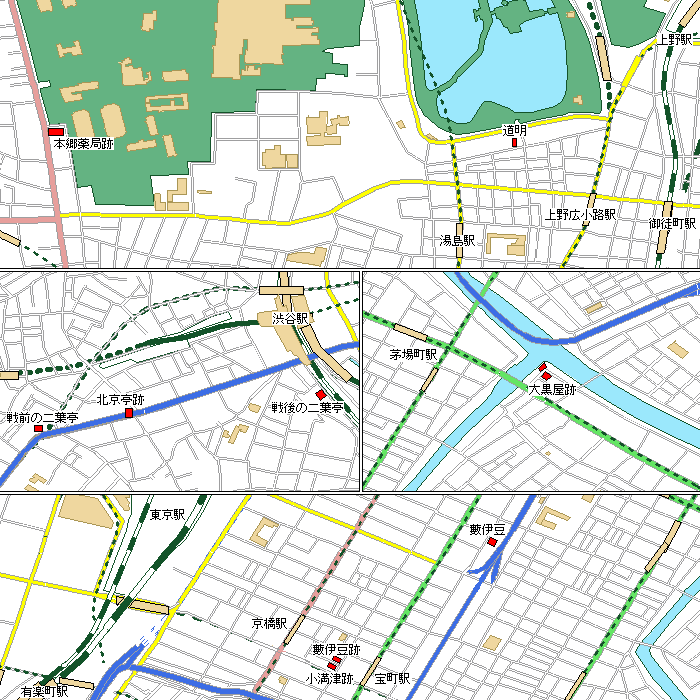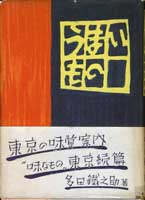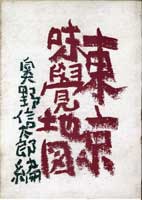前回も書きましたが、谷崎潤一郎の「細雪」は阪神間を中心としたお話のはずなのですが、京都はともかくとして、東京のお話もかなりのページを割いて書かれています。登場人物が大阪船場の古いのれんを誇る蒔岡家(まきおか)の四姉妹(鶴子、幸子、雪子、妙子)なので、阪神間のお話となったのでしょう。特に東京の描写では昭和10年代の有名なお店が登場しています。前回は銀座を中心にして歩きましたので、今回は池之端、日本橋、渋谷、本郷、そして鰻屋を歩きました。ただ、現在も残っているお店は少なく、池之端の「道明」と日本橋の山本海苔店のみが現存していました。
「…午後には四人で池の端の道明、日本橋の三越、海苔屋の山本、尾張町の襟円、平野屋、西銀座の阿波屋等を廻って歩いたが、生憎残暑のぶり返した、風はあるけれども照り付ける日であったので、三越の七階、ジャアマンベーカリー、コロンバン等々、方々で一と休みしては渇きを癒さねばならなかった。お春は移しい買物の包を持たされて、荷物の中から首を出したようになりながら、今日も顔じゅうに汗を沸かして三人の跡から附いて来たが、三人も皆めいめいに一つか二つ提げていた。そしてもう一度尾張町へ出、最後に服部の地下室で又幾つかの買い物をすると夕飯の時刻になったので、ローマイヤアは気が変らないからと、数寄屋橋際のニュウグランドへ上ったのは、宿へ帰って食べるよりも時間が省けるからでもあったが、一つには、今夜限りで又暫くは会えなくなるであろう雪子のために、彼女の好きな洋食の卓を囲み、生ビールを酌んで当座の割れを惜しもうと思ったからであった。…」。
上記に書かれている日本橋の三越はあまりに有名なので特に解説はしません。尾張町の襟円、平野屋、西銀座の阿波屋、ジャアマンベーカリー、ローマイヤは前回の銀座編で紹介しました。今回は池之端の「道明」です。組紐で有名だそうで、残念ながらお店には入りませんでした。池之端の「道明」について書かれた本を頼んでいますので、到着次第追加改版します。
★左の写真は日本橋三越前の
「…嘉永二年(一八四九) に初代山本徳治郎(幼名伊之助)が山本海苔店を創業した場所は、日本橋室町一丁日で、寛永九年(一六三二) に作製された「寛永江戸図」、正確には「武州豊嶋郡江戸庄図」にも”むろ町”と記載されている古い町である。
……。山本海苔店が創業した嘉永二年といえば、ペリー来航の四年前にあたり、時代が大きくうねっていたころだが、新参者にとって海苔業界の商いは楽ではなかった。
文化年間(一八〇四〜一七)まで海苔の老舗は浅草に集中しており、雷門前並木町の永楽屋庄右衛門、正木屋四郎左衛門、長坂屋伝助、井筒屋源七、尾張屋庄吉、雷門西広小路の木屋伝兵衛、仲兄世の大黒屋文右衛門、田原町三丁目の中島屋平右衛門、諏訪町の住吉屋藤兵衛などが、江戸城の御本丸や西丸、徳川御三家、諸侯、それに東叡山寛永寺などのご用達をつとめていたからだ。
これらの浅草海苔問屋は、品川や大森の生産地との結びつきが強く、集荷権を握っていて、日本橋の海苔商が割り込む余地は少なかった。
しかし、文政三年(一八二〇)に浅草雷門前並木町の永楽屋庄右衛門が、主要な仕入れ先である大森椛谷での海苔の採取権をめぐる不正事件に連座して処罰されたのが後々まで響いて、しだいに浅草の海苔問屋の勢力が弱まり、日本橋の海苔商でも大森あたりの海苔を扱うことが少しずつできるようになった。…」
どのお店も最初は大変です。次に大変なのは三代目なのですが、このへんはうまくいったようです。続きは本を呼んでください。その他「細雪」に掲載されている「コロンバン」、「数寄屋橋際のニュウグランド」は銀座の地図に掲載しておきます。