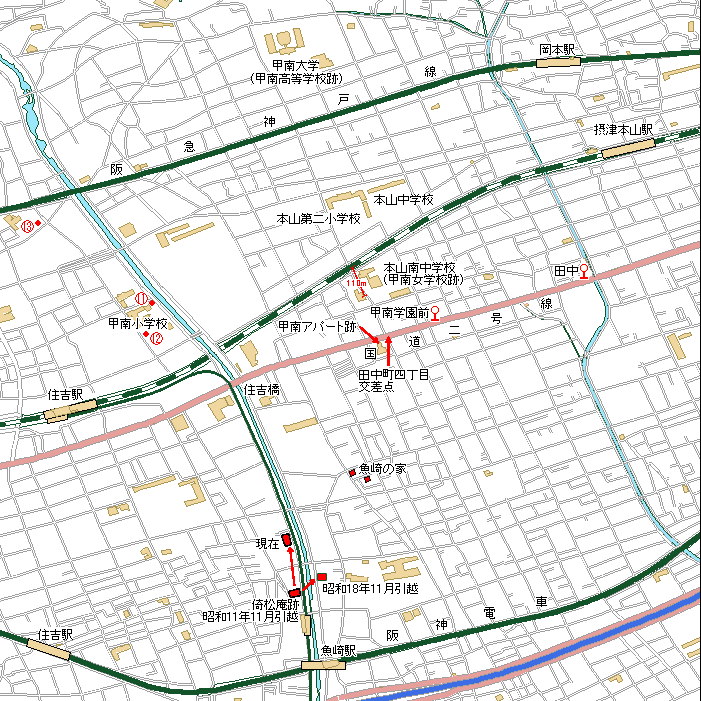谷崎潤一郎が「細雪」を書いたのが住吉川沿いの倚松庵 でした。この倚松庵に谷崎潤一郎は昭和11年11月から昭和18年11月まで、丁度7年間住んでいます。「細雪」は昭和13年前後の時代を描いていますから、丁度この倚松庵に住んでいた頃になるわけです。
「…いったいこの家は大部分が日本間で、洋間と云うのは、食堂と応接間と二た間つづきになった部屋があるだけであったが、家族は自分達が団欒をするのにも、来客に接するのにも洋間を使い、一日の大部分をそこで過すようにしていた。それに応接間の方には、ピアノやラジオ蓄音器があり、冬は煙炉に薪を燃やすようにしたあったので、寒い時分になると一層皆が其方にばかり集ってしまい、自然そこが一番板かであるところから、悦子も、階下に来客が立て込む時とか、病気で臥る時とかの外は、夜でなければめったに二階の自分の部屋へは上って行かないで、洋間で暮した。二階の彼女の部屋と云うものも、日本間に西洋家具の一揃が備えてあって、寝室と勉強部屋を兼ねるようにしてあったのだけれども、悦子は勉強するのにも、ままごと遊びをするのにも、応接間ですることを好み、いつも学校用品やままごとの道具をそこら一杯散らかしているので、不意に来客があったりすると、よく大騒ぎをすることがあった。…」。
上記は「細雪」が描いている蒔岡(まきおか)幸子の芦屋で住んでいる家の様子です。この蒔岡(まきおか)幸子の家の様子は谷崎潤一郎が住んでいた倚松庵と瓜二つなのです。谷崎潤一郎は倚松庵をモデルにして「細雪」を書いたのだとおもます。「細雪」では隣家として「シュトルツというドイツ人の一家」が書かれていますが、この倚松庵の南西に「シュルンボム」というドイツ人が住んでおり、そのまま使ったようです。
★左上の写真は現在の倚松庵 です(倚松庵の二階から住吉川を撮影しています)。離れ以外は当時のままですが、移築されています。現在の場所から南に120mが本来の場所だそうです。この倚松庵は川沿いで高さがあったため、阪神大水害は免れています。
★右の写真は倚松庵から住吉川を上流に上がった
「…たとえば住吉川の上流、白鶴美術館から野村邸に至るあたりの、数十丈の深さの谷が土砂と巨岩のために跡形もなく埋ってしまったこと、国道の住吉川に架した橋の上には、数百貫もある大きな石と、皮が擦り剥けて丸太のようになった大木とが、繁々と積み重なって交通を阻害していること、その手前二三丁の南側の、道路より低い所にある甲南アパートの前に多くの屍骸が流れ着いていること、それらの屍骸は皆全身に土砂がこびり着いていて顔も風態も分らぬこと、神戸市内も相当の出水で、阪神電車の地下線に水が流れ込んだために乗客の溺死者が可なりあるらしいこと、── これらの風説には臆測や誇張も加味されていたに違いないのであるが……」。
写真の住吉橋は現在は架け直されて新しい橋になっていました。新しい橋の写真 (同じ場所から撮影)を掲載しておきます。
この住吉川添いには阪神大水害の記念碑がいくつか作られていますが、住吉川右岸の甲南小学校には、東北の角に