<松江駅>
松江での立原道造については、本人の「長崎ノート」と、松江での宿泊先である山根薫氏のエッセイ(立原道造全集
第五巻の月報)しかありません。山根薫氏は下記にも書かれていますが、堀辰雄と東京帝大の同級生で、そのつながりから、手紙でのやりとりがあり、親しくなったものとおもわれます。
立原道造の「立原造造全集」、”第五巻 月報”から。
「立原道造君との出会い
山根薫
立原君が、当時松江に住んでいた拙宅に数日を過したのは昭和十三年の十一月であり、これが立原君との最初の、そしてまた最後の出会いであった。
堀辰雄から山陰旅行をする立原をよろしくとの手紙をもらったのが機縁であった。堀は一高の理科乙類で机を並べた同級生であった。そのころの堀はふくよかな丸顔の美青年であった。医学コースを選んだのであったが、堀も私も医者にはならないでしまった。堀はたしか国文学へ行ったと思うし、私は胸を患い、休学しては登校するという状態であったため医者になるのをあきらめ、心理学を選ぶことになった。こうした事情から堀との交友も疎縁になってしまった。
やがて作家として立った堀と旧交をあたためる機会をふたたび持つことになった。若いころ文学少女であった家内が堀の指導を望んだので、かれに手紙を出すことになった。かれは親切な手紙をくれた。そしてやがて沢西健氏を通じて同人雑誌「偽画」へ参加するよう呼びかけてくれた。沢西氏は手紙の中で、「偽画」は自分と立原道造とが中心になっていて、堀の指導をうけていること、立原は「四季」にも詩をのせていることなどを書きしるしていた。…」
当時の山根薫氏は、当時 旧制松江高等學校の先生で、東京帝大卒業後すぐに松江にきたものとおもわれます。旧制松江高等学校は大正9年(1920)に設立された旧制の高等学校です。旧制高等学校はナンバースクールとネームスクールに分けられ、ナンバースクールは明治期に設立されていますので、ネームスクールはかなり遅れての設立となります。因みに旧制高等学校は、一高、二高、三高、四高、五高、六高、七高、八高、新潟、松本、山口、松山、水戸、山形、佐賀、弘前、松江、大阪、浦和、福岡、静岡、高知、姫路、広島までです。旧制松江高等學校は現在は国立島根大学になっています。
立原道造の「長崎ノート」からです。
「十一月二十八日
僕は今極端に疲れてゐる。松江に着いたらどうかなるだらう。松江に明日境港から船で行く計企もつくって企もつくってみてはすぐにくづしてしまふ。今夜五時半ごろ松江に着いたら先刻から書きつづけたおまへへの手紙を投函することをたったひとつのねがひにしながら、もう米子をすぎて日はくれた。…」
立原道造は松江にかなり疲れて到着したようです。松江滞在は三泊四日で、滞在先で休養はあまりせず、寒い中を出歩いていたようです。これでは病気は良くなりません。悪くなる一方です。
★上記の写真は現在の松江駅です。明治41年(1908)に開設されています。当時の松江駅の写真(出典:アート今岡殿)を掲載しておきます。二代目の駅舎は昭和28年ですから、一代目の駅舎はそうとう長く使われていました。現在の駅舎は三代目になります。又、山陰本線が全通したのは昭和8年(1933)ですから、立原道造が山陰を訪ねるわずか5年前のことです。ですから、立原道造が訪ねてみたかった理由も分かります。
【立原 道造(たちはら みちぞう、大正3年(1914)7月30日 - 昭和14年(1939)3月29日)】
大正3年(1914)、立原貞次郎、とめ夫妻の長男として日本橋区橘町(現:東日本橋)に生まれる。東京府立第三中学(現東京都立両国高等学校)から第一高等学校に進学した。堀辰雄、室生犀星との交流が始まる。昭和9年(1934)東京帝国大学工学部建築学科に入学した。建築学科では岸田日出刀の研究室に所属。丹下健三が1学年下に在籍した。帝大在学中に建築の奨励賞である辰野賞を3度受賞した秀才。昭和11年(1937)、シュトルム短篇集『林檎みのる頃』を訳出した。翌12年(1938)、石本建築事務所に入所した道造は「豊田氏山荘」を設計。詩作の方面では物語「鮎の歌」を『文藝』に掲載し、詩集『ゆふすげびとの歌』を編んだ。詩集『萱草に寄す』や『暁と夕の詩』に収められたソネット(十四行詩)に音楽性を託したことで、近代文学史に名前をとどめることとなる。昭和13年、静養のために盛岡、長崎に相次いで向かうが、長崎で病状が悪化、12月東京に戻り入院、その旅で盛岡ノート、長崎ノートを記する。昭和14年、第1回中原中也賞(現在の同名の賞とは異なる)を受賞したものの、同年3月29日、結核のため24歳で夭折した。(ウイキペディア参照)


●立原道造の世界 【長崎ノート 松江編Ⅰ】
初版2011年12月3日
二版2012年7月2日 <V01L01> 森永の写真入替と普門院を追加 暫定版
二版2012年7月2日 <V01L01> 森永の写真入替と普門院を追加 暫定版
暫く休んでいましたが12月から再会します。今回も「立原道造の世界」の「長崎ノート」を引き続き掲載します。前回は舞鶴から松江までを掲載しましたが、今回は松江での立原道造を歩きます。松江は二回に分けて掲載する予定で、最初は松江市内を歩きます。
立原道造の松江市内地図
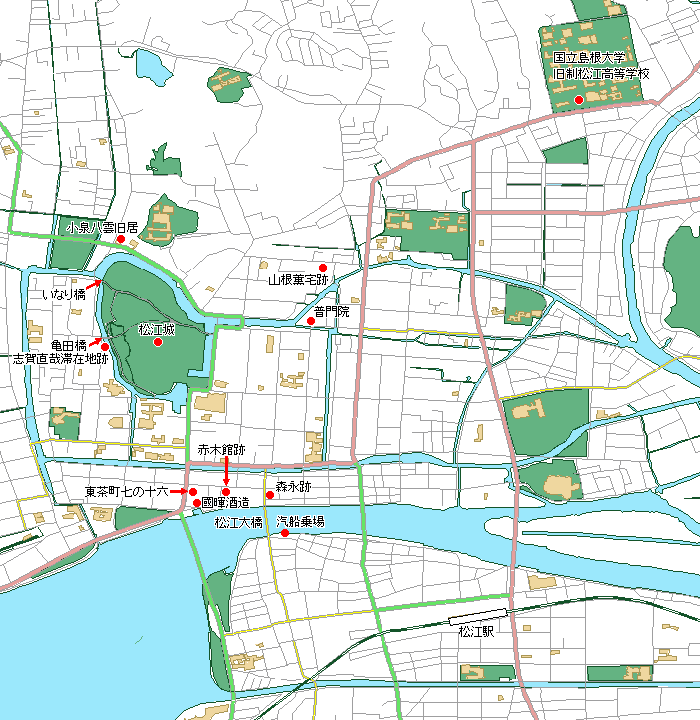
<山根薫宅>
立原道造が松江で宿泊したのが、堀辰雄の友人、山根薫氏宅でした。山根薫氏宅は松江城の直ぐ近くでした。
立原道造の「立原造造全集」、”第五巻 月報”からです。
「立原道造君との出会い
山根薫
… 美しい宍道湖のある町ではあるが、彼を迎えたころの松江は、すでに長い冬に入ろうとするきざしをみせていた。空の深い秋の日は終りを告げ、お忌み荒れの時期であった。松江郊外にある佐田神社のお祭りの前後には毎年大しけがやってきた。このお祭りは、出雲の神社に参集した全国の神々が会議を終っ七、お別れの宴をはる日である。このお忌みの日に土地の人々は神々のじゃまにならないよう気をつけなければならない。この日の前の大あらしで海から白蛇が打ちあげられると、翌年の豊作が予報されると考えられていた。
立原君がきたときには、あらしはなかったように思うが、暗い山陰の空は陰うつな気拝を与えたのではないかと思う。鳥栖で投函したハガキに「長崎へ入る最后のためらいのように佐賀の町を歩きまわり、さんさんと降りそそぐ太陽」を讃美しているのも、山陰の天気との、あまりにも大きい対照に驚いたからにちがいない。
彼の泊った拙宅の二階の窓からは、北山連山が遠く望まれ、南の縁からは、千鳥城と木立ちとを区切ったどんよりとした空にたくさんの烏が群れてとぷのがみえた。「静かなところですね」と何度かいっていた。…」
冬の日本海側は、曇り空の寒々しい日が多く、立原道造にとっては耐えられない日々だったとおもいます。
★写真は現在の松江市北堀町です。正面のやや左側にお城があります。山根氏宅跡は、写真の左側、赤いコーンがあるところです。
立原道造が松江で宿泊したのが、堀辰雄の友人、山根薫氏宅でした。山根薫氏宅は松江城の直ぐ近くでした。
立原道造の「立原造造全集」、”第五巻 月報”からです。
「立原道造君との出会い
山根薫
… 美しい宍道湖のある町ではあるが、彼を迎えたころの松江は、すでに長い冬に入ろうとするきざしをみせていた。空の深い秋の日は終りを告げ、お忌み荒れの時期であった。松江郊外にある佐田神社のお祭りの前後には毎年大しけがやってきた。このお祭りは、出雲の神社に参集した全国の神々が会議を終っ七、お別れの宴をはる日である。このお忌みの日に土地の人々は神々のじゃまにならないよう気をつけなければならない。この日の前の大あらしで海から白蛇が打ちあげられると、翌年の豊作が予報されると考えられていた。
立原君がきたときには、あらしはなかったように思うが、暗い山陰の空は陰うつな気拝を与えたのではないかと思う。鳥栖で投函したハガキに「長崎へ入る最后のためらいのように佐賀の町を歩きまわり、さんさんと降りそそぐ太陽」を讃美しているのも、山陰の天気との、あまりにも大きい対照に驚いたからにちがいない。
彼の泊った拙宅の二階の窓からは、北山連山が遠く望まれ、南の縁からは、千鳥城と木立ちとを区切ったどんよりとした空にたくさんの烏が群れてとぷのがみえた。「静かなところですね」と何度かいっていた。…」
冬の日本海側は、曇り空の寒々しい日が多く、立原道造にとっては耐えられない日々だったとおもいます。
★写真は現在の松江市北堀町です。正面のやや左側にお城があります。山根氏宅跡は、写真の左側、赤いコーンがあるところです。
<志賀直哉滞在地>
立原道造は松江市内を少し歩いていたようです。余り大きくない町ですが、お城と宍道湖に囲まれて、分かりやすい街並みです。又、立原道造は志賀直哉や小泉八雲の松江での住居などを巡っています(志賀直哉は松江での滞在記を書いていますので、ひょとしたら立原道造は事前に読んでいたのかもしれません)。
立原道造の「立原造造全集」、”第五巻 月報”からです。
「立原道造君との出会い
山根薫
… 勤務のあった私は、どこへも案内してあげなかった。ひとりで志賀直哉がかつて住んでいた家のあたりや、小泉八雲の旧居をたずねたりしたようであったが、たいていは家内や家内の友だちと文学の話などをしていた。元気になって東京へ帰ったら、雑誌をつくって一緒に勉強しょうということになったと家内がうれしそうに話していたことを思い出す。
松江での立原君は、間もなく病の床に臥さねばならない人とはとても見えなかった。長身でやせ型ではあったが、しようすいしているようには見えなかった。もの静かでやさしい好青年であった。…」
山根薫氏の奥様が文学に興味を持たれていて、その関係で堀辰雄から立原道造を紹介されていていたので事前に立原道造を知っていたようです。
志賀直哉は大正3年6月、31歳の時、城崎から松江を訪ねています。最初は末次本町の赤木館という旅館に入り、次に宍道湖畔東茶町七の十六に仮寓した後、四日後、内中原町六七に移っています。松江城の西側、濠に面した家で、亀田橋のすぐ南側になります。9月中旬には京都に移っていますので、約三ヶ月程の滞在になります。
志賀直哉の「壕端の住まい」からです。
「 一ト夏、山陰松江に暮した事がある。町はずれの濠に臨んだささやかな家で、独り住まいには申し分なかった。庭から石段で直ぐ濠になっている。対岸は城の裏の森で、大きな木が幹を傾け、水の上に低く枝を延ばしている。水は浅く、真菰が生え、寂びた工合、濠と云うより古い池の趣があった。鳰鳥が始終、真菰の間を啼きながら往き来した。
私は此処で出来るだけ簡素な暮しをした。人と人と人との交渉で疲れ切った都会の生活から来ると、大変心が安まった。虫と鳥と魚と水と草と空と、それから最後に人間との交渉ある暮しだった。…」
もう一人、芥川龍之介も松江を訪ねています。
芥川龍之介は第一高等学校の同級生、恒藤恭(つねとうきょう 旧姓井川)氏の勧めで、恒藤恭氏の故郷である松江を訪ねています。大正4年8月の約一ヶ月弱の滞在でしたが、その時の様子を「松江印象記」に書いています。
「 松江へ来て、まず自分の心をひいたものは、この市まちを縦横じゅうおうに貫いている川の水とその川の上に架かけられた多くの木造の橋とであった。河流の多い都市はひとり松江のみではない。しかし、そういう都市の水は、自分の知っている限りでたいていはそこに架けられた橋梁きょうりょうによって少からず、その美しさを殺そがれていた。……
… 橋梁に次いで、自分の心をとらえたものは千鳥城の天主閣であった。天主閣はその名の示すがごとく、天主教の渡来とともに、はるばる南蛮から輸入された西洋築城術の産物であるが、自分たちの祖先の驚くべき同化力は、ほとんど何人なんぴともこれに対してエキゾティックな興味を感じえないまでに、その屋根と壁とをことごとく日本化し去ったのである。寺院の堂塔が王朝時代の建築を代表するように、封建時代を表象すべき建築物を求めるとしたら天主閣を除いて自分たちは何を見いだすことができるだろう。…」
恒藤恭氏は第一高等学校から京都帝国大学に進学し、後に京大教授になります。瀧川事件で辞職しますが、戦後、京大教授に復職しています。有名な方です。
恒藤恭氏の「袖珍翡翠記」からです。
「 四十年振りの帰郷…
… 大正四年(一九一五年)の夏休みに、当時京大の二回生であった私は、一高時代の同級生であった芥川龍之介を松江に招いた。そのころ母や妹や弟たちは、うべや橋の近くの家から他の場所に移って住んでいたが、その家が手狭であったので、芥川を迎えるために、お花畑にささやかな空家をめっけて、しばらくそこを借りた。
八月三日に東京を出発した芥川は、五日の夕ぐれに松江に到着し二十一日まで滞在した。そのあいだ母がお花畑の家に来て、私たちと起居を共にし、炊事をしてくれた。それは亀田橋(?)のすこし手前にある、城のお濠に臨んだささやかな平屋造りの家で、せまい庭のすぐ東側には、お濠の水がひたひたとたたえていた。…」
立原道造の長崎ノートでは書かれていない芥川龍之介を何故ここで書いたかと言うと、志賀直哉が滞在していた”内中原町六七”の住居に芥川龍之介も滞在したからです。多分、偶然だとおもいますが、一年違いで滞在しています。
★写真の正面やや右側の建物のところが大正3年に志賀直哉が、大正4年に芥川龍之介が滞在した松江市内中原町六七番地の住居跡です。少し先の右側に亀田橋があります。亀田橋の袂、左側にに志賀直哉と芥川龍之介の記念碑が建てられています。亀田橋を渡ると松江城に入ることができます。
立原道造は松江市内を少し歩いていたようです。余り大きくない町ですが、お城と宍道湖に囲まれて、分かりやすい街並みです。又、立原道造は志賀直哉や小泉八雲の松江での住居などを巡っています(志賀直哉は松江での滞在記を書いていますので、ひょとしたら立原道造は事前に読んでいたのかもしれません)。
立原道造の「立原造造全集」、”第五巻 月報”からです。
「立原道造君との出会い
山根薫
… 勤務のあった私は、どこへも案内してあげなかった。ひとりで志賀直哉がかつて住んでいた家のあたりや、小泉八雲の旧居をたずねたりしたようであったが、たいていは家内や家内の友だちと文学の話などをしていた。元気になって東京へ帰ったら、雑誌をつくって一緒に勉強しょうということになったと家内がうれしそうに話していたことを思い出す。
松江での立原君は、間もなく病の床に臥さねばならない人とはとても見えなかった。長身でやせ型ではあったが、しようすいしているようには見えなかった。もの静かでやさしい好青年であった。…」
山根薫氏の奥様が文学に興味を持たれていて、その関係で堀辰雄から立原道造を紹介されていていたので事前に立原道造を知っていたようです。
志賀直哉は大正3年6月、31歳の時、城崎から松江を訪ねています。最初は末次本町の赤木館という旅館に入り、次に宍道湖畔東茶町七の十六に仮寓した後、四日後、内中原町六七に移っています。松江城の西側、濠に面した家で、亀田橋のすぐ南側になります。9月中旬には京都に移っていますので、約三ヶ月程の滞在になります。
志賀直哉の「壕端の住まい」からです。
「 一ト夏、山陰松江に暮した事がある。町はずれの濠に臨んだささやかな家で、独り住まいには申し分なかった。庭から石段で直ぐ濠になっている。対岸は城の裏の森で、大きな木が幹を傾け、水の上に低く枝を延ばしている。水は浅く、真菰が生え、寂びた工合、濠と云うより古い池の趣があった。鳰鳥が始終、真菰の間を啼きながら往き来した。
私は此処で出来るだけ簡素な暮しをした。人と人と人との交渉で疲れ切った都会の生活から来ると、大変心が安まった。虫と鳥と魚と水と草と空と、それから最後に人間との交渉ある暮しだった。…」
もう一人、芥川龍之介も松江を訪ねています。
芥川龍之介は第一高等学校の同級生、恒藤恭(つねとうきょう 旧姓井川)氏の勧めで、恒藤恭氏の故郷である松江を訪ねています。大正4年8月の約一ヶ月弱の滞在でしたが、その時の様子を「松江印象記」に書いています。
「 松江へ来て、まず自分の心をひいたものは、この市まちを縦横じゅうおうに貫いている川の水とその川の上に架かけられた多くの木造の橋とであった。河流の多い都市はひとり松江のみではない。しかし、そういう都市の水は、自分の知っている限りでたいていはそこに架けられた橋梁きょうりょうによって少からず、その美しさを殺そがれていた。……
… 橋梁に次いで、自分の心をとらえたものは千鳥城の天主閣であった。天主閣はその名の示すがごとく、天主教の渡来とともに、はるばる南蛮から輸入された西洋築城術の産物であるが、自分たちの祖先の驚くべき同化力は、ほとんど何人なんぴともこれに対してエキゾティックな興味を感じえないまでに、その屋根と壁とをことごとく日本化し去ったのである。寺院の堂塔が王朝時代の建築を代表するように、封建時代を表象すべき建築物を求めるとしたら天主閣を除いて自分たちは何を見いだすことができるだろう。…」
恒藤恭氏は第一高等学校から京都帝国大学に進学し、後に京大教授になります。瀧川事件で辞職しますが、戦後、京大教授に復職しています。有名な方です。
恒藤恭氏の「袖珍翡翠記」からです。
「 四十年振りの帰郷…
… 大正四年(一九一五年)の夏休みに、当時京大の二回生であった私は、一高時代の同級生であった芥川龍之介を松江に招いた。そのころ母や妹や弟たちは、うべや橋の近くの家から他の場所に移って住んでいたが、その家が手狭であったので、芥川を迎えるために、お花畑にささやかな空家をめっけて、しばらくそこを借りた。
八月三日に東京を出発した芥川は、五日の夕ぐれに松江に到着し二十一日まで滞在した。そのあいだ母がお花畑の家に来て、私たちと起居を共にし、炊事をしてくれた。それは亀田橋(?)のすこし手前にある、城のお濠に臨んだささやかな平屋造りの家で、せまい庭のすぐ東側には、お濠の水がひたひたとたたえていた。…」
立原道造の長崎ノートでは書かれていない芥川龍之介を何故ここで書いたかと言うと、志賀直哉が滞在していた”内中原町六七”の住居に芥川龍之介も滞在したからです。多分、偶然だとおもいますが、一年違いで滞在しています。
★写真の正面やや右側の建物のところが大正3年に志賀直哉が、大正4年に芥川龍之介が滞在した松江市内中原町六七番地の住居跡です。少し先の右側に亀田橋があります。亀田橋の袂、左側にに志賀直哉と芥川龍之介の記念碑が建てられています。亀田橋を渡ると松江城に入ることができます。
<小泉八雲の旧居>
立原道造が訪ねたであろう、小泉八雲の旧宅です。この付近が北堀町城見縄手になります。
立原道造の「長崎ノート」からです。
「 十一月二十九日
松江での一日。 ── 水の都。とりわけ北堀町城見縄手のあたりが美しい。いなり橋に立ってその町がはじめて眼にはいったとき、しばらくぼんやりした。古い屋並と水の色と松の木が日本の都合のタブロオを完成してゐる ── ドラマティックに。しづかだ、だが、そのしづかさは眠ってゐるしづかさだ。
城は北方的な感じがする。天守閣からの眺めはたのしい。…」
北堀町城見縄手は松江では有名な観光地となっています。団体客がどっと来ていました。又、”お堀めぐり”も人気がありました(昔はやっていなかった)。小泉八雲旧宅の右隣には出雲蕎麦で有名な”八雲庵”もあります。
★写真の正面が小泉八雲の旧宅です。この道沿いが城見縄手となります。上記に書かれている”いなり橋”と”いなり橋”から見た城見縄手付近、松江城、お城からの眺めを掲載しておきます。
立原道造が訪ねたであろう、小泉八雲の旧宅です。この付近が北堀町城見縄手になります。
立原道造の「長崎ノート」からです。
「 十一月二十九日
松江での一日。 ── 水の都。とりわけ北堀町城見縄手のあたりが美しい。いなり橋に立ってその町がはじめて眼にはいったとき、しばらくぼんやりした。古い屋並と水の色と松の木が日本の都合のタブロオを完成してゐる ── ドラマティックに。しづかだ、だが、そのしづかさは眠ってゐるしづかさだ。
城は北方的な感じがする。天守閣からの眺めはたのしい。…」
北堀町城見縄手は松江では有名な観光地となっています。団体客がどっと来ていました。又、”お堀めぐり”も人気がありました(昔はやっていなかった)。小泉八雲旧宅の右隣には出雲蕎麦で有名な”八雲庵”もあります。
★写真の正面が小泉八雲の旧宅です。この道沿いが城見縄手となります。上記に書かれている”いなり橋”と”いなり橋”から見た城見縄手付近、松江城、お城からの眺めを掲載しておきます。
<普門院>
2012年7月2日 普門院を追加
立原道造は北堀町城見縄手からお堀沿いに東に歩きます。北堀橋を南に渡って少し東に歩き、普門院橋を北に渡ると正面が普門院です。
立原道造の「長崎ノート」からです。
「 十一月二十九日…
…
一日中くもったり晴れたり雨が降ったりして定まりない天候だ。しかし大體は気持よく晴れてゐた。夕ぐれが來たときに僕は水路のほとりに立ってゐた。北堀のつづきだ。水はまだ空のうすらあかりを映してゐて、灯はもうキラキラとともってゐた。そのとき、奇妙な女の唄の聾をきいた。見ると水の向う側の家に髪を不思議な格好に束ねた女がゐる。この町の女の狂人だといふことだった。灯をともさないその窓で、影繪のやうな女がうたってゐる。それがこの夕ぐれに奇妙なニュアンスを興へてゐる。普門院といふこのお寺では、昔、殿様に女の人が殺されたといふはなしがある。そんなはなしのイメージがかさなる。…」
”殿様に女の人が殺された”と書いています。立原道造は小泉八雲の「小豆磨き橋の怪談」を読んでいたのではないかとおもいます。”小豆磨き橋”は普門院の近くだとのことなので、普門院橋のことではないかとおもいます。「小豆磨き橋の怪談」には”夜ごと女の幽霊が出た”と書いてありますので、イメージを膨らませて書いたのではないでしょうか!
★写真の正面が普門院です。手前の橋が普門院橋となります。北堀町城見縄手からお堀が続いています。
2012年7月2日 普門院を追加
立原道造は北堀町城見縄手からお堀沿いに東に歩きます。北堀橋を南に渡って少し東に歩き、普門院橋を北に渡ると正面が普門院です。
立原道造の「長崎ノート」からです。
「 十一月二十九日…
…
一日中くもったり晴れたり雨が降ったりして定まりない天候だ。しかし大體は気持よく晴れてゐた。夕ぐれが來たときに僕は水路のほとりに立ってゐた。北堀のつづきだ。水はまだ空のうすらあかりを映してゐて、灯はもうキラキラとともってゐた。そのとき、奇妙な女の唄の聾をきいた。見ると水の向う側の家に髪を不思議な格好に束ねた女がゐる。この町の女の狂人だといふことだった。灯をともさないその窓で、影繪のやうな女がうたってゐる。それがこの夕ぐれに奇妙なニュアンスを興へてゐる。普門院といふこのお寺では、昔、殿様に女の人が殺されたといふはなしがある。そんなはなしのイメージがかさなる。…」
”殿様に女の人が殺された”と書いています。立原道造は小泉八雲の「小豆磨き橋の怪談」を読んでいたのではないかとおもいます。”小豆磨き橋”は普門院の近くだとのことなので、普門院橋のことではないかとおもいます。「小豆磨き橋の怪談」には”夜ごと女の幽霊が出た”と書いてありますので、イメージを膨らませて書いたのではないでしょうか!
★写真の正面が普門院です。手前の橋が普門院橋となります。北堀町城見縄手からお堀が続いています。
<松江大橋の袂のモリナガ>
2012年7月2日 写真を入替え
最後は松江大橋の袂にある”森永”です。立原道造は松江で東京銀座の雰囲気が味わえる”森永”を訪ねています。やはり、森永といえば、銀座の”森永キャンデーストア”をイメージしますね。
立原道造の「長崎ノート」からです。
「 十一月三十日
風が吹きあれて、空はくらい雲に蔽はれ、それが吹き拂はれる。多のこのあたりの気候は陽の光に恵まれずにこんな風にしてずつとつづくのださうだ。明るさと暗さとが今はまだ激しくたたかつてゐる。けふは日本海につき出してゐる岬の方へ行ってみようとおもってゐる。海があれてゐるかも知れないが、舟にのる。 ── 僕の旅の豫定はまたのびはじめた。長崎に着くのはすこしおくれるだらう。しかも早く落着きたいとねがってゐる。ふたつのねがひがいつも胸のなかであらがってゐる。しかも、傷はやぶれたまま、不安なたよりない身體を旅に驅ってゐる。このごろは咳がやまない、咽喉がどうかなってゐるのだらうか。……この部屋からお城が見える、身もだへして木のあちらで、うづたかくつもつた灰色の雲を背にして、陽をうけてゐるが、しかも黒く暗い。しかし美しい城だ。風はなかなかやみさうにもない、硝子戸の中は陽がさしてあたたかい。けふはひとりだ。
*
松江大橋の袂のモリナガの二階で、波立つ宍道湖をながめてゐる。 ── 町の人たちは黒い長いマントオを着て橋を歩いて行く。自轉車が行く。朝なので明るい。カイツブリらしい鳥が渡の間を行ったり來たりしてゐる。熱い加排をのみながら、船の時間を待ってゐる。
…」
松江大橋の袂にある”森永”の場所についてはなかなか分からなかったのですが、昭和28年発行の「岩波写真文庫 松江」と昭和29年の松江市全図の地図にも掲載されていました。”森永”の文字が分かるまで拡大した写真も掲載しておきます。
その他では、十一月三十日の生田勉宛絵葉書に町の様子が書かれていました。
「579 十一月三十日 〔水〕生田勉宛(東京市杉並區高圓寺四の六〇一橘川方)<繪端書>
君は、まへに山陰の方へ來たことがあるだらうか。ここは北らしい波の來る海岸をとはつて來て、しづかな町だ。水路と松とが美しい。松江大橋に立って 宍道湖を見てゐたときに虹がかかった。虹の下に黒い城が光ってゐた。そして湖畔の造酒屋の白壁や大きな木の樽が、とりわけ眼についた、それはひとつの美しい繪だった、僕の眼は美しい繪を身のまはりにつくりながら そのなかを旅してゐる。しかし 旅は切なく悲しい。道造。」
”湖畔の造酒屋”は宍道湖大橋の北詰にある「國暉酒造」ではないかとおもいます。
★写真は松江大橋北詰から北側を撮影したものです。”森永”は写真やや右の茶色のビルのところにありました。現在は”森永”は無くなっており、当時とはすっかり変わってしまっています。松江大橋からの写真も掲載しておきます。松江もご多分に漏れずシャッター通り化、一歩手前という感じでした。
2012年7月2日 写真を入替え
最後は松江大橋の袂にある”森永”です。立原道造は松江で東京銀座の雰囲気が味わえる”森永”を訪ねています。やはり、森永といえば、銀座の”森永キャンデーストア”をイメージしますね。
立原道造の「長崎ノート」からです。
「 十一月三十日
風が吹きあれて、空はくらい雲に蔽はれ、それが吹き拂はれる。多のこのあたりの気候は陽の光に恵まれずにこんな風にしてずつとつづくのださうだ。明るさと暗さとが今はまだ激しくたたかつてゐる。けふは日本海につき出してゐる岬の方へ行ってみようとおもってゐる。海があれてゐるかも知れないが、舟にのる。 ── 僕の旅の豫定はまたのびはじめた。長崎に着くのはすこしおくれるだらう。しかも早く落着きたいとねがってゐる。ふたつのねがひがいつも胸のなかであらがってゐる。しかも、傷はやぶれたまま、不安なたよりない身體を旅に驅ってゐる。このごろは咳がやまない、咽喉がどうかなってゐるのだらうか。……この部屋からお城が見える、身もだへして木のあちらで、うづたかくつもつた灰色の雲を背にして、陽をうけてゐるが、しかも黒く暗い。しかし美しい城だ。風はなかなかやみさうにもない、硝子戸の中は陽がさしてあたたかい。けふはひとりだ。
*
松江大橋の袂のモリナガの二階で、波立つ宍道湖をながめてゐる。 ── 町の人たちは黒い長いマントオを着て橋を歩いて行く。自轉車が行く。朝なので明るい。カイツブリらしい鳥が渡の間を行ったり來たりしてゐる。熱い加排をのみながら、船の時間を待ってゐる。
…」
松江大橋の袂にある”森永”の場所についてはなかなか分からなかったのですが、昭和28年発行の「岩波写真文庫 松江」と昭和29年の松江市全図の地図にも掲載されていました。”森永”の文字が分かるまで拡大した写真も掲載しておきます。
その他では、十一月三十日の生田勉宛絵葉書に町の様子が書かれていました。
「579 十一月三十日 〔水〕生田勉宛(東京市杉並區高圓寺四の六〇一橘川方)<繪端書>
君は、まへに山陰の方へ來たことがあるだらうか。ここは北らしい波の來る海岸をとはつて來て、しづかな町だ。水路と松とが美しい。松江大橋に立って 宍道湖を見てゐたときに虹がかかった。虹の下に黒い城が光ってゐた。そして湖畔の造酒屋の白壁や大きな木の樽が、とりわけ眼についた、それはひとつの美しい繪だった、僕の眼は美しい繪を身のまはりにつくりながら そのなかを旅してゐる。しかし 旅は切なく悲しい。道造。」
”湖畔の造酒屋”は宍道湖大橋の北詰にある「國暉酒造」ではないかとおもいます。
★写真は松江大橋北詰から北側を撮影したものです。”森永”は写真やや右の茶色のビルのところにありました。現在は”森永”は無くなっており、当時とはすっかり変わってしまっています。松江大橋からの写真も掲載しておきます。松江もご多分に漏れずシャッター通り化、一歩手前という感じでした。
松江編Ⅱは少し時間がかかります。
立原道造の長崎ノート地図
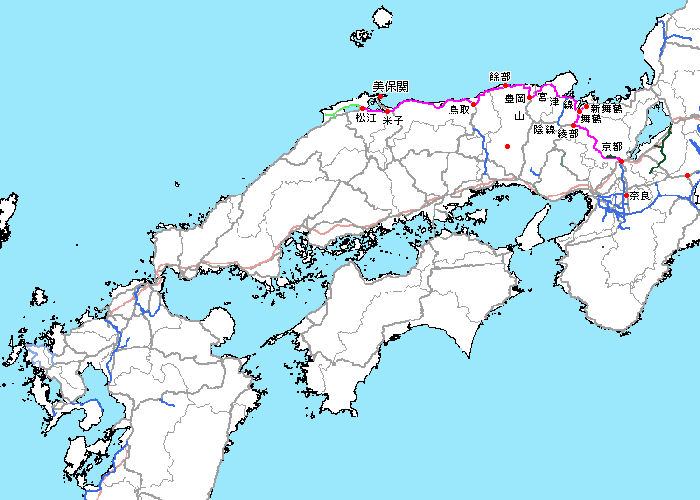
立原道造年表
| 和 暦 | 西暦 | 年 表 | 年齢 | 立原道造の足跡 |
| 大正3年 | 1914 | 第一次世界大戦始まる | 0 | 7月30日 東京都日本橋区橘町橘町三丁目一番地に父貞次郎、母とめの次男として生まれる |
| 大正7年 | 1918 | シベリア出兵 | 5 | 4月 養徳幼稚園に入園 |
| 大正8年 | 1919 | 松井須磨子自殺 | 6 | 8月 父貞次郎死去、家督を継ぐ |
| 大正10年 | 1921 | 日英米仏4国条約調印 | 8 | 4月 久松小学校に入学(開校以来の俊童と言われる) |
| 大正12年 | 1923 | 関東大震災 | 10 | 9月 関東大震災、流山に避難する 12月 東京に戻る |
| 昭和2年 | 1927 | 金融恐慌 芥川龍之介自殺 地下鉄開通 |
14 | 4月 府立第三中学校に入学 |
| 昭和4年 | 1929 | 世界大恐慌 | 16 | 3月 神経衰弱療養の為、豊島家に宿泊 |
| 昭和6年 | 1931 | 満州事変 | 18 | 4月 府立第三中学校を4年で修了し第一高等学校入学 |
| 昭和9年 | 1934 | 丹那トンネル開通 | 21 | 3月 第一高等学校卒業 4月 東京帝国大学工学部建築学科入学 |
| 昭和12年 | 1937 | 蘆溝橋で日中両軍衝突 | 24 | 3月 東京帝国大学卒業 4月 石本建築事務所に入社 |
| 昭和13年 | 1938 | 関門海底トンネルが貫通 岡田嘉子ソ連に亡命 「モダン・タイムス」封切 |
25 | 9月15日 盛岡に向かう(盛岡ノートを書き始める) 9月15、16日 山形 竹村邸泊 9月17日 上ノ山温泉泊 9月19日 盛岡着 10月20日 帰京 11月24日 夜行で長崎に向かう 11月25日 奈良を回り京都着(長崎ノートを書き始める) 11月27日 京都から舞鶴に向かう 11月28日 舞鶴から松江に向かう 11月28日から12月1日まで松江に滞在 |





