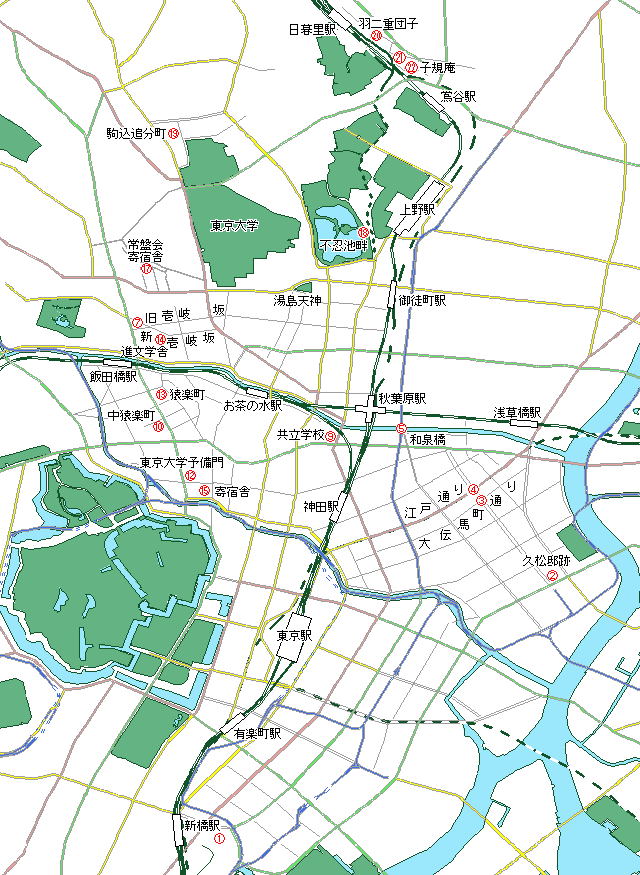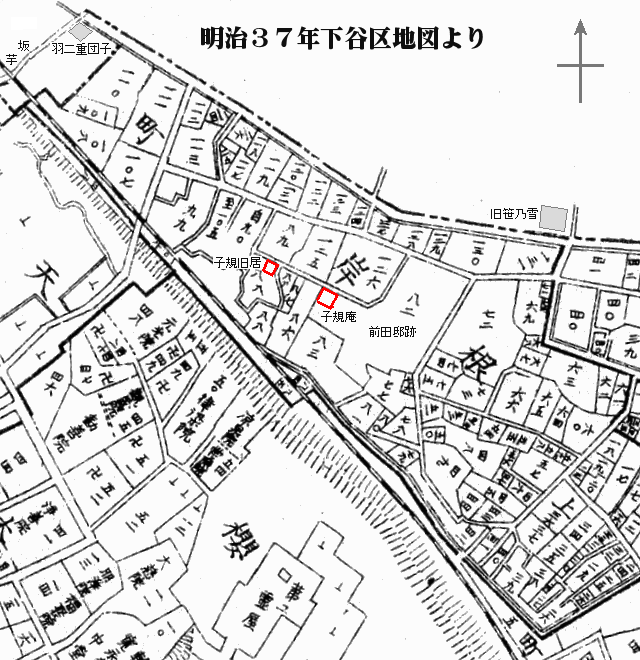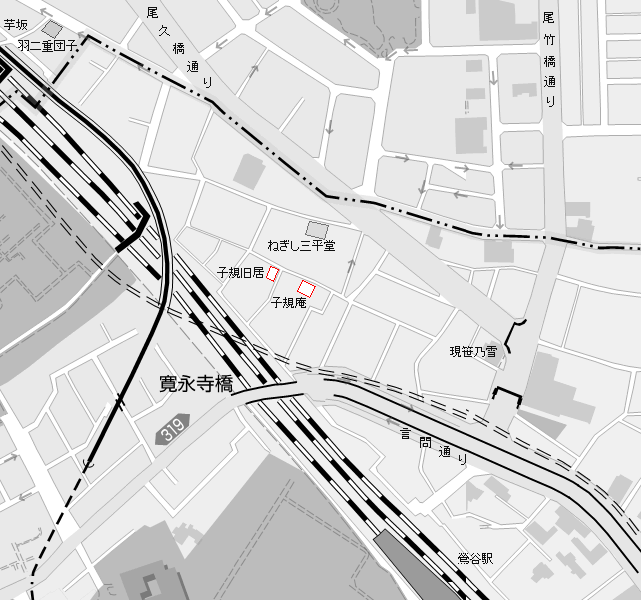< 羽二重団子>
羽二重団子>
羽二重団子は根岸ではあまりに有名ですね。この羽二重団子は創業文政2年(1819年)のだんご屋さんで、夏目漱石や正岡子規、司馬遼太郎といった文豪たちの作品の中にたびたび登場します。初代の庄五郎が芋坂の「藤の木茶屋」で、王子街道を従来した人々に団子を売ったのが始まりだそうで、この団子が「きめ細かく羽二重のようだ」と評判を呼んでこの名前がついたそうです。この羽二重団子の横に丁度芋坂があり、慶応4年5月15日、上野の戦争で敗れた彰義隊数百人が日光へ逃げるため、この芋坂を駆け下りてきています。その際に数名が羽二重団子の店に侵入、刀、槍を縁の下に投げ込み、野良着に変装したそうです。正岡子規の日記である「仰臥漫録」を読むと
「…九月四日 朝曇 後晴
昨夜はよく眠る 新聞『日本』『二六』『京華』『大阪毎日』を読む例の如し 『海南新聞』は前日の分翌日の夕刻に届くを例とす
朝 雑炊三椀 佃煮 梅干
牛乳一合ココア入 菓子パン二個 昼 鰹のさしみ 粥三椀 みそ汁 佃煮 梨二つ
葡萄酒一杯(これは食時の例なり 前日日記にぬかす)
間食 芋坂団子を買来らしむ(これに付悶着あり)
あん付三本焼一本を食ふ 麦湯一杯
塩煎餅三枚 茶一碗
晩 粥三椀 なまり節 キャベツのひたし物
梨一つ
午前種竹山人来る 菖蒲田原釜なこそなどの海水浴に済んで帰ると 原釜にては松魚一尾八銭高きとき十三銭
家庭の快楽といふこといくらいふても分らず
物 思 ふ 窓 に ぶ ら り と 糸 瓜 哉
肋骨の贈り来りし美人画は羅に肉の透きたる処にて裸体画の如し
裸 体 画 の 鏡 に 映 る 朝 の 秋
美 女 立 て り 秋 海 業 の 如 き か な。…」 、と書かれています。死去する一年前の明治34年9月4日の日記です。ココア入りの牛乳等も飲んでいますから当時としてはかなり贅沢な食事ですね。芋坂団子(羽二重団子)も”あん付三本焼一本”を食べています。今だと食べ切れない量です。
芋坂団子(羽二重団子)の句もいくつか残しています。
芋坂も団子も月のゆかりかな
芋坂の団子の起り尋ねけり
★左上の写真が羽二重団子です。羽二重団子は、平べったい4粒のだんごで、こしあんと生醤油の2種類。得に、甘さ控えめのこしあんは、キメが細かいのに粉っぽくなくて絶品、二つ食べると丁度よい感じになります。琴の音が流れる店内で、中庭を眺めながら食べることもでき、団子2本とお茶のセットは462円です。右にお店の写真も掲載しておきます。
【正岡子規(本名:常規。幼名は処之助でのちに升と改めた)】 慶応3年(1867)9月17日、愛媛県松山市で父正岡常尚、母八重の長男として生まれる。旧制愛媛一中(現松山東高)を経て上京し、東大予備門から東京帝国大学哲学科に進学する。秋山真之とは愛媛一中、共立学校での同級生。共立学校における子規と秋山の交遊を司馬遼太郎が描いたのが小説『坂の上の雲』。東大では夏目漱石と同級生。大学中退後、明治25年(1892)に新聞「日本」に入社。俳句雑誌『ホトトギス』を創刊して俳句の世界に大きく貢献した。従軍記者として日清戦争にも従軍したが、肺結核が悪化し明治35年9月19日死去。享年34歳。
子規の東京地図
正岡子規の東京年表
|
和 暦 |
西暦 |
年 表 |
年齢 |
正岡子規の足跡 |
| 明治16年 |
1883 |
モーパッサン「女の一生」
岩倉具視没
|
16 |
6月 日本橋区浜町の旧松山藩主久松邸内に寄寓
7月頃 赤坂丹後町の須田学舎に入学
9月 久松邸内に戻る
10月 共立学校(学舎)に入学
10月末 神田区仲猿楽町19番地の藤野宅に下宿
|
| 明治17年 |
1884 |
森鴎外ドイツ留学
秩父事件
|
17 |
夏 東五軒町三十五番地 藤野宅に下宿
夏 進文学舎に通う
9月 東京大学予備門入学
秋 猿楽町五番地の板垣善五郎宅に下宿
|
| 明治18年 |
1885 |
清仏天津条約
|
18 |
夏 松山に帰省
|
| 明治19年 |
1886 |
谷崎潤一郎誕生
|
19 |
4月 清水則遠の葬儀
4月 予備門が第一高等中学校と改称
ベースボールに熱中
夏 永坂の別邸に一時奇遇 |
| 明治20年 |
1887 |
長崎造船所が三菱に払下
|
20 |
9月 第一高等中学校予科進級
一橋外の高等中学校に寄宿
12月 常盤会寄宿舎に転居
|
| 明治22年 |
1889 |
大日本帝国憲法発布
パリ万国博覧会 |
22 |
1月 夏目金之助と交遊が始まる
第一高等中学校本郷に移転
10月 不忍池畔に下宿
|
| 明治23年 |
1890 |
慶應義塾大学部設置
帝国ホテル開業 |
23 |
1月 常盤会寄宿舎に戻る
9月 東京帝国大学文科大学哲学科入学 |
| 明治24年 |
1891 |
大津事件
東北本線全通 |
24 |
12月 本郷区駒込追分町30番地奥井方に下宿 |
| 明治25年 |
1892 |
東京日日新聞(現毎日新聞)創刊 |
25 |
2月 下谷区上根岸88番地に転居
10月 東京帝国大学を退学
11月 母八重、姉律を東京に呼ぶ
12月 日本新聞社入社
|
| 明治27年 |
1894 |
東学党の乱
日清戦争 |
27 |
2月 上根岸82番地に転居 |
| 明治28年 |
1895 |
日清講和条約
三国干渉 |
28 |
4月 日清戦争へ従軍
5月 県立神戸病院に入院
8月
松山の夏目漱石の下宿に移る |
| 明治29年 |
1896 |
アテネで第1回オリンピック開催
樋口一葉死去 |
29 |
1月 子規庵で鴎外、漱石参加の句会開催 |
| 明治33年 |
1900 |
義和団事件 |
33 |
9月 漱石ロンドンへ出発 |
| 明治35年 |
1902 |
八甲田山死の行軍 |
35 |
9月19日 死去 |
< 下谷区上根岸88番地>
下谷区上根岸88番地>
子規は駒込追分町の下宿をわずか三カ月で出て、上根岸の羯南宅西隣に転居します。この頃はまだまだ元気だったようです。
「…居士は追分町の下宿を引払って、下谷区上根岸八十八番地に轉寓した。それは二月二十九日でありし事が、塾や宛の書簡に明記されてゐる。その追分町に居た期間は約三ケ月に過ぎず、起草の小説「月の都」が脱稿して十日も経たぬうちに轉寓したのであった。上根岸八十二番地の現在の子規庵の西隣が、当時の日本新聞社長、陸掲南の邸である。其虞には南へ入り込む小路があって、陸邸は角家になってゐる。両て陸邸の門前小路をへだてゝ西角が居士の轉寓した八十八番地の家である。…… 寒川鼠骨氏は「同人」の昭和九年九月親に「子規庵の今昔」と題して大分委しく記してゐる。『此の八十八番地は八畳と四畳半と二畳と六畳に臺所附の家であったが居士が借りたのは八畳と四畳半の二室であった、初は金井姓の家主の老婦人と居た、老婦人の頑迷な小むつかしさには居士も困り按いて悲鳴を揚げて居る……』…。」。
ここで、母八重、姉律を東京に呼びます。駒込追分町も居心地が良くなかったわけですが、この上根岸88番地も居心地は良くなかったようです。それでもこの下宿には二年ほどいました。
子規がこの下宿について句を残しています。
小生表記の番地へ転寓、、処は名高き鶯横町
鶯のとなりに細きいほり哉
実の処汽車の往復喧しく(レールより一町ばかり)ために脳痛をまし候
鶯の遠のいてなく汽車の音
あまつさへ家婦の待遇余りよからず罪なくして配所の月の感あり 駒込追分町の静かな家から少々うるさい根岸に移った事を良くあらわしていますね。
★左上の写真の道の突当り正面のクリ−ム色の家のところが
上根岸88番地です。写真の左側が子規庵ですから右隣が羯南宅になります。
< 子規庵>
子規庵>
明治25年2月に下谷区上根岸82番地(羯南宅の西隣から東隣に移ります)に移ります。
鼠骨氏の「子規庵の今昔」では、
「…八十二番地への移轉は二十七年の一月に子規居士を編集長として新聞「少日本」を創刊する議が決し、俸給も二十円に増額された偽めに少々高い家賃を奮発し、羯南先生の東隣に借家が出来たのを幸として断行されたのであった。…」、と書かれています。その当時の状況を、「…自分は二十九年の碁と三十一年の初夏、前後二回子規庵を訪うたばかりで、同庵の昔に就ては飴り知らない。二十九年の場合は鳴雪翁の案内で行ったが、上野公園をぬけて上根岸に到り、大名屋敷の通用門のやうなものを入ってしばらく住宅の間といふやうなところを進むと竹垣があり其竹垣の三尺戸を押して入ると小庭があり種々の草木が植ゑ込まれてゐる其中をすぢかひに十数歩進むと古ぼけた縁端があって、障子を開ければすぐ居士の病室に隣りし八畳の座敷であった。我我は裏口から子規庵を訪うたのである。表口に廻るには多少道が遠いので裏口から出入する者が少くないと云ふやうなことを其時鳴雪翁は語ってゐられた。又三十一年の場合は自分単独で表口から訪問した。何虞から何う行ったかは記憶に無いが、道幅の至って狭い鶯横町に入って子規庵をたづねあてた。当時口さがない人々の間では犬糞横町と称せられてゐた程鶯横町の雅美な名稀には縁の遠い薄汚ない小路であった。…」、とあります。
ここが子規、終生の住居となります(
裏の庭からの写真も掲載しておきます)。この頃の家賃は週刊朝日編「値段の明治・大正・昭和風俗史」によると板橋付近で明治32年の家賃が75銭(六畳、四畳半、三畳、台所、洗面所付)、明治三十一年の銀行員の初任給が三十五円だそうです(子規は明治31年には日本新聞社から40円貰っていた)。
★右上の写真が現在の子規庵です。
「…表門の開き戸をくゞり入ると敷歩のうちに玄関先きの沓脱ぎが見えてゐる。普通沓脱の外にあるべき格子戸は無かった。障子を明けると二畳の玄関があって、其右側が三畳の茶の間と水場であり、左側が四畳半の部屋、又玄関の奥が八畳の座敷で座敷の左に並びて六畳の部屋、これが居士の平生病臥するところである。前記の四畳半と竪につゞいてゐる八畳の座敷には三尺の板縁があって南受けであるから病室も亦南をうけてゐる。所謂子規庵の小園なるものは其の南庭をいったもので二十九年の訪問の場合、鳴雪翁につれられて裏口から入ったのは其の小園に踏み入ったわけである。…」。
これで子規庵の中の様子がわかります。この子規庵の付近は前田侯の地所で、明治の初年本郷の加賀屋敷の大部分が大学の用地に収用された際に御家人の家を移した所だそうです。子規庵は前田侯の別荘内の貸家の一つでした。
< 大龍寺>
2007年5月7日大龍寺の写真を追加
大龍寺>
2007年5月7日大龍寺の写真を追加 明治27年2月に上根岸82番地の子規庵に移ってからは、ここが終生の地となります。明治28年、日清戦争に従軍、帰国途中の船内で喀血、神戸病院に入院します(神戸の子規については別途特集します)。この後、子規は松山に戻り、夏目漱石の下宿に転がり込むわけです(この辺りの話は有名ですね!)。このころから体調が徐々に悪化していきます。明治35年9月14日頃から殆ど書けなくなってきており、18日には昏睡状態になりつつあったようです。19日午前一時に永眠(35歳)しますが、高浜虚子が「回想 子規・漱石」の中でその時のことを語っています。
「…その十八日の夜は皆帰ってしまって、余一人座敷に床を展べて寝ることになった。どうも寝る気がしないので庭に降りて見た。それは十二時頃であったろう。糸瓜の棚の上あたりに明るい月が掛っていた。余は黙ってその月を仰いだまま不思議な心持に鎖されて暫く突立っていた。やがてまた座敷に戻って病床の居士を覗いて見るとよく眠っていた。「さあ清さんお休み下さい。また代ってもらいますから。」と母堂が言われた。母堂は少し前まで臥せっていられたのであった。そこで今まで起きていた妹君も次の間に休まれることになったので、余も座敷の床の中に這入った。眠ったか眠らぬかと思ううちに、「清さん清さん。」という声が聞こえた。その声は狼狽した声であった。余が擬起して病床に行く時に妹君も次の間から出て来られた。その時母堂が何と言われたかは記憶していない。けれどもこういう意味の事を言われた。居士の枕頭に鷹見氏の夫人と二人で話しながら夜伽をして居られたのだが、あまり静かなので、ふと気がついて覗いて見ると、もう呼吸はなかったというのであった。妹君は泣きながら「兄さん兄さん」と呼ばれたが返事がなかった。洗足のままで隣家に行かれた。それは電話を借りて医師に急を報じたのであった。…」。
虚子が一番身近で臨終に立ち会っていたようです。
また柴田宵曲の「評伝 正岡子規」では、
『…何か写生するつもりで画板に紙の貼ってあったのを、無言で傍に持ち来らしめ、
糸瓜咲て痰のつまりし仏かな
をととひの糸瓜の水も取らざりき
痰一斗糸瓜の水も間にあはず の三句をしたためたのは、十八日の午前である。これが居士の絶筆であった。この日はあまりものもいわず、昏睡状態が続いていたが、その夜母堂も令妹も、一人残って泊っていた虚子氏も、誰も気づかぬうちに、居士の英魂は己に天外に去っていた。あまり蚊帳の中の静なのを怪しんで居士の名を呼んだ時は、手は己に冷え渡って、優に額上に微温を存するのみであった。時に九月十九日午前一時、虚子氏が急を報ずるために外へ出たら、十七夜の月が明るく照っていたそうである。…』、とあります。
子規の遺骸は20日滝野川村宇田端大龍寺に葬られ、会葬者は150名余りでした。戒名は「子規居士」で、3年後の明治38年に羯南翁の筆に成る墓石が建てられました。大龍寺は湯島霊雲寺の末寺で、現在の本堂の扁額は「岡本太郎」筆です。
★左上の写真が田端大龍寺内の正岡子規のお墓で、右の写真が大龍寺正面です。左上写真の中央に「子規居士之墓」があり、右側は母「正岡八重墓」、左側は「正岡氏累世之墓」です。一番左側の石柱には、病没4年前、明治31年7月13日に友人河東銓に宛てた書簡の中に有る墓碑銘が刻まれています。はじめは昭和9年の33回忌に作られた自筆の銅板の墓碑銘だったのですが、昭和11年2月に盗難にあい、同年9月に石に刻みなおしています。
「正岡子規又ノ名ハ虎之助又ノ名ハ升又ノ名ハ子規又ノ名ハ獺祭書屋主人又ノ名ハ竹ノ里人伊豫松山ニ生レ東京根岸ニ住ム父隼太松山藩御馬廻加番タリ卒ス母大原氏ニ養ハル日本新聞社員タリ明治三十□年□月□日没ス享年三十□月給四十圓」なかなか面白いですね。
次回は「正岡子規の神戸」を歩きます。
子規東京地図-5-(明治37年の上根岸)
子規東京地図-6-(現在の上根岸)