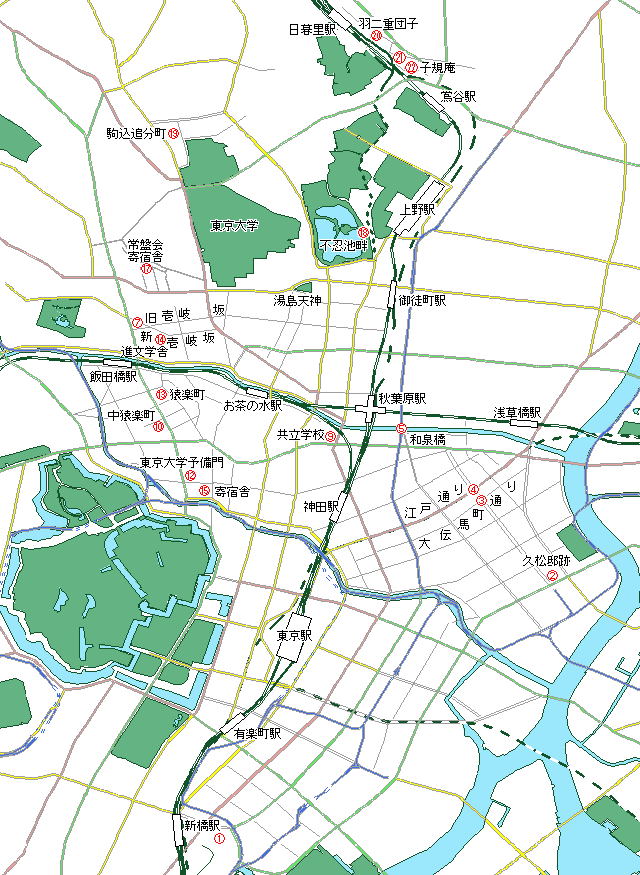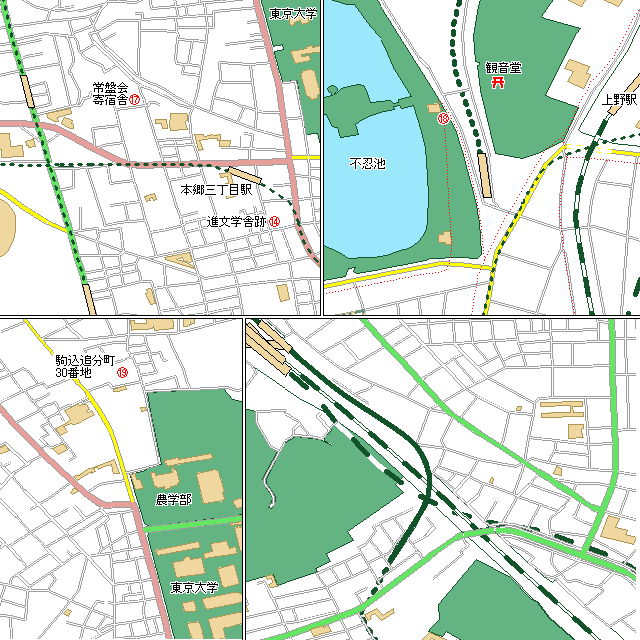< 常盤会寄宿舎>
常盤会寄宿舎>
明治20年、子規は松山出身者向けの寄宿舎、常盤会に下宿します。本郷の東京帝大には近かくなったのですが、第一高等中学校はまだ一ツ橋にあり、通学には遠かったとおもいます。
「…嘗ても語りし如く常盤会寄宿舎は、敷地一杯に建物があって、極めて僅かな余地を南庭に有し其虞に鉄棒とブランコ位が設備されてゐたに過ぎず、大がかりな遊戯運動は到底舎内に行ふわけに行かざりしが、伴に門前道路をへだてし向ひ側に可なり広い空地があって、之が開放されてゐた。飄亭氏は之を吉原の駆黴院跡と称してをり、碧梧桐氏は梅毒病院跡と語ってゐるが、自分は軍に駆黴院跡と当時聞いてゐたやうに思ふ。吉原からは相当かけはなれた遠くであり、根津から云っても近からざる此の地に、遊郭の駆黴院が何故あったものか知るを得ないが、当時は己に取り払はれて宅地となってゐたもので、舎生の遊戯連動は主として此処を利用してゐた。 其の宅地の面積がどれ位なものであったか自分は記憶してゐないが、廣いと云ったところでたかだか三百坪かその以上少々位のものであったらう。…」。
常盤会寄宿舎跡はもともと明治17年から坪内逍遥が住んでいた所で、明治20年に同じ町内に移転後、旧松山藩主の久松家が同じ場所に松山藩の子弟の為に常盤会寄宿舎を建てています。
★左上の写真の左側の建物の所(現日立本郷ビル)が常盤会寄宿舎跡です。右側の坂は炭団坂で、本郷区真砂町(文京区本郷4丁目)から菊坂に向かって下る坂道。命名の由来は、かつて炭田を商うものが多く住んでいたため、往来の人が炭団のように転がり落ちるためという二説があるようです(東京文学地名辞典による)。柳原極堂によると、
「…小石川の春日町停留所から市電の軌道に治び宮坂を本郷三丁目に向つて登ると、未だ登り切らぬ少し手前に眞砂町停留所がある。其処の十字路を左側即ち北方へ折れて少し歩めば路はすぐ遼きて其処から狭小な急坂が北へ下ってゐる。それは炭団坂である。而で其の坂の下り口西側崖上に今から三十一年前改築されし前記の常盤合寄宿舎が甚だ古ぼけて見苦しく残存してゐる。…」、下記に真砂町の地図を掲載しておきますので参考にしてください。
【正岡子規(本名:常規。幼名は処之助でのちに升と改めた)】 慶応3年(1867)9月17日、愛媛県松山市で父正岡常尚、母八重の長男として生まれる。旧制愛媛一中(現松山東高)を経て上京し、東大予備門から東京帝国大学哲学科に進学する。秋山真之とは愛媛一中、共立学校での同級生。共立学校における子規と秋山の交遊を司馬遼太郎が描いたのが小説『坂の上の雲』。東大では夏目漱石と同級生。大学中退後、明治25年(1892)に新聞「日本」に入社。俳句雑誌『ホトトギス』を創刊して俳句の世界に大きく貢献した。従軍記者として日清戦争にも従軍したが、肺結核が悪化し明治35年9月19日死去。享年34歳。
子規の東京地図
正岡子規の東京年表
|
和 暦 |
西暦 |
年 表 |
年齢 |
正岡子規の足跡 |
| 明治16年 |
1883 |
モーパッサン「女の一生」
岩倉具視没
|
16 |
6月 日本橋区浜町の旧松山藩主久松邸内に寄寓
7月頃 赤坂丹後町の須田学舎に入学
9月 久松邸内に戻る
10月 共立学校(学舎)に入学
10月末 神田区仲猿楽町19番地の藤野宅に下宿
|
| 明治17年 |
1884 |
森鴎外ドイツ留学
秩父事件
|
17 |
夏 東五軒町三十五番地 藤野宅に下宿
夏 進文学舎に通う
9月 東京大学予備門入学
秋 猿楽町五番地の板垣善五郎宅に下宿
|
| 明治18年 |
1885 |
清仏天津条約
|
18 |
夏 松山に帰省
|
| 明治19年 |
1886 |
谷崎潤一郎誕生
|
19 |
4月 清水則遠の葬儀
4月 予備門が第一高等中学校と改称
ベースボールに熱中
夏 永坂の別邸に一時奇遇 |
| 明治20年 |
1887 |
長崎造船所が三菱に払下
|
20 |
9月 第一高等中学校予科進級
一橋外の高等中学校に寄宿
12月 常盤会寄宿舎に転居
|
| 明治22年 |
1889 |
大日本帝国憲法発布
パリ万国博覧会 |
22 |
1月 夏目金之助と交遊が始まる
第一高等中学校本郷に移転
10月 不忍池畔に下宿
|
| 明治23年 |
1890 |
慶應義塾大学部設置
帝国ホテル開業 |
23 |
1月 常盤会寄宿舎に戻る
9月 東京帝国大学文科大学哲学科入学 |
| 明治24年 |
1891 |
大津事件
東北本線全通 |
24 |
12月 本郷区駒込追分町30番地奥井方に下宿 |
< 不忍池畔>
不忍池畔>
子規は一時期、常盤会寄宿舎から出て不忍池湖畔に下宿します。
「…明治二十二年十月初旬、居士が轉寓せし上野不忍池畔の下宿は何虞であったか。大谷是空氏に宛てし十一月八日附の居士の端書には唯弁天廟畔とのみありて町名番地等は略されて居り、其他に據るべき當時の書信類は未だ現ほれてゐない。『正岡の居た不忍池畔の下宿は無極庵の隣で二階建で なしに平屋の離家みたいなところぢやなかつたかと恩ふ、我々は憶かに裏から出入したやうなおぼえがあ る』と五百木飄亭氏は言ってゐる。『不忍池畔に西洋料理の青陽楼といふのがあって、子規の下宿はその一二軒北隣であった、部屋から小さい路をへだてゝ池を見晴らしてゐた』と、大谷是空氏は語ってゐる。菊池謙二郎氏は又『不忍池連の子規の寓居は下宿屋ではなく、中年の婦人の家であったやうに思ふ』と言ってゐる。た…」。
この不忍池湖畔の下宿についてはなかなか場所が分からなかったのですが柳原極堂の『子規の「下宿がへ」に就て』(子規全集10巻に掲載)に詳細に書かれていました。
★左上の写真の正面あたりに子規の下宿がありました。写真の左側が観音堂の階段になります。
「…観音堂の石段下、公園ぞひの、道路を三四十間南へ歩みたるところ、右側即ち、池の側に無極亭といふ二階建の貸席屋がある。其の南隣は板囲の宅地で、其の次から数軒の料亭が南へつゞいてゐる。其処の町名はと聞くと、黒門町と称し、又、元黒門下とも云ふ。公園の入口あたりの位置に、昔黒門があった関係から此の稱のあるわけである。居士の文中にも、飄亭氏の談話にも、居士の下宿の南隣に無極庵といふがあつたと言はれてゐるが、前記の無極亭はその無極庵の後である。営業上の都合で庵を亭に改めたのだといふ。居士の記するところによれば、無極庵の北隣が居士の下宿せし家で、それより北へ清凌亭、待合、員鍋とつゞき水月亭といふ汁粉屋が其の北の端であったといふが無極亭より北のそれら五軒は今はすべて無くて其址と思はるゝあたり、多少の樹を植込みたる芝生になってゐる。市電の軌道を敷設の際買収して取りこぼったものだと云ふ。
無極亭も其際十間ばかり南へ家を移したもので、当時使用せし古井が今の家の北十間ばかりのところに残されてゐる。其の古井の北が即ち居士の寄寓せし家のあったところである。…」。
この辺りも空襲で焼けていますので無極庵も残っていませんでしたが、上記に書かれている井戸はまだありました。
不忍池から見た写真も掲載しておきます(写真の右側に井戸があります)。
< 駒込追分町30番地>
駒込追分町30番地>
明治24年12月、子規は常盤会寄宿舎を出て本郷区駒込追分町の奥井家に下宿します。
「…二十四年十二月中旬、居士は常盤合寄宿舎を出て駒込追分町三十番地なる奥井屋敷の離屋に下宿したのである。當時を知ってゐる菊池謙二郎氏が嘗て自分に語り聞かせしところに依れば、其の奥井といふは一高(今の農学部)の寄宿舎から路を隔てて稍稍北方にあり、昔は小大名の邸宅でもあったかと思はるるほど廣壮な屋敷であって、立派な庭園があり、本屋の外に三棟ほどの離屋があった。子規は其の一棟に住んでゐた。…」。
当時の駒込追分町30番地はかなり広く、子規が下宿した離屋の詳細の場所をつかむのは殆ど不可能でした。昔は大きな家が多かったようです。
★右上の写真の左側付近が駒込追分町30番地です(現在の向丘二丁目9〜10付近です)。
「…其帝大農学部前の北を学校の境に沿うて東へ入る町がある。二三十間ばかり進むと大学の生垣に沿うて町が左側即ち北方へ折れてゐる。其のまゝ一町ばかり進むと東方から他の町が丁字形に突き當って来る、自然大学の生垣も其処から東方へ曲ってゐるのである。其の東方から突き當ってゐる町は根津須賀町と称して根津権現の社は其の町にある。その根津須賀町が西へ突き當ったところ、農学部の生垣の東へ曲り角の西側あたりが本郷駒込追分町である。農学部の生垣と併行してゐるあたりは三十一番地で、須賀町の突き當ってゐる処から北が三十番地である。三十番地の北は駒込蓬莱町に接してゐる。大学に近い関係からかこのあたりには旅館兼高等下宿が多い。三十番地の表通りは十敷戸の小商店が軒を並べてゐるが西某へ入って見ると数十戸の小住宅が建ち並んでゐる。…」。
柳原極堂の『子規の「下宿がへ」に就て』に場所が詳細に書かれていました。よく分かりますね!!
次回も「正岡子規の東京を歩く」の続編を掲載します。
子規東京地図-4-