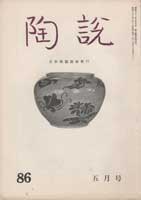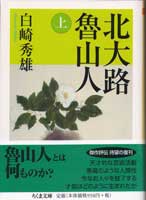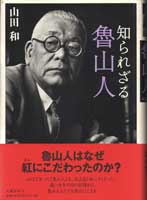<「陶説 北大路魯山人伝」 吉田耕三>
2015年4月11日追加
白崎秀雄氏の「北大路魯山人」と山田和氏の「知られざる魯山人」だけではよく分からないところがあるので、最初に戻って、「陶説」の昭和35年(1960)5月
86号から1年半掲載された吉田耕三氏の「北大路魯山人伝」を新たに掲載することにしました(これが魯山人について書かれた最初の評伝です)。住所等が記載されたハガキや封筒が残っていれば正確な場所がわかるのですが、人からの伝聞のみで書いているケースがほとんどで何方のが正しいのかよく分かりません。困ったものです。
「陶説」の昭和35年(1960)5月 86号から1年半掲載された吉田耕三氏の「北大路魯山人伝」からです。
「… 魯山人の家系は、京都北区にある上賀茂神社、正しく言へば賀茂別雷神社の社家の中にある。遠く伝説にまで逆れば、神武大皇を熊野から大和に先導した八咫鳥(武角身命)を祖神大した賀茂族は、奈良から京都の地に都を移される以前から、山城国の大部を開拓していたが、祖神武角身命と女神に依姫命を下鴨の賀茂御祖神社に、又玉依姫命と高靇神。との御子神の別雷神をば、賀茂別雷神社にまつって奉仕していた。欽明天皇の頃から賀茂祭は記録にのつていて、A・D六七八(天政天皇六年)には賀茂神社の造営が行はれたことになっているが、実際神社に奉仕した社司、社家の記録は、A・D九五五(天暦九年)賀茂族中興の祖とあがめられている賀茂在実からほゞ明確に残されている。それによると、在実には長男忠成(嫡流)と、その弟忠頼(庶流)の二人の男子があり。嫡流にはその名の一字に氏を、庶流には、平・保・宗・弘・重・兼・清・顕・成・俊・直・幸・久・経・能、いづれか一字をつけさせて区別するようになった。
家系はすべて男系に限り、女系は許されなかった。戦国時代以降、賀茂族の賀茂の氏名のほかに、県つまり分田主として今日の苗字をつけはしめたが、これとても、神主を出すことの出来る家柄と、社人の家柄とは厳格に区別して来た。明治以降、神主は宮司となったが、宮司を出す家柄を社司と改めて、松下・梅辻・森・鳥居大路・富野・岡本・林の七
家とし、社人は社家と改められて百二十軒と限られた。この社家に藤木・坐田・松山・井関・北大路・酉池・山本等の苗字がある。…」。
下記にある2名の評伝も含めて比較すると、一番詳細に書かれているようにおもえます。ただ、最初にも書きましたが、内容は人伝えの伝聞がほとんどです。ただ魯山人から直接聞くことができた唯一の人です。下記の二人の評伝はこの吉田耕三氏の「北大路魯山人伝」が元になっていることは確かです。ただ、裏付け調査をほとんどしていないようで、間違いも多そうです。
【北大路魯山人(きたおおじ ろさんじん 1883年(明治16年)3月23日 - 1959年(昭和34年)12月21日)は、日本の芸術家。本名は北大路
房次郎(きたおおじ ふさじろう)】
晩年まで、篆刻家・画家・陶芸家・書道家・漆芸家・料理家・美食家などの様々な顔を持っていた。
明治16年(1883)、京都市上賀茂(現在の京都市北区)北大路町に、上賀茂神社の社家・北大路清操、とめ(社家・西池家の出身)の次男として生まれる。生活は貧しく、魯山人の上に夫の連れ子が一人いた。魯山人が生まれる前に父親が自殺、母親も失踪したため親戚をたらい回しにされる。一度農家に養子に出されるが、6歳の時に竹屋町の木版師・福田武造の養子となり、10歳の時に梅屋尋常小学校を卒業。烏丸二条の千坂和薬屋に丁稚奉公に出された。明治36年(1903)、書家になることを志して上京。翌年の日本美術展覧会で一等賞を受賞し、頭角を現す。明治38年(1905)、町書家・岡本可亭の内弟子となり、明治41年から中国北部を旅行し、書道や篆刻を学んだ。大正4年(1915)、福田家の家督を長男に譲り、自身は北大路姓に復帰。その後も長浜をはじめ京都・金沢の素封家の食客として転々と生活することで食器と美食に対する見識を深めていった。大正6年(1917)便利堂の中村竹四郎と知り合い交友を深め、その後、古美術店の大雅堂を共同経営することになる。大雅堂では、古美術品の陶器に高級食材を使った料理を常連客に出すようになり大正10年(1921)会員制食堂・「美食倶楽部」を発足。自ら厨房に立ち料理を振舞う一方、使用する食器を自ら創作していた。大正14年(1925)には東京・永田町に「星岡茶寮(ほしがおかさりょう)」を中村とともに借り受け、中村が社長、魯山人が顧問となり、会員制高級料亭を始めた。昭和2年(1927)には宮永東山窯から荒川豊蔵を鎌倉山崎に招き、魯山人窯芸研究所・星岡窯(せいこうよう)を設立して本格的な作陶活動を開始する。1928年(昭和3年)には日本橋三越にて星岡窯魯山人陶磁器展を行う。魯山人の横暴さや出費の多さから、昭和11年(1936)星岡茶寮の経営者・中村竹四郎からの内容証明郵便で解雇通知を言い渡され、魯山人は星岡茶寮を追放、同茶寮は昭和20年の空襲により焼失した。戦後は経済的に困窮し不遇な生活を過ごすが、昭和21年(1946)には銀座に自作の直売店「火土火土美房(かどかどびぼう)」を開店し、在日欧米人からも好評を博す。昭和29年(1954)にロックフェラー財団の招聘で欧米各地で展覧会と講演会が開催され、その際にパブロ・ピカソ、マルク・シャガールを訪問。昭和30年には織部焼の重要無形文化財保持者(人間国宝)に指定されるも辞退。昭和34年(1959)に肝吸虫(古くは「肝臓ジストマ」と呼ばれた寄生虫)による肝硬変のため横浜医科大学病院で死去。平成10年、管理人の放火と焼身自殺により、魯山人の終の棲家であった星岡窯内の家屋が焼失した。(ウイキペディア参照)
★写真は「陶説」の昭和35年(1960)5月発行の86号です。ここから1年半、吉田耕三氏の「北大路魯山人伝」が掲載されます。ただ、きっちり毎月掲載された訳では無く、途中、2回休んでいますから、18回掲載で昭和36年12月まで掛かっています。昭和36年12月号を見ると、最後に”つづく”と記載があるのですが、その後の号を見ても”つづき”がありません。突然掲載がとり止めになったという感じです。中止になった理由がよく分かりません。
【吉田 耕三(よしだ こうぞう、1915年 - )】
神奈川県横浜市出身の美術評論家。日本画家の速水御舟の甥。御舟から日本画を学び、御舟の日本画の鑑定人を務める。現代陶芸の旗手といわれた加守田章二の才能を認める。陶芸の公募展・日本陶芸展創設を企画する。東京美術学校(現・東京藝術大学)日本画科卒業。復員後、世界的な陶磁学者で陶芸家・小山冨士夫の助手となり、その後、東京帝室博物館(現・東京国立博物館)陶磁器主任で、陶磁器の批評と収集の天才といわれる北原大輔、人間国宝・荒川豊蔵、百五銀行頭取で陶芸作家・川喜田半泥子から焼き物に関する学問と技術を学ぶ。北大路魯山人の弟子でもある。東京国立近代美術館の創立時から勤務して日本画と工芸を担当し、総括主任研究官などを歴任。日本伝統工芸展鑑査委員、日本陶芸展運営委員・審査員を務める。(ウイキペディア参照)

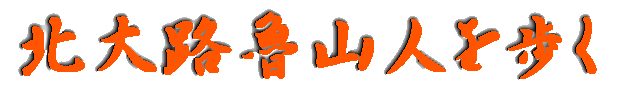
●魯山人の東京を歩く -1-
初版2015年3月7日
二版2015年4月11日 <V01L01> 「陶説」の北大路魯山人伝を掲載 暫定版
二版2015年4月11日 <V01L01> 「陶説」の北大路魯山人伝を掲載 暫定版
新企画、「北大路魯山人を歩く」の掲載を始めます。直ぐに掲載を始められるとおもったのですが、伝記的な本を複数冊読んでみると、少しずつ食い違ったりしており、調査に多くの時間が掛かってしまいました。まず最初は東京から歩いてみます。京都も取材済みなのですが、もう少し調べる必用がありそうにおもっています。
<「北大路魯山人」 白崎秀雄>
魯山人の伝記としては吉田耕三氏の次に書かれた本で、白崎秀雄氏が昭和46年(1971)に文藝春秋社より出版したものです。白崎秀雄氏はその後何度か加筆修正し、昭和60年(1885)に新潮社より再度出版されています。最初は吉田耕三氏の「北大路魯山人伝」を鵜呑みにして書いていたようですが、間違いに気づき、修正を加えたようです。文庫本化は平成9年(1997)、中央公論社より、続いて平成25年(2013)ちくま文庫として最新版が出版されています。
白崎秀雄氏の「北大路魯山人」の書き出しです。
「 第 一 章
一、一太上京
大正九年(一九二〇)十一月半ぼすぎの某日、宵。
東京京橋東仲通り、「大雅堂美術店」の一階六畳間で、一人の少年が端近に膝をそろえていた。
板床のところに、ホームスパン地の洋服にノーネクタイの、大きな身体の「先生」が、さかんにビールを呷り、料理を口に運んでいる。となりでめくら縞の着物の「旦那さん」がビールを注ぎ、他に馴染客も三、四人「先生」をかこむようにして、賑かに飲み食いしている。
鼻下髭の「先生」は、肉付きゆたかな頬を桜いろにして、大声で美術のこと料理のこと、あるいは人物月旦を談じていたが、
「おい、よう来たな、よう来た。お前名前は一太だったな」
と、鼈甲ぶち眼鏡の部厚いレンズの奥から少年を見すえて、いいかけて来た。一分刈の青い頭を、折るように下げて、少年は「先生」にそのとき鷲づかみにされたような思いがした。…」。
最初、出版されたのは昭和46年、魯山人が無くなったのが昭和34年ですから、無くなってから12年で伝記を書いたわけです。まだ魯山人の関係者の方々がご存命のころだったとおもいます。死去から10年以上経過しており、言えなかったことも語れるようになる時期になったころです。叉、関係者に実際にヒヤリングして書けるわけですから一番いいころだとおもいます。
★写真はちくま文庫の白崎秀雄著「北大路魯山人」です。平成25年(2013)発行です。
【白崎 秀雄(しらさき ひでお、1920年-1992年)作家、美術評論家、福井市出身】
伝記小説に新境地を開き、骨董、書画、日本絵画、篆刻などの関連著作が多い。北大路魯山人研究で著名で、魯山人を世に広めた人物としても知られる。魯山人の芸術性・技術的な特異性を鋭く評価した。(ウイキペディア参照)
魯山人の伝記としては吉田耕三氏の次に書かれた本で、白崎秀雄氏が昭和46年(1971)に文藝春秋社より出版したものです。白崎秀雄氏はその後何度か加筆修正し、昭和60年(1885)に新潮社より再度出版されています。最初は吉田耕三氏の「北大路魯山人伝」を鵜呑みにして書いていたようですが、間違いに気づき、修正を加えたようです。文庫本化は平成9年(1997)、中央公論社より、続いて平成25年(2013)ちくま文庫として最新版が出版されています。
白崎秀雄氏の「北大路魯山人」の書き出しです。
「 第 一 章
一、一太上京
大正九年(一九二〇)十一月半ぼすぎの某日、宵。
東京京橋東仲通り、「大雅堂美術店」の一階六畳間で、一人の少年が端近に膝をそろえていた。
板床のところに、ホームスパン地の洋服にノーネクタイの、大きな身体の「先生」が、さかんにビールを呷り、料理を口に運んでいる。となりでめくら縞の着物の「旦那さん」がビールを注ぎ、他に馴染客も三、四人「先生」をかこむようにして、賑かに飲み食いしている。
鼻下髭の「先生」は、肉付きゆたかな頬を桜いろにして、大声で美術のこと料理のこと、あるいは人物月旦を談じていたが、
「おい、よう来たな、よう来た。お前名前は一太だったな」
と、鼈甲ぶち眼鏡の部厚いレンズの奥から少年を見すえて、いいかけて来た。一分刈の青い頭を、折るように下げて、少年は「先生」にそのとき鷲づかみにされたような思いがした。…」。
最初、出版されたのは昭和46年、魯山人が無くなったのが昭和34年ですから、無くなってから12年で伝記を書いたわけです。まだ魯山人の関係者の方々がご存命のころだったとおもいます。死去から10年以上経過しており、言えなかったことも語れるようになる時期になったころです。叉、関係者に実際にヒヤリングして書けるわけですから一番いいころだとおもいます。
★写真はちくま文庫の白崎秀雄著「北大路魯山人」です。平成25年(2013)発行です。
【白崎 秀雄(しらさき ひでお、1920年-1992年)作家、美術評論家、福井市出身】
伝記小説に新境地を開き、骨董、書画、日本絵画、篆刻などの関連著作が多い。北大路魯山人研究で著名で、魯山人を世に広めた人物としても知られる。魯山人の芸術性・技術的な特異性を鋭く評価した。(ウイキペディア参照)
<「知られざる魯山人」 山田和>
山田和の「知られざる魯山人」は 北大路魯山人の関する伝記物で一番新しく書かれたものです。平成15年(2003)から「諸君!」に連載され、平成19年(2007)10月に「知られざる魯山人」として出版されています。昭和60年(1885)に白崎秀雄氏が書かれた「北大路魯山人」に対抗するものとして云われていますが、読んでみるとそうでもないようです。魯山人の死去から相当経って、関係者もほとんどいない中で”よく調べて書かれている”とおもいました。山田氏の父親が地元の新聞記者だったころ魯山人と親しかったのがきっかけのようです。
山田和氏の「知られざる魯山人」から、書き出しです。
「 一 ある雪の日、私の家から魯山人のすべてを持ち去る男がやって来た……
あれは昭和三十五年(一九六〇年)一月のことだ。
吹雪の北陸の小さな駅に一人の男が降り立ち、駅前からの雪道をおぼつかない足取りで歩きはじめた。分厚いオーバーコートに身を包んでいても、男は土地の者には見えなかった。長靴を履かぬ者のいないその季節に、彼は革靴を履いていたからである。
男は、雪さえなければ数分の道を、おそらく三倍もかけて私の家にやって来た。難儀な雪の道中を私が見ていたのではない。母に言われて、玄関へ客の靴を揃えに行ったとき、私は男のずぶずぶになった靴を見てそう思ったのである。
男は道具屋に商売替えした北大路魯山人の元使用人で、北鎌倉に近い大船・山崎の魯山人の星岡窯を去ったあと、近くの葉山で店舗なしの道具商をはじめていた。道具商といっても扱うのは魯山人の作品だけだが、その男が魯山人が亡くなって数週間後に突然私の家に現れたのである。…」。
魯山人が亡くなった昭和30年代ではまだまだ魯山人の陶芸品に関しては価値が認められていなかったようです。先見の明があるものがいち早く魯山人の陶芸品を集めていたようです。今ではおよびもつかない金額になっているようです。
★写真は文藝春秋社版、平成19年(2007)発行の「知られざる魯山人」です。魯山人の伝記としては最後の出版となるのではないかとおもいます。関係者も少なくなった今となってはこれより詳しい伝記は出てこないとおもいます。参考図書を比較して矛盾が無いか検証し、裏付けを取って書かれています。一番正しいとおもうのですが、完璧ではないようです。
【山田 和(やまだ かず、男性、1946年 - )ノンフィクション作家】
富山県砺波市生まれ。1973年より福音館書店勤務。1993年退社しノンフィクション作家となる。1996年『インド ミニアチュール幻想』を刊行し、講談社ノンフィクション賞受賞。2008年『知られざる魯山人』で大宅壮一ノンフィクション賞受賞。地元の新聞記者だった父親が魯山人と親しかった。(ウイキペディア参照)
山田和の「知られざる魯山人」は 北大路魯山人の関する伝記物で一番新しく書かれたものです。平成15年(2003)から「諸君!」に連載され、平成19年(2007)10月に「知られざる魯山人」として出版されています。昭和60年(1885)に白崎秀雄氏が書かれた「北大路魯山人」に対抗するものとして云われていますが、読んでみるとそうでもないようです。魯山人の死去から相当経って、関係者もほとんどいない中で”よく調べて書かれている”とおもいました。山田氏の父親が地元の新聞記者だったころ魯山人と親しかったのがきっかけのようです。
山田和氏の「知られざる魯山人」から、書き出しです。
「 一 ある雪の日、私の家から魯山人のすべてを持ち去る男がやって来た……
あれは昭和三十五年(一九六〇年)一月のことだ。
吹雪の北陸の小さな駅に一人の男が降り立ち、駅前からの雪道をおぼつかない足取りで歩きはじめた。分厚いオーバーコートに身を包んでいても、男は土地の者には見えなかった。長靴を履かぬ者のいないその季節に、彼は革靴を履いていたからである。
男は、雪さえなければ数分の道を、おそらく三倍もかけて私の家にやって来た。難儀な雪の道中を私が見ていたのではない。母に言われて、玄関へ客の靴を揃えに行ったとき、私は男のずぶずぶになった靴を見てそう思ったのである。
男は道具屋に商売替えした北大路魯山人の元使用人で、北鎌倉に近い大船・山崎の魯山人の星岡窯を去ったあと、近くの葉山で店舗なしの道具商をはじめていた。道具商といっても扱うのは魯山人の作品だけだが、その男が魯山人が亡くなって数週間後に突然私の家に現れたのである。…」。
魯山人が亡くなった昭和30年代ではまだまだ魯山人の陶芸品に関しては価値が認められていなかったようです。先見の明があるものがいち早く魯山人の陶芸品を集めていたようです。今ではおよびもつかない金額になっているようです。
★写真は文藝春秋社版、平成19年(2007)発行の「知られざる魯山人」です。魯山人の伝記としては最後の出版となるのではないかとおもいます。関係者も少なくなった今となってはこれより詳しい伝記は出てこないとおもいます。参考図書を比較して矛盾が無いか検証し、裏付けを取って書かれています。一番正しいとおもうのですが、完璧ではないようです。
【山田 和(やまだ かず、男性、1946年 - )ノンフィクション作家】
富山県砺波市生まれ。1973年より福音館書店勤務。1993年退社しノンフィクション作家となる。1996年『インド ミニアチュール幻想』を刊行し、講談社ノンフィクション賞受賞。2008年『知られざる魯山人』で大宅壮一ノンフィクション賞受賞。地元の新聞記者だった父親が魯山人と親しかった。(ウイキペディア参照)
<「別冊 太陽 魯山人」>
定番の「別冊 太陽 魯山人」です。「別冊 太陽」は内容も充実していて大変参考になるので一通り揃えている中の一冊です。中に座談会があって、上記項目に書かれている”一太”氏が参加しています。面白いです。叉、星丘茶寮について細かく書かれているので大変参考になります。
「別冊 太陽 魯山人」から座談会 ”魯山人の味覚と料理”からです。
「[座談会]
魯山人の味覚ど料理
その盛時には、夜毎、各界の貴顕紳士がより集い、魯山人が思う存分腕をふるった星岡茶寮。
当時、天下第一の格式を誇ったその魁苧の裏方を勤めた人びとによって明かされる、人間魯山人と、その料理哲学。
武山一太
島村きよ
松浦沖太(誌上参加)
平野雅立早(司会)
美食倶楽部、花の茶屋
平野 今日の座談会は「魯山人の味覚と料理」というテーマになっております。星岡茶寮以前に”美食倶楽部”とか”花の茶屋”時代がございますが、とくにウェートをおきたいのは、星岡茶寮というものは現在の料苧とは違うと。その料理の実態、もてなしの仕方、客層などについてのお話を伺えればと思っております。
まず武山さんに魯山人との結び付きを手短かにお話ししていただいて、お話の糸口をつけていただきたいと思います。
武山 わたしが先生と一番最初に会ったのは大正九年ですからね。
平野 じゃ、先生とお知り合いになったときは、もう大雅堂を経営なさっていた。
武山 もうちゃんとできていたんです。柱をみんな黒くしてね、ウィンドーがあってね。
平野 そこは商売は成り立っていたんでしょうか。
武山 成り立つもなにも、景気がよくて、すごくよかった。
平野 その店舗は何坪ぐらいの店舗でしたか。
武山 小さいもんです。間口が三間ぐらいです。それで一間ぐらいのウィンドーがあって、こっち見てるでしょ。角の店ですから、横からも入れる。入ったらすぐ階段をトントンと上がると三間あったんです。表に八畳の間があって、その奥に三畳か四畳わたしが寝ていたところがあって、その奥にまた四畳半ぐらいがあったんです。
平野 その二階は何をするんですか。
武山 八畳に中村竹四郎さんと北大路さんとが寝てたわけです。
平野 じゃ、住まいを兼ねてたわけですね。
武山 そうそう。で、そうしておったらそこへいろんな人がやってくるんですよ、家具屋さんだとか。北大路さん面白いから。あのとおりでしよ、サルマタ一つでもってワー。ちゅう感じでしゃべりまくるから面白いしね、みんな来た人が動かな
いんですよ。で、昼になると飯食わなきゃいかんでしよ。そうすると、魚仙という魚屋が少し先にあるんですが、その魚屋へ自分が買い物に行って、みんなに飯食わしてやろうというんでやりだしたんですよ。
平野 ほォ。それが天下の星岡茶寮の一番最初。じゃ、大雅堂でおもてなしをする料理材料はどうなさったんですか。
武山 北大路さんが近所の魚屋から生きた魚を自分で買ってきて、カツオならカツオの刺身をやるわけですよ。
平野 大雅堂の中に台所もあったわけなんですか。武山 ええ、奥に台所があり板の間かあって、板の間の下はすでにコンクリにしてあってね、スッポンやなんかいましたよ。ウナギは表に生け簀こしらえて、石燈籠やなんかがあるところヘウナギを放してあったですね。
平野 じゃ、名目はあくまでも人雅堂美術店で、中で食事を作ると。
武山 ええ。食事って、最初はカネ取ったわけじゃないんですよ。だけども、それじゃやりきれんから、市電のパスみたいのをこさえたんですよ。たしか一食二十五銭でしょうね、一枚持ってきたら食わせてやるちゅうて、それやったわけですよ。そうなると、どうしても小僧がいるでしよ。それでわたしが……渡りに船ということになる。
平野 それが震災まで続いたわけですね。
武山 そうそう。それで朝になると鴻巣はもちろんそうだし、近所に丸屋というスッポン屋を出しましたが、それも北大路さんが指導してたんですよね。…」
又、続きが面白いのですが、”鴻巣(メイゾン鴻之巣)”が書かれています。「メイゾン鴻之巣」は大正4年頃には日本橋木原店(きわらだな)に転居(今のCOREDO日本橋と日本橋西川の間の通)、大正9年末には京橋区南傳馬2−12、現在の明治屋の所に転居しています。大正14年に経営者の駒蔵が死去するとお店は無くなります。ですから、京橋区南傳馬二丁目のころの話しだとおもわれます。
★写真は昭和58年(1983)3月発行の「別冊 太陽 魯山人」です。この頃が魯山人人気がピークのころではなかったかとおもいます。
定番の「別冊 太陽 魯山人」です。「別冊 太陽」は内容も充実していて大変参考になるので一通り揃えている中の一冊です。中に座談会があって、上記項目に書かれている”一太”氏が参加しています。面白いです。叉、星丘茶寮について細かく書かれているので大変参考になります。
「別冊 太陽 魯山人」から座談会 ”魯山人の味覚と料理”からです。
「[座談会]
魯山人の味覚ど料理
その盛時には、夜毎、各界の貴顕紳士がより集い、魯山人が思う存分腕をふるった星岡茶寮。
当時、天下第一の格式を誇ったその魁苧の裏方を勤めた人びとによって明かされる、人間魯山人と、その料理哲学。
武山一太
島村きよ
松浦沖太(誌上参加)
平野雅立早(司会)
美食倶楽部、花の茶屋
平野 今日の座談会は「魯山人の味覚と料理」というテーマになっております。星岡茶寮以前に”美食倶楽部”とか”花の茶屋”時代がございますが、とくにウェートをおきたいのは、星岡茶寮というものは現在の料苧とは違うと。その料理の実態、もてなしの仕方、客層などについてのお話を伺えればと思っております。
まず武山さんに魯山人との結び付きを手短かにお話ししていただいて、お話の糸口をつけていただきたいと思います。
武山 わたしが先生と一番最初に会ったのは大正九年ですからね。
平野 じゃ、先生とお知り合いになったときは、もう大雅堂を経営なさっていた。
武山 もうちゃんとできていたんです。柱をみんな黒くしてね、ウィンドーがあってね。
平野 そこは商売は成り立っていたんでしょうか。
武山 成り立つもなにも、景気がよくて、すごくよかった。
平野 その店舗は何坪ぐらいの店舗でしたか。
武山 小さいもんです。間口が三間ぐらいです。それで一間ぐらいのウィンドーがあって、こっち見てるでしょ。角の店ですから、横からも入れる。入ったらすぐ階段をトントンと上がると三間あったんです。表に八畳の間があって、その奥に三畳か四畳わたしが寝ていたところがあって、その奥にまた四畳半ぐらいがあったんです。
平野 その二階は何をするんですか。
武山 八畳に中村竹四郎さんと北大路さんとが寝てたわけです。
平野 じゃ、住まいを兼ねてたわけですね。
武山 そうそう。で、そうしておったらそこへいろんな人がやってくるんですよ、家具屋さんだとか。北大路さん面白いから。あのとおりでしよ、サルマタ一つでもってワー。ちゅう感じでしゃべりまくるから面白いしね、みんな来た人が動かな
いんですよ。で、昼になると飯食わなきゃいかんでしよ。そうすると、魚仙という魚屋が少し先にあるんですが、その魚屋へ自分が買い物に行って、みんなに飯食わしてやろうというんでやりだしたんですよ。
平野 ほォ。それが天下の星岡茶寮の一番最初。じゃ、大雅堂でおもてなしをする料理材料はどうなさったんですか。
武山 北大路さんが近所の魚屋から生きた魚を自分で買ってきて、カツオならカツオの刺身をやるわけですよ。
平野 大雅堂の中に台所もあったわけなんですか。武山 ええ、奥に台所があり板の間かあって、板の間の下はすでにコンクリにしてあってね、スッポンやなんかいましたよ。ウナギは表に生け簀こしらえて、石燈籠やなんかがあるところヘウナギを放してあったですね。
平野 じゃ、名目はあくまでも人雅堂美術店で、中で食事を作ると。
武山 ええ。食事って、最初はカネ取ったわけじゃないんですよ。だけども、それじゃやりきれんから、市電のパスみたいのをこさえたんですよ。たしか一食二十五銭でしょうね、一枚持ってきたら食わせてやるちゅうて、それやったわけですよ。そうなると、どうしても小僧がいるでしよ。それでわたしが……渡りに船ということになる。
平野 それが震災まで続いたわけですね。
武山 そうそう。それで朝になると鴻巣はもちろんそうだし、近所に丸屋というスッポン屋を出しましたが、それも北大路さんが指導してたんですよね。…」
又、続きが面白いのですが、”鴻巣(メイゾン鴻之巣)”が書かれています。「メイゾン鴻之巣」は大正4年頃には日本橋木原店(きわらだな)に転居(今のCOREDO日本橋と日本橋西川の間の通)、大正9年末には京橋区南傳馬2−12、現在の明治屋の所に転居しています。大正14年に経営者の駒蔵が死去するとお店は無くなります。ですから、京橋区南傳馬二丁目のころの話しだとおもわれます。
★写真は昭和58年(1983)3月発行の「別冊 太陽 魯山人」です。この頃が魯山人人気がピークのころではなかったかとおもいます。
<京橋区高代町三番地の丹羽茂正宅>
2015年4月11日 ”高代町六番地”を追加
魯山人は明治36年秋、20歳の時に京都から上京します。行き先は伯母・中大路屋寸に教えられた屋寸の娘・かねの嫁ぎ先、京橋区高代町三番地の丹羽茂正宅でした。生き別れた母親が東京に居ると聞いたのと、東京で一旗揚げようとしたのだとおもいます。又、京都ではどうしても限界があると感じたのだともおもいます。東海道線が全線開通したのは明治22年ですから、鉄道で東京まで行くことができました。
山田和氏の「知られざる魯山人」からです。
「… 四 失望からはじまった房次郎の青春
手に風呂敷包みを一つ下げ、二十歳の「西洋看板描き」兼「一字書き賞金稼ぎ」の福田房次郎が終着駅の新橋に降り立ったのは、魯山人自身の回想によれば明治三十六年(一九〇三年)秋の夕暮れのことであった。当時東海道線(新橋−神戸間、明治二十二年開通)の直通は日に五本、急行が二本に鈍行が三本だから、彼の回想をもとにすると京都を深夜零時十五分発の鈍行で発って、約十七時間半後の同日午後五時四十分に新橋に着いたことになる。
風呂敷包みのほかには懐中に五円入りの財布だけで、羽織袴で一通りの正装をした彼はそのまま伯母・中大路屋寸に教えられた屋寸の娘・かねの嫁ぎ先、京橋区高代町三番地の丹羽茂正宅へ向かった。丹羽宅までは道を訊ねながら歩いたというから、半里ほどの道のりを三、四十分かけたのだろう。途中の銀座通りを愉しむゆとりは、おそらくなかったにちがいない。…」
明治36年1月の時刻表を見ると、京都ー東京間の運賃は三等で3円75銭、二等で6円57錢とあります。5円持っていたようなので、十分に東京まで行けました。京都から東京までは急行が2本、普通が2本(14時28分発、0時23分発)、真夜中の東京行は京都発0時23分、新橋着が18時53分と書かれていました。上記と少し違います。10ヶ月位違うので、時刻が少し変ったのかもしれません。明治39年の時刻表では、京都から東京までは最急行が1本、急行が2本、普通が3本(12時28分発、15時10分発、0時18分発)、真夜中の東京行は京都発0時18分、新橋着が17時12分と書かれていました。これも上記と少し違います。この時は東京駅はまだ出来ておらず、東海道線は新橋まででした。
新橋駅から京橋区高代町三番地までのルートは、駅から銀座通りを京橋まで進み、橋を越えてから右に曲がり、弾正橋を渡って直ぐに左に曲がれば高代町三番地です(一般的なルート)。
白崎秀雄氏の「北大路魯山人」からです。
「… 福田房次郎は、ついその前日の朝、京都から風呂敷包み一つを提げて、新橋駅へ着いたばかりであった。
新橋から歩いて、現今の京橋と桜橋の中間の高代町三番地に丹羽茂正方を訪ねた。丹羽の妻は、房次郎の父北人路清操の妹屋須が、中大路家に嫁して生んだ長女である。
房次郎は、京都二条通西洞院の屋須の許で、生れてはじめて生母が東京にいることをきいた。丹羽方へ行けば、トメの居所もわかるはずだという。
彼はたまたま得たペンキによる西洋看板書きの注文を、二夜ほとんど一睡もせずに仕上げ、受けとった五円を懐中に、京都を発った。養父母の福田武造・フサには無断、平常着のままで。房次郎はかねて書家を志し、上京を望んでいたが、木版職人の武造に、「親を見捨てる気か」と反対され、果さずに来た。房次郎は、実母に会うためにも自らの志望のためにも、養家には上京をかくしておかねばならなかった。
丹羽は、レッテル等にニスで防水加工をする俗称ニス引屋を営んでいた。客を養うことを吝まぬ人であった。清晃も氏雅も、同家に滞留したことが度々ある。
房次郎が訪ねたとき、近所へ出かけていた丹羽は、まもなく帰宅して房次郎の身上と来意をきくや、労って家に上げ、泊めた。…」
こちらの方は、乗った列車まで書かれていませんでした。復刻版の時刻表を見ているので、数年おきにしか時刻表がありません。何処かで明治36年秋頃の時刻表を見ることができたら調べておきます。
吉田耕三氏の「北大路魯山人伝」からです。
「… 明治三十六年の秋の夕暮の事、その頃の松消堂は京橋高代町三番地(現在京橋と桜橋の都電の停留所の中間で昭和通りを横切つて少し行つた所に新弾正橋がある。(写真参照)この橋を渡りきつた電車道の中央あたり(矢印)(明治四十年頃道路の拡張で店をば同じく京橋高代町六番地に移転した。)にあつた。総二階で二間間口、表は四枚の濡障子で、左右に開く真中の二枚に人々松清堂と屋号が墨書してあつた。その障子をあけて、手に風呂敷包みをさげ、羽織をちやんと着てひと通りの身成りをしながら、何処となく身すぽらしい感じのした大柄な青年が、おずおずとした態度で人つて来た時の事を、当時十才位であつた長女の清さんが今でもよく覚えている。
その青年は、けげんな面ざしで応待に出たかねさんに、「京都の二条から、こちらを尋ねるように云われて参りましたが、私は福田房次郎と申します。」と自己紹介をした。
彼は其の頃、鉄道の終着駅であつた新橋から、この京橋高代町まで人に聞き聞き歩いて来たと云つていた。…」
”高代町三番地”は上記二人と同じです。ただ、次に移転した”高代町六番地”を書いているのは吉田耕三氏だけです。後の二人は裏付けが取れなかったのだとおもわれえます。
★写真の正面、道路の上辺りが高代町三番地になります。先の首都高速道路の下にある橋は弾正橋です。明治時代の弾正橋はもっと左側にありました(明治40年の京橋区地図より抜粋)。大正時代に新しく馬塲先門からの道を通したため、新しい弾正橋を架設、今までの弾正橋を「元弾正橋」としていました(大正元年の京橋区地積図より抜粋)。このように新道路ができたため、高代町三番地が無くなってしまっています。高代町六番地は写真左端の道を80m程進んだ左側にあります(下記の地図参照)。
弾正橋は明治11年(1878)11月に京橋区の楓川に、アメリカ人技師スクワイヤー・ウイップルの発明した形式を元に工部省赤羽分局により製作、架橋された橋です。当時は橋幅は9.1m(5間)あったと記録に残っています。架設経費は4058円。付近に島田弾正屋敷があったため、弾正橋と称されたそうです。当時、馬場先門から本所や深川を結ぶ主要路であったので、文明開化のシンボル的存在の鉄橋でした。大正2年(1912)の市区改正事業により、北側に新しく弾正橋が架橋されたため、「元弾正橋」と改称され、さらに大正12年(1923)の関東大震災後の震災復興計画によって廃橋となりましたが、その由緒を惜しんで門前仲町の富岡八幡宮の裏手に移設されています。移設当時は橋下は八幡堀という河川でしたが、後に埋め立てられ、現在のような人道陸橋となっています。(ウイキペディア参照)
2015年4月11日 ”高代町六番地”を追加
魯山人は明治36年秋、20歳の時に京都から上京します。行き先は伯母・中大路屋寸に教えられた屋寸の娘・かねの嫁ぎ先、京橋区高代町三番地の丹羽茂正宅でした。生き別れた母親が東京に居ると聞いたのと、東京で一旗揚げようとしたのだとおもいます。又、京都ではどうしても限界があると感じたのだともおもいます。東海道線が全線開通したのは明治22年ですから、鉄道で東京まで行くことができました。
山田和氏の「知られざる魯山人」からです。
「… 四 失望からはじまった房次郎の青春
手に風呂敷包みを一つ下げ、二十歳の「西洋看板描き」兼「一字書き賞金稼ぎ」の福田房次郎が終着駅の新橋に降り立ったのは、魯山人自身の回想によれば明治三十六年(一九〇三年)秋の夕暮れのことであった。当時東海道線(新橋−神戸間、明治二十二年開通)の直通は日に五本、急行が二本に鈍行が三本だから、彼の回想をもとにすると京都を深夜零時十五分発の鈍行で発って、約十七時間半後の同日午後五時四十分に新橋に着いたことになる。
風呂敷包みのほかには懐中に五円入りの財布だけで、羽織袴で一通りの正装をした彼はそのまま伯母・中大路屋寸に教えられた屋寸の娘・かねの嫁ぎ先、京橋区高代町三番地の丹羽茂正宅へ向かった。丹羽宅までは道を訊ねながら歩いたというから、半里ほどの道のりを三、四十分かけたのだろう。途中の銀座通りを愉しむゆとりは、おそらくなかったにちがいない。…」
明治36年1月の時刻表を見ると、京都ー東京間の運賃は三等で3円75銭、二等で6円57錢とあります。5円持っていたようなので、十分に東京まで行けました。京都から東京までは急行が2本、普通が2本(14時28分発、0時23分発)、真夜中の東京行は京都発0時23分、新橋着が18時53分と書かれていました。上記と少し違います。10ヶ月位違うので、時刻が少し変ったのかもしれません。明治39年の時刻表では、京都から東京までは最急行が1本、急行が2本、普通が3本(12時28分発、15時10分発、0時18分発)、真夜中の東京行は京都発0時18分、新橋着が17時12分と書かれていました。これも上記と少し違います。この時は東京駅はまだ出来ておらず、東海道線は新橋まででした。
新橋駅から京橋区高代町三番地までのルートは、駅から銀座通りを京橋まで進み、橋を越えてから右に曲がり、弾正橋を渡って直ぐに左に曲がれば高代町三番地です(一般的なルート)。
白崎秀雄氏の「北大路魯山人」からです。
「… 福田房次郎は、ついその前日の朝、京都から風呂敷包み一つを提げて、新橋駅へ着いたばかりであった。
新橋から歩いて、現今の京橋と桜橋の中間の高代町三番地に丹羽茂正方を訪ねた。丹羽の妻は、房次郎の父北人路清操の妹屋須が、中大路家に嫁して生んだ長女である。
房次郎は、京都二条通西洞院の屋須の許で、生れてはじめて生母が東京にいることをきいた。丹羽方へ行けば、トメの居所もわかるはずだという。
彼はたまたま得たペンキによる西洋看板書きの注文を、二夜ほとんど一睡もせずに仕上げ、受けとった五円を懐中に、京都を発った。養父母の福田武造・フサには無断、平常着のままで。房次郎はかねて書家を志し、上京を望んでいたが、木版職人の武造に、「親を見捨てる気か」と反対され、果さずに来た。房次郎は、実母に会うためにも自らの志望のためにも、養家には上京をかくしておかねばならなかった。
丹羽は、レッテル等にニスで防水加工をする俗称ニス引屋を営んでいた。客を養うことを吝まぬ人であった。清晃も氏雅も、同家に滞留したことが度々ある。
房次郎が訪ねたとき、近所へ出かけていた丹羽は、まもなく帰宅して房次郎の身上と来意をきくや、労って家に上げ、泊めた。…」
こちらの方は、乗った列車まで書かれていませんでした。復刻版の時刻表を見ているので、数年おきにしか時刻表がありません。何処かで明治36年秋頃の時刻表を見ることができたら調べておきます。
吉田耕三氏の「北大路魯山人伝」からです。
「… 明治三十六年の秋の夕暮の事、その頃の松消堂は京橋高代町三番地(現在京橋と桜橋の都電の停留所の中間で昭和通りを横切つて少し行つた所に新弾正橋がある。(写真参照)この橋を渡りきつた電車道の中央あたり(矢印)(明治四十年頃道路の拡張で店をば同じく京橋高代町六番地に移転した。)にあつた。総二階で二間間口、表は四枚の濡障子で、左右に開く真中の二枚に人々松清堂と屋号が墨書してあつた。その障子をあけて、手に風呂敷包みをさげ、羽織をちやんと着てひと通りの身成りをしながら、何処となく身すぽらしい感じのした大柄な青年が、おずおずとした態度で人つて来た時の事を、当時十才位であつた長女の清さんが今でもよく覚えている。
その青年は、けげんな面ざしで応待に出たかねさんに、「京都の二条から、こちらを尋ねるように云われて参りましたが、私は福田房次郎と申します。」と自己紹介をした。
彼は其の頃、鉄道の終着駅であつた新橋から、この京橋高代町まで人に聞き聞き歩いて来たと云つていた。…」
”高代町三番地”は上記二人と同じです。ただ、次に移転した”高代町六番地”を書いているのは吉田耕三氏だけです。後の二人は裏付けが取れなかったのだとおもわれえます。
★写真の正面、道路の上辺りが高代町三番地になります。先の首都高速道路の下にある橋は弾正橋です。明治時代の弾正橋はもっと左側にありました(明治40年の京橋区地図より抜粋)。大正時代に新しく馬塲先門からの道を通したため、新しい弾正橋を架設、今までの弾正橋を「元弾正橋」としていました(大正元年の京橋区地積図より抜粋)。このように新道路ができたため、高代町三番地が無くなってしまっています。高代町六番地は写真左端の道を80m程進んだ左側にあります(下記の地図参照)。
弾正橋は明治11年(1878)11月に京橋区の楓川に、アメリカ人技師スクワイヤー・ウイップルの発明した形式を元に工部省赤羽分局により製作、架橋された橋です。当時は橋幅は9.1m(5間)あったと記録に残っています。架設経費は4058円。付近に島田弾正屋敷があったため、弾正橋と称されたそうです。当時、馬場先門から本所や深川を結ぶ主要路であったので、文明開化のシンボル的存在の鉄橋でした。大正2年(1912)の市区改正事業により、北側に新しく弾正橋が架橋されたため、「元弾正橋」と改称され、さらに大正12年(1923)の関東大震災後の震災復興計画によって廃橋となりましたが、その由緒を惜しんで門前仲町の富岡八幡宮の裏手に移設されています。移設当時は橋下は八幡堀という河川でしたが、後に埋め立てられ、現在のような人道陸橋となっています。(ウイキペディア参照)
魯山人の銀座・日本橋地図
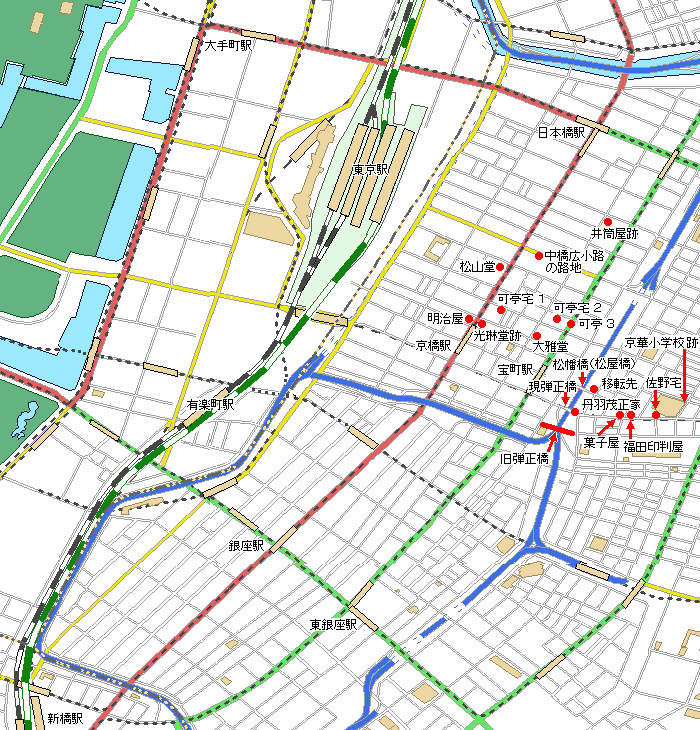
<四条隆平男爵邸>
魯山人(房次郎)は実母が働いていると聞いた、千駄ヶ谷の四条隆平男爵邸に向かいます。四条隆平男爵は明治初期には本所区南二葉町5番地(大名の屋敷跡?)、その後、麹町区下二番町46番地、豊島郡千駄ヶ谷字内藤反甫315と移っています。魯山人(房次郎)が訪ねた時は豊島郡千駄ヶ谷の頃のようです。
山田和氏の「知られざる魯山人」からです。
「…屋敷は現在の千駄ヶ谷駅構内にかかる広大な敷地の中に建っていた。その立派な佇まいを見て彼は気おくれした。しかし意を決して門をくぐった。以下はそのときの魯山人の回想である。
「『四条家に母をたづねた時、母は四谷まで使いに出かけて留守だつたが、お嬢さんの四条駒子さん (当時二十歳)が会つてくれて、母が帰ってくるまで待つていたらと云つてくれた。』
やがて母が使いから戻つて対面したのだが、この時、彼(自分)を見ても少しも嬉しさとか懐かしさとか云った表情を顔に表はさず、むしろ実に冷たい態度だつた。つんとして、何しに来たと言はんばかりのこわ面で、僕はおそろしささえ感じた程だつた。母は黙って外に出て行き、やがて縞の着物 と、下着の上下を買つて来たが、それが一目で古衣だつたので、僕は失望すると同時に癩にさはつた ことを今でも覚えている。母は、兎も角お帰りなさいと言つた」(前掲伝記、同号同文。カッコ内とルビは筆者)」
千駄ヶ谷駅は明治37年(1904)8月、 甲武鉄道の駅として開業していますので、魯山人(房次郎)が訪ねた頃は駅はありませんでした。お茶の水−新宿間が開通したのは明治37年(1904)12月です。
白崎秀雄氏の「北大路魯山人」からです。
「… 明治三十年代の初めから、四条邸は現在の国電千駄ヶ谷駅の東北の角あたりの地点にあった。当時の地名は、東京府下豊多摩郡千駄谷村字千駄谷。周囲は、北へ数丁の四谷や内藤新宿まで、人家は田畑の中に疎らにしかない。
駒子が二十二歳で六月に長女を生んだ年、つまり明治三十六年(一九〇三)晩秋某日の午わずかすぎのこと。下男が彼女に、なんでもまだ逢ったことはないが、御当家に奉公中の北大路トメの息子で福田房次郎という者だと、若い男が訪ねて来ました、と取次いだ。
おりから、トメは麹町へ使いに出て留守だった。
四条家では、十三年前に男爵夫人が亡くなったが後妻を納れず、前の年に婿養子を迎えた駒子が、おのずから主婦のような形になっていた。…」
”東京府下豊多摩郡千駄谷村字千駄谷”という住所は、華族名鑑(明治35年10月)に記載の”豊島郡千駄ヶ谷字内藤反甫315”と合いません。正確な地番は法務局で調べる必用がありそうです。
高代町三番地から千駄ヶ谷までは、日比谷から三宅坂、永田町、四谷経由で千駄ヶ谷まで6.8Kmの距離です。当然、歩いたとおもいます。
★写真、正面の白いビルから奥一帯が”豊島郡千駄ヶ谷字内藤反甫315”となります。当時の地図を掲載しておきます。千駄ヶ谷駅前には徳川家達邸が広大な敷地を占めていました。
魯山人(房次郎)は実母が働いていると聞いた、千駄ヶ谷の四条隆平男爵邸に向かいます。四条隆平男爵は明治初期には本所区南二葉町5番地(大名の屋敷跡?)、その後、麹町区下二番町46番地、豊島郡千駄ヶ谷字内藤反甫315と移っています。魯山人(房次郎)が訪ねた時は豊島郡千駄ヶ谷の頃のようです。
山田和氏の「知られざる魯山人」からです。
「…屋敷は現在の千駄ヶ谷駅構内にかかる広大な敷地の中に建っていた。その立派な佇まいを見て彼は気おくれした。しかし意を決して門をくぐった。以下はそのときの魯山人の回想である。
「『四条家に母をたづねた時、母は四谷まで使いに出かけて留守だつたが、お嬢さんの四条駒子さん (当時二十歳)が会つてくれて、母が帰ってくるまで待つていたらと云つてくれた。』
やがて母が使いから戻つて対面したのだが、この時、彼(自分)を見ても少しも嬉しさとか懐かしさとか云った表情を顔に表はさず、むしろ実に冷たい態度だつた。つんとして、何しに来たと言はんばかりのこわ面で、僕はおそろしささえ感じた程だつた。母は黙って外に出て行き、やがて縞の着物 と、下着の上下を買つて来たが、それが一目で古衣だつたので、僕は失望すると同時に癩にさはつた ことを今でも覚えている。母は、兎も角お帰りなさいと言つた」(前掲伝記、同号同文。カッコ内とルビは筆者)」
千駄ヶ谷駅は明治37年(1904)8月、 甲武鉄道の駅として開業していますので、魯山人(房次郎)が訪ねた頃は駅はありませんでした。お茶の水−新宿間が開通したのは明治37年(1904)12月です。
白崎秀雄氏の「北大路魯山人」からです。
「… 明治三十年代の初めから、四条邸は現在の国電千駄ヶ谷駅の東北の角あたりの地点にあった。当時の地名は、東京府下豊多摩郡千駄谷村字千駄谷。周囲は、北へ数丁の四谷や内藤新宿まで、人家は田畑の中に疎らにしかない。
駒子が二十二歳で六月に長女を生んだ年、つまり明治三十六年(一九〇三)晩秋某日の午わずかすぎのこと。下男が彼女に、なんでもまだ逢ったことはないが、御当家に奉公中の北大路トメの息子で福田房次郎という者だと、若い男が訪ねて来ました、と取次いだ。
おりから、トメは麹町へ使いに出て留守だった。
四条家では、十三年前に男爵夫人が亡くなったが後妻を納れず、前の年に婿養子を迎えた駒子が、おのずから主婦のような形になっていた。…」
”東京府下豊多摩郡千駄谷村字千駄谷”という住所は、華族名鑑(明治35年10月)に記載の”豊島郡千駄ヶ谷字内藤反甫315”と合いません。正確な地番は法務局で調べる必用がありそうです。
高代町三番地から千駄ヶ谷までは、日比谷から三宅坂、永田町、四谷経由で千駄ヶ谷まで6.8Kmの距離です。当然、歩いたとおもいます。
★写真、正面の白いビルから奥一帯が”豊島郡千駄ヶ谷字内藤反甫315”となります。当時の地図を掲載しておきます。千駄ヶ谷駅前には徳川家達邸が広大な敷地を占めていました。
<赤坂区青山南町六丁目百八番地 北大路清操宅>
魯山人(房次郎)の実母と兄は明治33年には東京に出ていたようです。京都には居たたまれなくなったのだとおもわれます。魯山人が生まれた明治16年から明治30年代までの実母の行動はよく分かっていないようです。この辺りは、京都編で詳しく書きたいとおもいます。
山田和氏の「知られざる魯山人」からです。
「… 房次郎は、この日から丹羽家に居候することになった。むろんその日のうちに房次郎は、自分の異父兄弟である西池氏雅が大阪で国鉄の切符切りをしていてときどき東京まで遊びに来ることや、兄の北大路清晃が都内深川の鉄工所で工員として働いていること、実母の登女がここからさほど遠くない千駄ヶ谷の四条隆平男爵邸に住み込んでいることを聞かされたはずである。」
山田和氏の「知られざる魯山人」には魯山人の兄、北大路清操の住まいについては書かれていないようです。まだ最後まで熟読していないので確信はありません。
白崎秀雄氏の「北大路魯山人」からです。
「… 北大路清操の長男で家督を継いでいた清晃は、明治三十三年一月京都府愛宕郡上賀茂村百四十一番戸より、東京市赤坂区青山南町六丁目百八番地へ転籍している。徴兵検査の結果兵役を免れ、トメの勧めによって上京したものであろう。房次郎より三歳上で、この転籍の年二十一である。
前記の吉田伝では、青山南町には清晃が借家して住み、トメも一時はともに住んだことがあるようだという。また、清晃は相当な蕩児で、遊廓に泊って勘定が足らず”附け馬”を引いて丹羽方へ帰ったりすることがあった、とものべられている。果してそこまで遊蕩する力があったであろうか。 トメが、清晃と一番地違いに在籍した記録はあるが、居住とは一致しないかも知れない。清晃は深川で職工をしていた。…」
ここに魯山人の兄、北大路清操の住まいが書かれていました。深川で職工をしていて、住まいは青山南町というのは少し不可解です。遠すぎます。青山南町の家が自宅なら理解できるのですが、自宅を購入するほどのお金は持っていなかったとおもいます。
★写真は青山の根津美術館前の交差点から東側を撮影したものです。赤坂区青山南町六丁目百八番地は写真の一帯全てです。とても広い範囲の地番です。元々は広いお屋敷で、それを区画整理して家作にしたか、もしくは、分譲地にしたとおもわれます。ここから深川は遠すぎます。
魯山人(房次郎)の実母と兄は明治33年には東京に出ていたようです。京都には居たたまれなくなったのだとおもわれます。魯山人が生まれた明治16年から明治30年代までの実母の行動はよく分かっていないようです。この辺りは、京都編で詳しく書きたいとおもいます。
山田和氏の「知られざる魯山人」からです。
「… 房次郎は、この日から丹羽家に居候することになった。むろんその日のうちに房次郎は、自分の異父兄弟である西池氏雅が大阪で国鉄の切符切りをしていてときどき東京まで遊びに来ることや、兄の北大路清晃が都内深川の鉄工所で工員として働いていること、実母の登女がここからさほど遠くない千駄ヶ谷の四条隆平男爵邸に住み込んでいることを聞かされたはずである。」
山田和氏の「知られざる魯山人」には魯山人の兄、北大路清操の住まいについては書かれていないようです。まだ最後まで熟読していないので確信はありません。
白崎秀雄氏の「北大路魯山人」からです。
「… 北大路清操の長男で家督を継いでいた清晃は、明治三十三年一月京都府愛宕郡上賀茂村百四十一番戸より、東京市赤坂区青山南町六丁目百八番地へ転籍している。徴兵検査の結果兵役を免れ、トメの勧めによって上京したものであろう。房次郎より三歳上で、この転籍の年二十一である。
前記の吉田伝では、青山南町には清晃が借家して住み、トメも一時はともに住んだことがあるようだという。また、清晃は相当な蕩児で、遊廓に泊って勘定が足らず”附け馬”を引いて丹羽方へ帰ったりすることがあった、とものべられている。果してそこまで遊蕩する力があったであろうか。 トメが、清晃と一番地違いに在籍した記録はあるが、居住とは一致しないかも知れない。清晃は深川で職工をしていた。…」
ここに魯山人の兄、北大路清操の住まいが書かれていました。深川で職工をしていて、住まいは青山南町というのは少し不可解です。遠すぎます。青山南町の家が自宅なら理解できるのですが、自宅を購入するほどのお金は持っていなかったとおもいます。
★写真は青山の根津美術館前の交差点から東側を撮影したものです。赤坂区青山南町六丁目百八番地は写真の一帯全てです。とても広い範囲の地番です。元々は広いお屋敷で、それを区画整理して家作にしたか、もしくは、分譲地にしたとおもわれます。ここから深川は遠すぎます。
魯山人の青山・千駄ヶ谷地図(村上春樹の地図を流用)
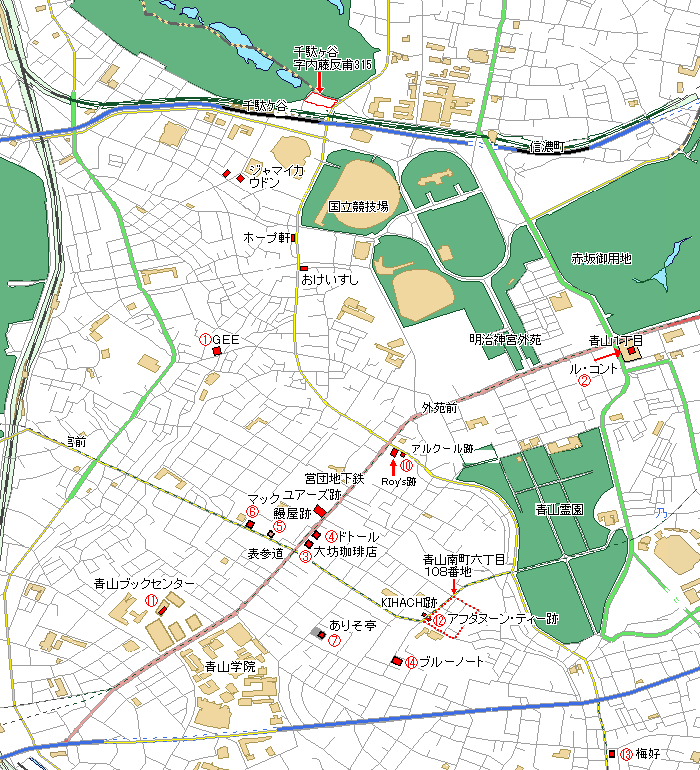
<巌谷一六、日下部鳴鶴>
魯山人(房次郎)は京都時代から自信があったのは書道だったため、書家としての将来を託し、当時、国内で最も有名だった巌谷一六、日下部鳴鶴を訪ねます。四条隆平男爵の紹介状を持っての訪問でした。
山田和氏の「知られざる魯山人」からです。
「… 房次郎が師事することを望んだ日下部鳴鶴(天保九年〜大正十一年・一八三人〜一九二二年)と巌谷一六(天保五年〜明治三十八年・一八三四〜一九〇五年)は当代きっての書家だった。日下部は清朝末の書家・楊守敬(一八三九〜一九一五年。明治十三年から四年間滞日)との出会いによって書風を一変させ、江戸以降衰微しつつあった御家流を中心とする日本の書道界に新風を巻き起こし、「近代随一の書家」と仰がれていたし、巌谷一六もまた楊守敬の影響下に一六風と呼ばれる独自の書風を完成させて書道界を席巻していた。二人は当時の日本書道界の二大領袖だっただけでなく、明治大正書道史においては中興の祖の感もあり、とくに鳴鶴などは支那で「東海の書聖」と称されていた。しかもこの二人は、ともに房次郎の出生地・京都や隣の近江の育ちだったから、その意味でも彼にとって特別憧憬の的だったのである。
房次郎が四条男爵の紹介状を携えて、日下部鳴鶴と巌谷一六を訪れたのはまもなくのことだったが、彼は二、三度通っただけでやめてしまった。」
お二人とも偉い先生なので、いくら紹介状があるとは言え、二十歳ぐらいの若造は相手にしないとおもいます。
白崎秀雄氏の「北大路魯山人」からです。
「… 房次郎は、まもなく四条男爵の添書を懐中に、巌谷一六をその麹町区番町の邸に訪ねた。
幕末以来沈滞したわが書道界を革新し、六朝風の書と書の学問的研究法をもたらしたのは、清人楊守敬の来日であった。楊に学んでそれを祖述し、日本の主流となったのが、巌谷一六・日下部鳴鶴・松田雪洞の三者とされる。
一六は名は修、もと近江水口藩士で、後に貴族院議員に列せられ、しきりに各地を遊歴し、需に応じて揮毫した。
はじめて訪ねたとき、房次郎は書生に、「先生は今御書見中だから」といって帰され、数日置いて再度行くと、「お客様と御歓談中だ」といって、またもや取次いでもらえなかった。
房次郎は三度目のとき、かなりの間、門の傍らで玄関の様子をうかがっていた。
やがて、客を送って一六が玄関まで現れ、挨拶を交した。客が供待ちをしていた人力車に乗り、車が動き出す。
そのとき、房次郎は小走りに玄関へ駈け込むや、書生の制止もきかず、上り框に手をつき、「四条男爵様からの添書をもって参上いたしました、大先生に御引見をおねがい申し上げます」
と、添書をちょうど一六の膝のあたりへ、捧げるようにした。
この年、古稀に当っていた一六は、しばし唖然とした。封書の宛名は、たしかに四条男爵の手跡である。彼はただちに披いてみて、房次郎を起たせ、奥へ伴った。…」
白崎秀雄氏の方が話しとしては面白いですね、本当かどうかは別にしてですが!
★写真は巌谷一六の住んでいた当時の”麹町区元園町1-27”附近です。27番地は道の両側、100m位先までです。右側は麹町小学校なので、推定ですが、左側ではなかったかなとおもっています。この地番は「現今名家書画鑑 明35年」からです。日下部鳴鶴の住まいは”麹町区中六番町17”となります。
続きます!
魯山人(房次郎)は京都時代から自信があったのは書道だったため、書家としての将来を託し、当時、国内で最も有名だった巌谷一六、日下部鳴鶴を訪ねます。四条隆平男爵の紹介状を持っての訪問でした。
山田和氏の「知られざる魯山人」からです。
「… 房次郎が師事することを望んだ日下部鳴鶴(天保九年〜大正十一年・一八三人〜一九二二年)と巌谷一六(天保五年〜明治三十八年・一八三四〜一九〇五年)は当代きっての書家だった。日下部は清朝末の書家・楊守敬(一八三九〜一九一五年。明治十三年から四年間滞日)との出会いによって書風を一変させ、江戸以降衰微しつつあった御家流を中心とする日本の書道界に新風を巻き起こし、「近代随一の書家」と仰がれていたし、巌谷一六もまた楊守敬の影響下に一六風と呼ばれる独自の書風を完成させて書道界を席巻していた。二人は当時の日本書道界の二大領袖だっただけでなく、明治大正書道史においては中興の祖の感もあり、とくに鳴鶴などは支那で「東海の書聖」と称されていた。しかもこの二人は、ともに房次郎の出生地・京都や隣の近江の育ちだったから、その意味でも彼にとって特別憧憬の的だったのである。
房次郎が四条男爵の紹介状を携えて、日下部鳴鶴と巌谷一六を訪れたのはまもなくのことだったが、彼は二、三度通っただけでやめてしまった。」
お二人とも偉い先生なので、いくら紹介状があるとは言え、二十歳ぐらいの若造は相手にしないとおもいます。
白崎秀雄氏の「北大路魯山人」からです。
「… 房次郎は、まもなく四条男爵の添書を懐中に、巌谷一六をその麹町区番町の邸に訪ねた。
幕末以来沈滞したわが書道界を革新し、六朝風の書と書の学問的研究法をもたらしたのは、清人楊守敬の来日であった。楊に学んでそれを祖述し、日本の主流となったのが、巌谷一六・日下部鳴鶴・松田雪洞の三者とされる。
一六は名は修、もと近江水口藩士で、後に貴族院議員に列せられ、しきりに各地を遊歴し、需に応じて揮毫した。
はじめて訪ねたとき、房次郎は書生に、「先生は今御書見中だから」といって帰され、数日置いて再度行くと、「お客様と御歓談中だ」といって、またもや取次いでもらえなかった。
房次郎は三度目のとき、かなりの間、門の傍らで玄関の様子をうかがっていた。
やがて、客を送って一六が玄関まで現れ、挨拶を交した。客が供待ちをしていた人力車に乗り、車が動き出す。
そのとき、房次郎は小走りに玄関へ駈け込むや、書生の制止もきかず、上り框に手をつき、「四条男爵様からの添書をもって参上いたしました、大先生に御引見をおねがい申し上げます」
と、添書をちょうど一六の膝のあたりへ、捧げるようにした。
この年、古稀に当っていた一六は、しばし唖然とした。封書の宛名は、たしかに四条男爵の手跡である。彼はただちに披いてみて、房次郎を起たせ、奥へ伴った。…」
白崎秀雄氏の方が話しとしては面白いですね、本当かどうかは別にしてですが!
★写真は巌谷一六の住んでいた当時の”麹町区元園町1-27”附近です。27番地は道の両側、100m位先までです。右側は麹町小学校なので、推定ですが、左側ではなかったかなとおもっています。この地番は「現今名家書画鑑 明35年」からです。日下部鳴鶴の住まいは”麹町区中六番町17”となります。
続きます!
魯山人の番町・麹町地図(永井荷風の地図を流用)
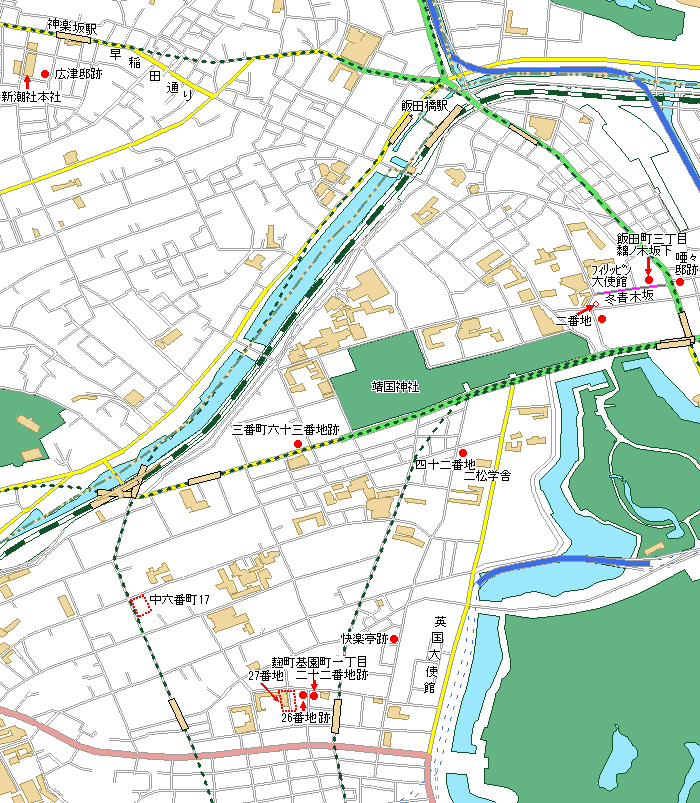
北大路魯山人年表
| 和 暦 | 西暦 | 年 表 | 年齢 | 北大路魯山人の足跡 |
|
明治16年
|
1883 | 日本銀行開業 鹿鳴館落成 岩倉具視死去 |
0 | 3月23日 北大路魯山人は上賀茂神社の社家 北大路清操の次男として京都府愛宕郡上賀茂村第百六十六番戸で生まれます。 (本名:房次郎) |
| 明治36年 | 1903 | 小等学校の教科書国定化 | 20 | 秋 上京 京橋高代町3番地 丹羽茂正宅に間借 実母の登女が住み込んでいる四条男爵邸を訪ねる 日下部鳴鶴と巌谷一六を訪問 |