<「武蔵野夫人」>
大岡昇平は昭和23年1月、疎開先の兵庫県明石市大久保を離れて、上京します。上京先は成城学園で同級であった小金井の富永次郎宅でした(東京二十三区以外の郡部には転入可能となった)。富永次郎は富永太郎の弟です。その当時のことが昭和25年正月から「群像」に連載を始めた「武蔵野夫人」に書かれています。
「… 土地の人はなぜそこが「はけ」と呼ばれるかを知らない。「はけ」の荻野長作といえば、この辺の農家に多い荻野姓の中でも、一段と古い家とされているが、人々は単にその長作の家のある高みが「はけ」なのだと思っている。
中央線国分寺駅と小金井駅の中間、線路から平坦な畠中の道を二丁南へ行くと、道は突然下りとなる。「野川」と呼ばれる一つの小川の流域がそこに開けているが、流れの細い割に斜面の高いのは、これがかつて古い地質時代に関東山地から流出して、北は入間川、荒川、東は東京湾、南は現在の多摩川で限られた広い武蔵野台地を沈澱させた古代多摩川が、次第に西南に移って行った跡で、斜面はその途中作った最も古い段丘の一つだからである。
狭い水田を発達させた野川の対岸はまたゆるやかに高まって楯状の台地となり、松や桑や工場を乗せて府中まで来ると、第二の段丘となって現在の多摩川の流域に下りている。
野川はつまり古代多摩川が武蔵野におき忘れた数多い名残川の一つである。段丘は三鷹、深大寺、調布を経て喜多見の上で多摩の流域に出、それから下は直接神奈川の多摩丘陵と対しっつ腕々六郷に到っている。…」。
大岡昇平らしい書き出しです。丁寧に野川付近を説明しています。この野川はもう少し下流には野川公園があり、村上春樹の「1973年のピンボール」でゴルフ場(当時はICUのゴルフ場だった)として登場しています。
★左上の写真は昭和28年出版の新潮文庫版「武蔵野夫人」です(写真は平成17年発行の17版)。昭和26年の講談社版「武蔵野夫人」の写真も掲載しておきます。

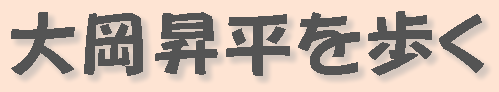
●大岡昇平の東京を歩く -5-
初版2008年2月2日 <V01L01>
今週は「大岡昇平を歩く」の六回目を掲載します。大岡昇平は昭和23年1月、疎開先の兵庫県明石市大久保から上京します。東京都小金井市の富永家次男、富永次郎(富永太郎の弟)宅に寄寓します。
< はけの小道>
はけの小道>
「武蔵野夫人」で登場する「はけの小道」です。小説ではこの前には「道子」の家があるのですが、当時は中村研一画伯の家がありました(小説と何の関係もないそうです)。現在は「はけの森美術館」となっています。
「…古代武蔵野が鬱蒼たる原生林に蔽われていたころ、また降っては広漠たる荒野と化して、渇いた旅人が斃死したころも、斜面二倍はこの豊かな湧き水のために、常に人に住まわれていた。長作の先祖が初めここに住みついたのも、明らかにこの水のためであって、「はけの荻野」と呼ばれたのもそのためであろうが、今は鑿井技術が発達して到るところ井戸があり、湧水の必要は薄れたから、現在長作の家が建っている日当りのいい高みが「はけ」だと人は思っているわけである。
もっとも人がこの湧水を忘れたのは、あながち生活の原因からばかりではない。長作の家で使っている水溜りから西へ十間ばかり、つまりこの窪地の正面を蔽う広さの全部が、今は生垣によって占められ、酒落た冠木門の中には梅、木犀、泰山木等の花樹が、四季とりどりの花を咲かせる。つまりこれは近ごろとみにこの辺に増えた都会人の住宅の一つであって、道行く人はこの垣の中に、かつてこの土地の繁栄の条件であった湧水があろうなどとは思わない。…」。
「はけの小道」の小川には今も水が流れています。湧き水から流れているのか、人工的に流しているのかはわかりませんでした。この「はけ」の意味は、小金井市のホームページを参照すると、「「はけ」とは、国分寺崖線(がいせん)と呼ばれる段丘崖のことです。古多摩川の浸食によって、武蔵野にできた台地の武蔵野段丘と、その一段低い立川段丘の間の崖をさし、西は立川市の北東付近から、東は世田谷区の野毛町付近までのびています。」、だそうです。下記の写真を見てもらった方が分かります。
★左上の写真は小金井市中町一丁目の「はけの小道」です。「 はけの森美術館」が道路を挟んだ向かい側にあります。
はけの森美術館」が道路を挟んだ向かい側にあります。
「武蔵野夫人」で登場する「はけの小道」です。小説ではこの前には「道子」の家があるのですが、当時は中村研一画伯の家がありました(小説と何の関係もないそうです)。現在は「はけの森美術館」となっています。
「…古代武蔵野が鬱蒼たる原生林に蔽われていたころ、また降っては広漠たる荒野と化して、渇いた旅人が斃死したころも、斜面二倍はこの豊かな湧き水のために、常に人に住まわれていた。長作の先祖が初めここに住みついたのも、明らかにこの水のためであって、「はけの荻野」と呼ばれたのもそのためであろうが、今は鑿井技術が発達して到るところ井戸があり、湧水の必要は薄れたから、現在長作の家が建っている日当りのいい高みが「はけ」だと人は思っているわけである。
もっとも人がこの湧水を忘れたのは、あながち生活の原因からばかりではない。長作の家で使っている水溜りから西へ十間ばかり、つまりこの窪地の正面を蔽う広さの全部が、今は生垣によって占められ、酒落た冠木門の中には梅、木犀、泰山木等の花樹が、四季とりどりの花を咲かせる。つまりこれは近ごろとみにこの辺に増えた都会人の住宅の一つであって、道行く人はこの垣の中に、かつてこの土地の繁栄の条件であった湧水があろうなどとは思わない。…」。
「はけの小道」の小川には今も水が流れています。湧き水から流れているのか、人工的に流しているのかはわかりませんでした。この「はけ」の意味は、小金井市のホームページを参照すると、「「はけ」とは、国分寺崖線(がいせん)と呼ばれる段丘崖のことです。古多摩川の浸食によって、武蔵野にできた台地の武蔵野段丘と、その一段低い立川段丘の間の崖をさし、西は立川市の北東付近から、東は世田谷区の野毛町付近までのびています。」、だそうです。下記の写真を見てもらった方が分かります。
★左上の写真は小金井市中町一丁目の「はけの小道」です。「
< 富永次郎邸>
富永次郎邸>
大岡昇平が昭和23年に上京し、寄寓したのが成城学園で同級たった富永次郎でした。まだ戦後3年しか経っていませんから、家族で住む場所を探すのは大変だったと思います。富永次郎は富永太郎の弟です。富永家は渋谷の富ヶ谷に住居を構えていたのですが、小金井の土地は以前から買ってあったようで、父謙治の退職後の住まいとして考えていたようです(大正13年頃から家を建て始めて14年夏には転居予定だった)。
「…駅の附近に群れるパンパンとその客の間を素速く通り抜け、人気のない横丁を曲ると、古い武蔵野の道が現われた。低い陸稲の揃った間を黒い土が続いていた。その土の色は、恐らく彼が熱帯から帰って懐しく思った唯一のものであった。彼は人間に絶望していたが、自然は愛していた。兵士は自然に接することが多い職業である。
茶木垣に沿い、栗林を抜けて、彼がようやくその畠中の道に倦きたころ、「はけ」 の斜面を蔽う喬木の群が目に入るところまで来た。
それは彼の幼時から見馴れた木立であった。樫、杉、樺など、宮地老人の土地の背後を飾る樹々は淋しい少年であったころ、彼の最も懐しい映像であった。ここへ来ることだけが、そのころ彼の楽しみであったことを彼は思い出した。
「はけ」の下道から、斜面の上を通る道に跨がる宮地老人の土地は、老人の奇妙なべダンチスムによって、他の家のように門を駅に近い上道に持っていなかった。「ここはもともと南の多摩川の方から開けた土地だ。神社も寺もみな府中の方を向いているだろう。それが自然に従うというものだ」と彼はいっていた。上道には小さな木戸が開いているだけで、老人は勉を含めてあらゆる訪問客にそこから入るのを許さなかった。
行く手にその古ぼけた木戸が見えた時、勉はふとそこから入る気になった。木戸は掛け金が下りていたが、生垣の横から手を入れて容易にはずすことができた。木戸を押しながら、彼は不思議な喜びを感じた。彼はそれを単に子供らしいいたずらの喜びと思っていたが、こういう秘密な行動はやはり常に奇襲を強要されていた前線から彼の得た習慣だったかも知れない。「捕手から」これが彼に気に入ったのである。
木戸から入ったところはまだ三十坪ばかり平らになっていた。かつて宮地老人が長男のために家を予定していたところであるが、今は荒れるに任せて、杉や樫の間に、この辺で旺盛に育つ山吹が一面に咲き乱れ、下草を隠していた。…」。
南東2Kmに戦前日本一の航空機工場であった中島航空機武蔵野製作所(現在のICUと富士重工の所です)がありました。最盛期は5万人の従業員を抱えていましたので、米軍の空襲も激しく、終戦までに十数回爆撃されています。すぐ近くですが、直接の爆撃は受けなかったようです。
★左上の写真の道は上記に書かれている”はけの下道”です。右の坂道はムジナ坂です。正面の石垣の上が富永家でした。推定ですが、父謙治の死後、上部を富永次郎(次男)、下部を富永三郎(三男)で分けたのではないでしょうか。大岡昇平と富永太郎のつながりを探すと、「…大正十四年十二月(太郎の死後一ケ月である)に弟の次郎と成城学園で同級となり、以来富永家との交際が続いている。富ヶ谷一四五六番地の家とは一キロ半ぐらいの距離であるから、よく遊びに行った。一九四六年以来、私が太郎の遺稿を托され、その伝記を書くのに、十分な便宜を与えられているのはこのためである。…」。富永太郎の弟と「成城学園」で同級でした。戦後、大岡昇平が戦地から生きて帰って来たときに東京でやっかいになったのが富永次郎でした。
大岡昇平が昭和23年に上京し、寄寓したのが成城学園で同級たった富永次郎でした。まだ戦後3年しか経っていませんから、家族で住む場所を探すのは大変だったと思います。富永次郎は富永太郎の弟です。富永家は渋谷の富ヶ谷に住居を構えていたのですが、小金井の土地は以前から買ってあったようで、父謙治の退職後の住まいとして考えていたようです(大正13年頃から家を建て始めて14年夏には転居予定だった)。
「…駅の附近に群れるパンパンとその客の間を素速く通り抜け、人気のない横丁を曲ると、古い武蔵野の道が現われた。低い陸稲の揃った間を黒い土が続いていた。その土の色は、恐らく彼が熱帯から帰って懐しく思った唯一のものであった。彼は人間に絶望していたが、自然は愛していた。兵士は自然に接することが多い職業である。
茶木垣に沿い、栗林を抜けて、彼がようやくその畠中の道に倦きたころ、「はけ」 の斜面を蔽う喬木の群が目に入るところまで来た。
それは彼の幼時から見馴れた木立であった。樫、杉、樺など、宮地老人の土地の背後を飾る樹々は淋しい少年であったころ、彼の最も懐しい映像であった。ここへ来ることだけが、そのころ彼の楽しみであったことを彼は思い出した。
「はけ」の下道から、斜面の上を通る道に跨がる宮地老人の土地は、老人の奇妙なべダンチスムによって、他の家のように門を駅に近い上道に持っていなかった。「ここはもともと南の多摩川の方から開けた土地だ。神社も寺もみな府中の方を向いているだろう。それが自然に従うというものだ」と彼はいっていた。上道には小さな木戸が開いているだけで、老人は勉を含めてあらゆる訪問客にそこから入るのを許さなかった。
行く手にその古ぼけた木戸が見えた時、勉はふとそこから入る気になった。木戸は掛け金が下りていたが、生垣の横から手を入れて容易にはずすことができた。木戸を押しながら、彼は不思議な喜びを感じた。彼はそれを単に子供らしいいたずらの喜びと思っていたが、こういう秘密な行動はやはり常に奇襲を強要されていた前線から彼の得た習慣だったかも知れない。「捕手から」これが彼に気に入ったのである。
木戸から入ったところはまだ三十坪ばかり平らになっていた。かつて宮地老人が長男のために家を予定していたところであるが、今は荒れるに任せて、杉や樫の間に、この辺で旺盛に育つ山吹が一面に咲き乱れ、下草を隠していた。…」。
南東2Kmに戦前日本一の航空機工場であった中島航空機武蔵野製作所(現在のICUと富士重工の所です)がありました。最盛期は5万人の従業員を抱えていましたので、米軍の空襲も激しく、終戦までに十数回爆撃されています。すぐ近くですが、直接の爆撃は受けなかったようです。
★左上の写真の道は上記に書かれている”はけの下道”です。右の坂道はムジナ坂です。正面の石垣の上が富永家でした。推定ですが、父謙治の死後、上部を富永次郎(次男)、下部を富永三郎(三男)で分けたのではないでしょうか。大岡昇平と富永太郎のつながりを探すと、「…大正十四年十二月(太郎の死後一ケ月である)に弟の次郎と成城学園で同級となり、以来富永家との交際が続いている。富ヶ谷一四五六番地の家とは一キロ半ぐらいの距離であるから、よく遊びに行った。一九四六年以来、私が太郎の遺稿を托され、その伝記を書くのに、十分な便宜を与えられているのはこのためである。…」。富永太郎の弟と「成城学園」で同級でした。戦後、大岡昇平が戦地から生きて帰って来たときに東京でやっかいになったのが富永次郎でした。
< 富永三郎邸>
富永三郎邸>
富永家の三男が富永三郎です。「武蔵野夫人」の中に富永家と思われる記述があります。
「…大正の末停年で官を退くまでに、すでに相当の産を作っていたが、退職後も縁故をたどって静岡県のある私鉄の重役に収まり、二年の間にさらに産を殖やすと、あらかじめ別荘として建ててあった「はけ」の家に引っ込んでしまった。 こうして彼の生涯はある程度の幸福に達していた。ただ子供運はよくなかった。同じ静岡県の士族からもらった妻の民子との間に、二男一女が生れたが、男はいずれも早道し、末娘の道子だけしか残らなかった。……
… 彼女はそのかわり早くから八歳年上の長兄の俊一に熱中した。俊一はなぜか父親の衒学的シニスムに反抗し、若くからフランスの近代文学、ことにランボオに心酔して坊ちゃん風の漂浪の生活を送った。彼は丈が高く、小さな卵形の顔が長い首の上にちょこんと載って美しかった。彼の言葉は彼女にとって金科玉条で、自分の生活の細目に到るまで何でも彼の指図を仰ぎ、盆幕に方々からもらう小遣いもみんな彼に送ってしまった。 その兄が乱暴な生活のため肺を病んで二十四歳で死ぬと、今度は次兄の慶次が熱中の対象になった。彼は作曲家希望で少年の時からピアノを弾いた。彼女も一緒に習わされたが、彼女がさっぱり進歩しないのに反して、慶次が易々とむずかしいオーケストレーシオンを鍵盤の上で組み立てて行くのを、彼女はほとんど渇仰の眼で眺めた。その兄もやがて長兄と同じ二十四歳の若さで、恐らく長兄から感染した肺結核で死んで行った。彼女だけ感染の徴候を示さないのはちょっと不思議であったが、父に「それはお前の顎のせいだよ」といわれると、たしかにそうだと思われて来た。死んだ長兄に「道子の顔の造作はみんな優しいが、顎だけちょっと野蛮だな」といわれたことがあったからである。…」。
富永次郎の父謙治は鉄道省管史から青梅鉄道株式会社の専務になり、大正12年10月退職しています。富永家は3男、2女なので上記とは少し違います。亡くなったのは長男の太郎、だけで、大正14年に肺結核でなくなっています。
★右上の写真は富永三郎家の玄関です。表札は富永三郎となっていました。
富永家の三男が富永三郎です。「武蔵野夫人」の中に富永家と思われる記述があります。
「…大正の末停年で官を退くまでに、すでに相当の産を作っていたが、退職後も縁故をたどって静岡県のある私鉄の重役に収まり、二年の間にさらに産を殖やすと、あらかじめ別荘として建ててあった「はけ」の家に引っ込んでしまった。 こうして彼の生涯はある程度の幸福に達していた。ただ子供運はよくなかった。同じ静岡県の士族からもらった妻の民子との間に、二男一女が生れたが、男はいずれも早道し、末娘の道子だけしか残らなかった。……
… 彼女はそのかわり早くから八歳年上の長兄の俊一に熱中した。俊一はなぜか父親の衒学的シニスムに反抗し、若くからフランスの近代文学、ことにランボオに心酔して坊ちゃん風の漂浪の生活を送った。彼は丈が高く、小さな卵形の顔が長い首の上にちょこんと載って美しかった。彼の言葉は彼女にとって金科玉条で、自分の生活の細目に到るまで何でも彼の指図を仰ぎ、盆幕に方々からもらう小遣いもみんな彼に送ってしまった。 その兄が乱暴な生活のため肺を病んで二十四歳で死ぬと、今度は次兄の慶次が熱中の対象になった。彼は作曲家希望で少年の時からピアノを弾いた。彼女も一緒に習わされたが、彼女がさっぱり進歩しないのに反して、慶次が易々とむずかしいオーケストレーシオンを鍵盤の上で組み立てて行くのを、彼女はほとんど渇仰の眼で眺めた。その兄もやがて長兄と同じ二十四歳の若さで、恐らく長兄から感染した肺結核で死んで行った。彼女だけ感染の徴候を示さないのはちょっと不思議であったが、父に「それはお前の顎のせいだよ」といわれると、たしかにそうだと思われて来た。死んだ長兄に「道子の顔の造作はみんな優しいが、顎だけちょっと野蛮だな」といわれたことがあったからである。…」。
富永次郎の父謙治は鉄道省管史から青梅鉄道株式会社の専務になり、大正12年10月退職しています。富永家は3男、2女なので上記とは少し違います。亡くなったのは長男の太郎、だけで、大正14年に肺結核でなくなっています。
★右上の写真は富永三郎家の玄関です。表札は富永三郎となっていました。
【大岡昇平】
明治42年(1909)東京の生まれ。旧制中学のとき、小林秀雄、中原中也らを知る。京大仏文で学びスタンダールに傾倒。戦争末期に召集を受け、フィリピンに送られる。戦後、この間の体験を「伴虜記」「野火」などに書き継いだ。ほかに「花影」、恋愛小説に新風を送った「武蔵野夫人」など。たえず同時代に向けて発言するかたわら、「天誅組」「将門記」など歴史小説に一境地をひらいた。(筑摩書房 ちくま日本文学全集より)
明治42年(1909)東京の生まれ。旧制中学のとき、小林秀雄、中原中也らを知る。京大仏文で学びスタンダールに傾倒。戦争末期に召集を受け、フィリピンに送られる。戦後、この間の体験を「伴虜記」「野火」などに書き継いだ。ほかに「花影」、恋愛小説に新風を送った「武蔵野夫人」など。たえず同時代に向けて発言するかたわら、「天誅組」「将門記」など歴史小説に一境地をひらいた。(筑摩書房 ちくま日本文学全集より)
大岡昇平 小金井市 -1-
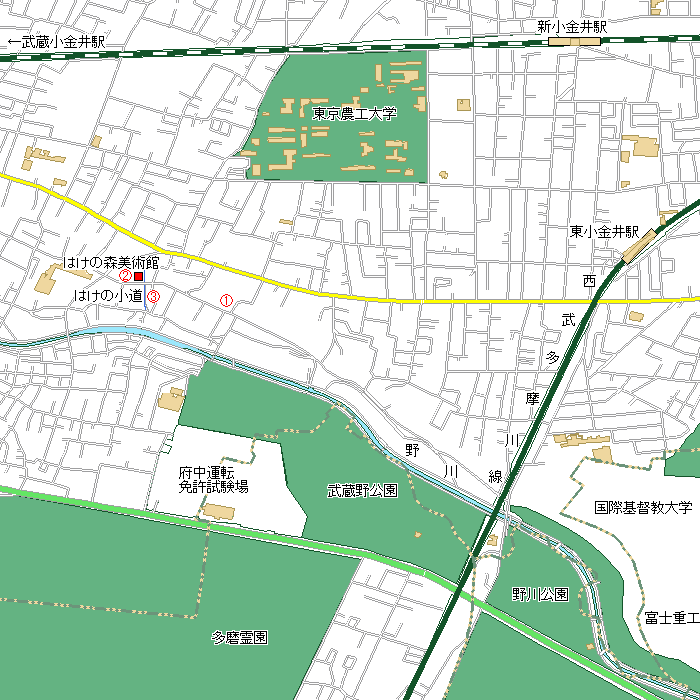
大岡昇平の年表
| 和 暦 | 西暦 | 年 表 | 年齢 | 大岡昇平の足跡 |
| 明治42年 | 1909 | 伊藤博文ハルビン駅で暗殺 | - | 父貞三郎、母つるの長男として牛込区新小川町で生まれる |
| 明治45年 | 1912 | 中華民国成立 タイタニック号沈没 |
3 | 春 麻布区笄町に転居 |
| 大正元年〜 2年 |
1912〜 13 |
島崎藤村、フランスへ出発 |
4 | 下渋谷字伊藤前に転居 宝泉寺付近に転居 下渋谷521番地に転居 |
| 大正3年 | 1914 | 第一次世界大戦始まる | 5 | 下渋谷543番地に転居 |
| 大正4年 | 1915 | 対華21ヶ条、排日運動 | 6 | 中渋谷字並木前180番地に転居 4月 渋谷第一尋常高等小学校入学 |
| 大正6年 | 1917 | ロシア革命 | 8 | 中渋谷896番地に転居 |
| 昭和13年 | 1938 | 関門海底トンネルが貫通 岡田嘉子ソ連に亡命 「モダン・タイムス」封切 |
29 | 10月 神戸の帝国酸素株式会社に入社(翻訳係) |
| 昭和14年 | 1939 | ノモンハン事件 ドイツ軍ポーランド進撃 |
30 | 10月 社内恋愛で上村春江と結婚 |
| 昭和16年 | 1941 | 真珠湾攻撃、太平洋戦争 | 32 | 2月 長女誕生 |
| 昭和18年 | 1943 | ガダルカナル島撤退 | 34 | 6月 帝国酸素を退社 7月 長男誕生 11月 川崎重工業に入社 |
| 昭和19年 | 1944 | マリアナ海戦敗北 東条内閣総辞職 レイテ沖海戦 神風特攻隊出撃 |
35 | 2月 川崎重工東京事務所に転勤 3月 教育召集を受ける 6月 臨時召集となる 7月 フィリッピンに出征 |
| 昭和20年 | 1945 | ソ連参戦 ポツダム宣言受諾 |
36 | 1月 ミンドロ島で米軍の捕虜となる 12月 復員、妻の疎開先の明石市大久保に住む 12月 和歌山の姉と大叔母を訪ねる |
| 昭和23年 | 1948 | 太宰治自殺 | 39 | 1月 上京 東京都小金井市中町1丁目の富永次郎宅に寄寓 12月 鎌倉市雪ノ下の小林秀雄宅離れに転居 |



