|
今週は”岡本綺堂の東京を歩く”の第二弾として江戸府内の「時の鐘」を巡ってみたいと思います。江戸初期の頃は江戸城で太鼓を昼夜十二刻を打って知らせていたようです。登城時間等の公の時間を知るには、すべてこの太鼓によらなければならなかったのです。明六つ(日の出)の太鼓が鳴ると江戸城の見附の門を開け、夕六つ(日の入り)の太鼓が鳴ると見附の門を閉めていたのです。この江戸城内の太鼓だけでは江戸府内全てで聞こえるはずがなく、その代わりに時を知らせる鐘を各地においたわけです。江戸時代で時の話といえば、やっぱりこれですね!『江戸っ子が屋台の蕎麦屋で蕎麦を食べた後、「おいいくらだい、16文か、銭は細けぇけどいいかい、手を出しねえ」「それでは、ひい、ふう、みい、……なな、やー」と数えたところで「今、何刻だ」「九つで」「十、十一、十二……十六」と……、それを近くで見ていた男が、翌日小銭を持って早くから蕎麦屋に行き、蕎麦を食べた後、嬉しそうに金を払い始める。「それでは、ひい、ふう、みい、……なな、やー」と数えたところで「今、何刻だ」「四(よつ)です」「いつ、むう、なな、やー……」と……』という話です。これは有名な「時蕎麦」という落語ですね、蕎麦代と時刻が同じ一桁だったのでうまくいくお話です。また時の鐘を打つには必ず捨て鐘というものを三つ撞きました。ですから四つ目から数えるのです。江戸時代の時の間隔は一定ではなく、日の長さによって時の間隔も変わっていました。「時の鐘の時間を計るには、大抵水時計を用いていましたが、その時間も日の永いときには昼の一時は長く、夜の一時は短かったので、本当の日永・短夜であったのです。これは日出・日没を基として明六つ・夕六つと区切り、昼夜を六分して、明六つ・五つ・四つ・九つ・八つ・七つ・夕六つを昼間とし、夕六つから五つ・四つ・九つ・八つ・七つ・明六つまでを夜としてあったので、一時の時間が冬日の二時間に決まっているにもかかわらず、日の永い時には一時が二時間二十分くらいに延びたり、日の短い時には一時が一時間四十分くらいに縮まったりするような不同の時刻ができたのです。」とあります。日の出ている間を基本としていますので、合理的といえば合理的です。
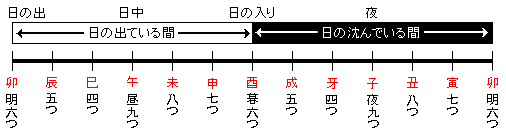
岡本綺堂の「風俗 江戸物語」では9ヶ所の「時の鐘」を紹介しています。今週は現在、鐘が残っている所を中心に紹介します。
【時の鐘 散歩地図】←ここをクリックして地図を出してください。
|