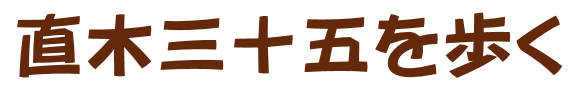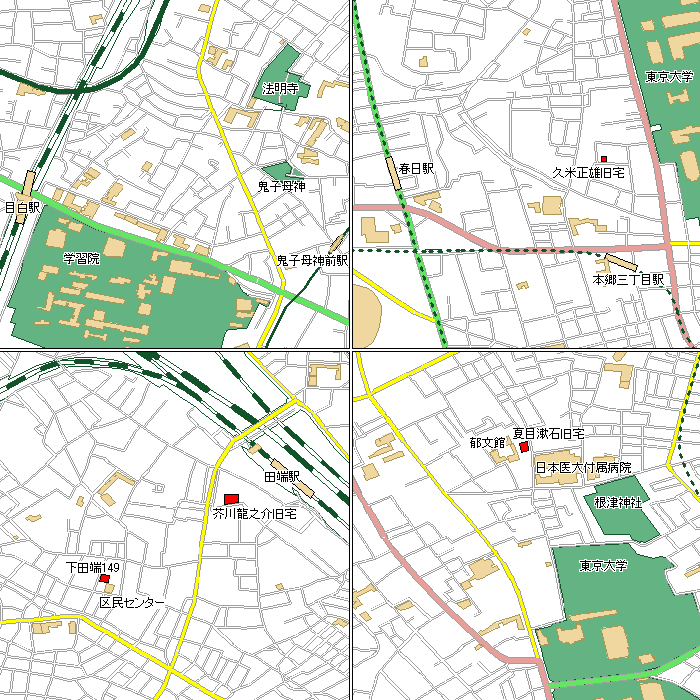直木三十五は明治44年3月、奥谷尋常小学校の代用教員を辞めて、早稲田大学予科を目指します。第六高等学校の入試に失敗し、国立の高等学校は無理と悟ったのでしょう。当時の早稲田大学予科は現在とは違い、簡単に入学できたとおもいます。
「…この女は私を獲ようとして、大阪から出てきたのである。しかし、何事もなかった。翌日
「市ちゃんとこへ行きましょうか」
「うむ」
そして、二人は、植木屋さんの離れで、市ちゃんと三人で寝た。
その暁、私は、無残にも、取り返しのつかぬ事を、されてしまったのである。
「荷物をもってくるから」
と、云って、須磨子は、大阪へ帰ってしまった。私は汚された身を、袴でつつんで、おもしろくない講義を聞きに行っていたが、その内
「家との事が、中々面倒で ── あんた、いつ帰る」
と、いう手紙がきた。そして、この手紙の終りに、何んと「旦那様」と、書いてあった。
うれしいような、馬鹿にされたような──こんな言葉は車屋と、乞食の使う言葉で、使われる奴は、五十歳以上というように感じていた私は、その手紙を披げて、にやにや笑いながら
(矢張り、征服したのかな)
とも、感じた。…」。
「死ぬまでを語る」からです。上手に、面白おかしく書いています。ほとんどフィクションではないかとおもいます。”その暁、私は、無残にも、取り返しのつかぬ事を、されてしまったのである”は本当に面白いですね。
★左の写真は鬼子母神を右にぬけた先です。”鬼子母神の境内を抜けると、もう一つ寺がある。その側に、植木屋があった。”と下記に書かれていましたので鬼子母神を抜けた先のお寺を探しました。写真の先に法明寺があります。推定ですがこの付近に植木屋があったのだとおもいます。
「…雑司ケ谷、鬼子母神の境内を抜けると、もう一つ寺がある。その側に、植木屋があったが、ここに、佛子須磨子の姉の子が、自炊して、早大へ通っていた。ここへ、一日、須磨子が現れた。井上市次郎というその甥さん── だが六つ齢下の甥さんは
「何んや、喧嘩したんか」
と、大きい眼を、もっと、大きくして聞いた。
「はあ、もう、大阪へ帰れへんつもり」
須磨子は、兄の玄竜という人と、余り仲がよくなかった。大学生位までは、美人の妹というものをもっていると、いろいろ利益や、興味が、多いものであるが、生活などが、うまく行かないのに、二十七にもなる妹をもっていると、何んなにそれが、美しくとも、古い女房の、美しさと同じで、少しも、よくは感じないものである。
「植村は」
「田端にいよる」…」。
この鬼子母神付近から早稲田大学までは2Km弱の距離です。20〜30分位ですので学生が歩くのには丁度良い距離ではないでしょうか。