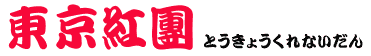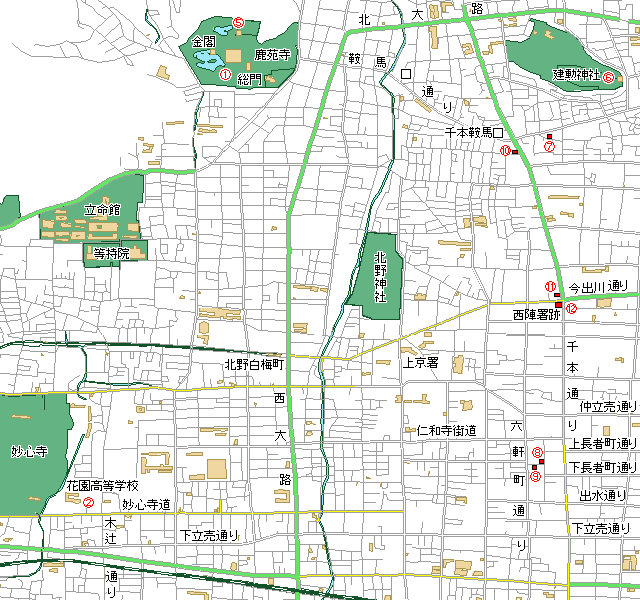養賢は終戦一年前の昭和19年4月、鹿苑寺に入ります。このお寺は一般には金閣寺と呼ばれていますが、鹿苑寺(臨済宗相国寺派の禅寺)が正式名称です。元々は西園寺公経の別荘(鎌倉時代)だったそうですが、その後、足利義満が西園寺家から譲り受け、山荘北山殿を造っています。三島由紀夫の「金閣寺」から引用します。「…足利義満は西園寺家の北山殿を譲り受け、ここに大規模な別荘を営んだ。その主要建築は、舎利殿、護摩堂、懺法堂、法水院などの仏教建築と、宸殿、公卿間、会所、天鏡閣、拱北楼、泉殿、看雪亭などの、住宅関係の建築とであった。舎利殿は最も力を注いで造られ、後に金閣と言われた建物である。いつ頃から金閣というようになったか、はっきりと一線を引くのは困難であるが、応仁の乱以後らしく、文明頃には可成普遍的に用いられている。金閣はひろい苑池(鏡湖池) にのぞむ三層の楼閣建築で、一三九八年(応永五年)どろ出来上ったものと思われる。一・二層は寝殿道風につくり、蔀戸を用いているが、第三層は方三間の純然たる禅堂仏堂風につくり、中央を桟唐戸、左右を花頑窓としている。屋根は槍皮葺・宝形道で金銅の鳳凰をあげている。また、池にのぞんで、切妻屋根の釣殴(漱清)を突出させ、全体の単調を破っている。屋根の勾配はゆるやかで、軒は疎樺とし、木割細く軽快優美であって、住宅風の建築に仏堂風を配して調和をえた庭園建築の優作であり、公家文化をとり入れた義満の趣味の現われと、当時の雰囲気とをよく伝えている。義満の死後、北山殿は遺命により禅刺となし、鹿苑寺と号した。その建物も他に移されたり、または荒廃したりしたが、金閣だけは幸いに残された。…」。よく現代まで残っていたとおもいます(残念ながら焼けてしまいますが!)。御所からは北西の方角で、またかなり離れていたため、大火にも合わずに済んだのだとおもいます。御所より南側だったらかなり昔に焼けてしまったとおもいます。
★左上の写真が金閣です。池に写る金閣はすばらしいです(写真はいまいち)。