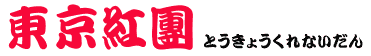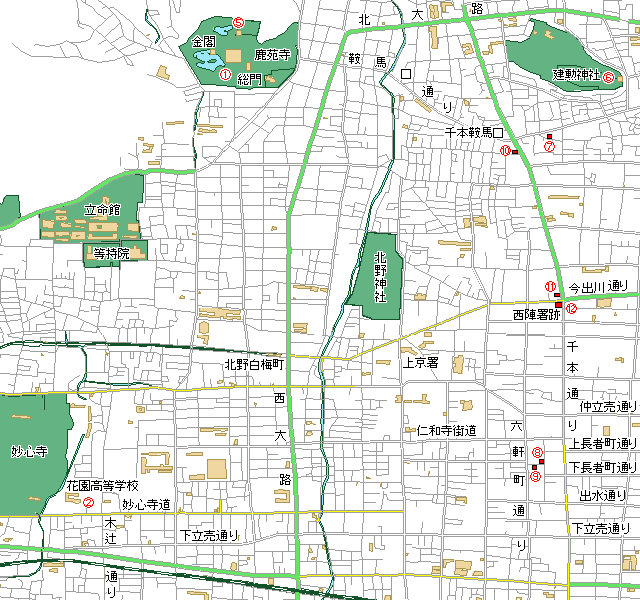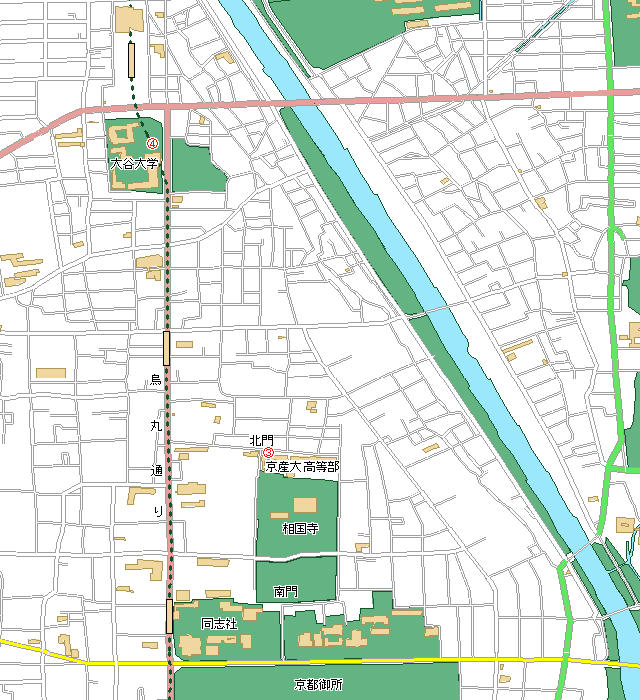養賢は昭和17年12月に父が死去したため、東舞鶴中学校を中退し約束より一年早く昭和18年4月、金閣寺に入山します。三島由紀夫の「金閣寺」から引用します。「…父の遺言どおり、私は京都へ出て、金閣寺の徒弟になった。そのとき住職に就いて得度したのである。学資は住職が出してくれ、その代りに掃除をしたり、住職の身のまわりの世話をしたりする。在家のいわゆる書生と同じことである。。……『金閣よ。やっとあなたのそばへ来て住むようになったよ』と、私は欝の手を休めて、心に呟くことがあった。『今すぐでなくてもいいから、いつかは私に親しみを示し、私にあなたの秘密を打明けてくれ。あなたの美しさは、もう少しのところではっきり見えそうでいて、まだ見えぬ。私の心象の金閣よりも、本物のほうがはっきり美しく見えるようにしてくれ。又もし、あなたが地上で比べるものがないほど美しいなら、何故それほど美しいのか、何故美しくあらねばならないのかを語ってくれ』 その夏の金閣は、つぎつぎと悲報が届いて来る戦争の暗い状態を餌にして、一そういきいきと輝やいているように見えた。六月にはすでに米軍がサイパンに上陸し、連合軍はノルマンジーの野を馳駆していた。拝観者の数もいちじるしく減り、金閣はこの孤独、この静寂をたのしんでいるかのようだった。…」。流石の三島由紀夫です。下記に水上勉の「金閣寺炎上」を掲載しておきますが、三島由紀夫の文章は”ことば”ひとつひとつに意味があるというか、美しいですね。水上勉は「ノンフィクション」として魅力があり、三島由紀夫は純文学として魅力があるようにおもいます。20歳で徴兵検査ですから養賢は兵隊に行かなくて済んだようです。
★左上の写真は金閣寺総門です。休日の撮影だったので観光客の切れ間が無く撮影に苦労しました。水上勉の「金閣炎上」からも引用しておきます。三島由紀夫の「金閣寺」と比べてみてください。「…林養賢は昭和十九年四月二日、林喜一郎につれられて金閣寺に入るのである。志満子は同道しなかった。約束より一年早く入山してきた養賢を、住職村上慈海師はこころよく迎えた。……京都駅からの手荷物が養賢の小僧部屋の六畳にはこばれた時、谷井貞一は、明けた障子の手前側に身をおいて、顔だけ敷居へ出して見た。学用品、書籍、衣類の入った行李一個と油紙に包んだ大包みが一個、その荷物はふつうの小僧のよりは少なかった。…」。水上勉の文章も読ませますね。次が読みたくなります。