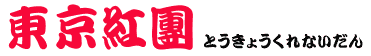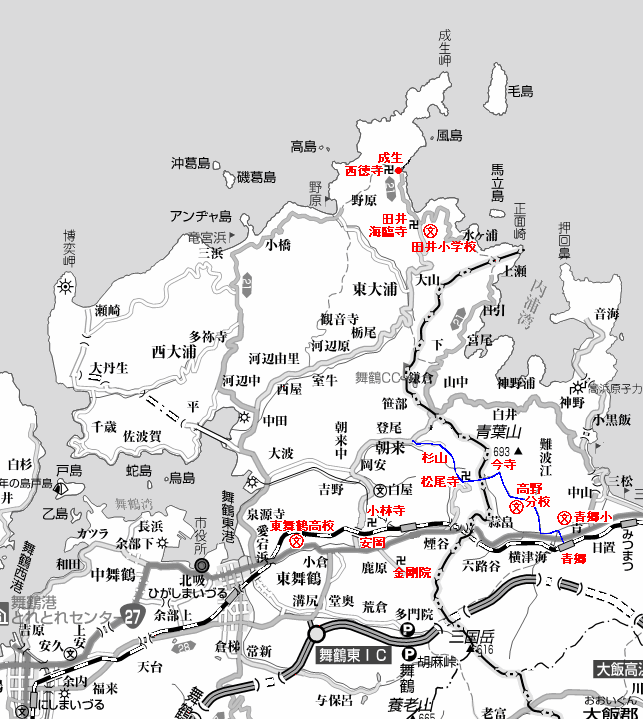水上勉と林養賢は戦前の昭和19年8月に出会っているようです。ただ、出会いは水上勉の「金閣炎上」に記載されているのですがあくまでもフィクションの本ですので真実については不明です。「…私が在地の名を冠して高野分教場とよばれたこの学校にいたのは、昭和十九年春から二十年の秋までだった。……昭和十九年の八月はじめである。確かな日はわすれたが、陽のかけらがそこらじゆうにつきささる暑い午すぎだった。杉山峠から北へ少し行った茅っ原で、その男たちと出あった。男たちというのは、私が京都の相国寺塔頭の小僧だった頃、本山宗務所から今宮の大徳寺よこにあった般若林中学へ通っていた上級生の滝谷節宗と、もう一人はその時しか見ていない中学生だった。……。…」。さすがに舞鶴付近については描写が細かいです。高野分教場で代用教員をしていた頃については「水上勉の生誕の地 若狭を歩く」を参照してください(近々に改版予定です)。林養賢は上記に書かれている”もう一人はその時にしか見ていない中学生だった”ようです。林養賢は昭和16年4月に東舞鶴中学校(旧制)に入学しますが昭和19年4月に金閣寺に入っており、そのため中学校も京都の臨済学院中等部に転入しています。ですから19年夏には臨済学院中等部に在学していましたから、養賢が夏休みに成生に戻っていたときの話になります。
★左上の写真は杉山峠から少し北に入った”杉山入口”です。写真の左側に杉山1.2Kmと書いてある看板が見えます。”杉山峠から北へ少し行った茅っ原”の茅っ原の場所がよく分かりませんでした。当時のこの付近は舞鶴軍港があったため要塞地帯だったようです。「…当時はこの半島全体は、舞鶴軍港を抱く要塞地帯だった。しょっちゅう監視員が見廻りにきた。司令部からの刷り物には、子供に山や森を写生させたり、地誌のまねごとすらも書かせてならないとあった。最上級の四年生のため、私は教室のうしろ壁に、掛軸型の「大日本帝国精図」をかけていたが、その地図にも分教場の所在する高野区の山や川は誌されていず、岬の名である成生ももちろんなかった。…」。青郷駅から高野分教場を通って今寺まではそこそこの道でしたが、今寺から松尾寺まではカローラクラスの車がやっと一台通れるくらいの道でした。今寺で「SM2Z舞鶴要塞第二地帯」と書かれた当時の石碑を見つけました。最初のSM2Zは何のことが分かりませんでした。