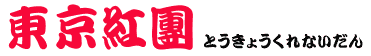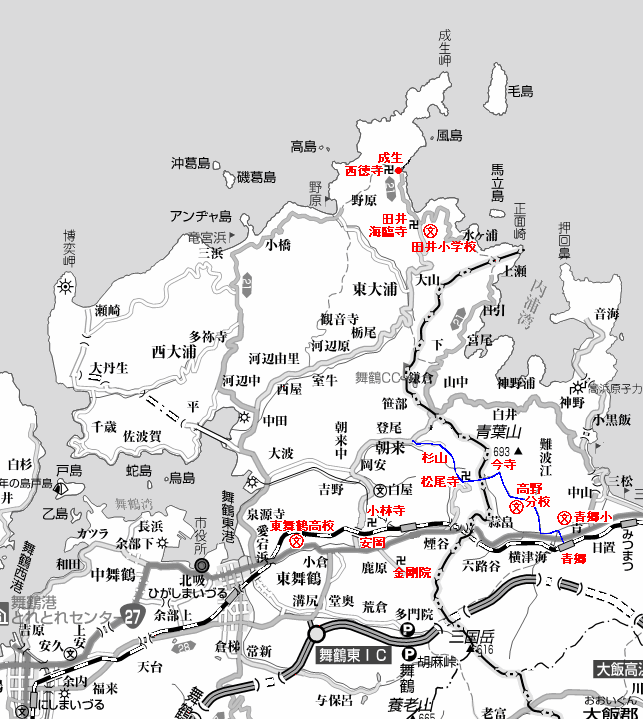金閣寺というと三島由紀夫と水上勉の金閣寺ですね。三島由紀夫と水上勉の金閣寺(正確には三島由紀夫は「金閣寺」、水上勉は「金閣炎上」)は少し意味合いが違います。三島由紀夫の「金閣寺」は純文学と言っていいとおもいますが、水上勉の「金閣炎上」はノンフィクション小説と言った方がいいとおもいます。両者の小説を参照しながら林養賢を歩いてみます。先ずは三島由紀夫の「金閣寺」の書き出しです。「幼時から父は、私によく、金閣のことを語った。 私の生れたのは、舞鶴から東北の、日本海へ突き出たうらさびしい岬である。父の故郷はそこではなく、舞鶴東郊の志楽である。懇望されて、僧籍に入り、辺鄙な岬の寺の住職になり、その地で妻をもらって、私という子を設けた。…」。もう一つ、三島由紀夫の「金閣寺」は昭和31年31歳の時に書かれたもので、水上勉の「金閣炎上」は23年後の昭和54年に書かれています。水上勉は当然三島由紀夫の「金閣寺」を読んでいた筈ですし参照しているとおもいます。
★左上の写真は舞鶴市字安岡にある林養賢と母親のお墓です(正面が本人で右側が母親の墓です)。林養賢の生まれ故郷、京都府舞鶴市字成生から始めようとおもったのですが、先ずは養賢のお墓から始めたいとおもいます。水上勉の「金閣炎上」この最後に林親子のお墓を訪ねる場面があります。「…共同墓地の、椿林の一角に、林家の墓石群はあった。隅に二基、正四角立方型の二尺ぐらいの高さの石塔があり、一基は養賢のもので、「正法院鳳林養賢居士」と彫字はよめ、一基は「慈照院心月妙満大姉」とよめた。裏に両名の死亡年月日があった。志満子は昭和二十五年七月三日になっていた。保津川投身の日である。ともに林家の建立による。母子が俗家へ帰ったのだから、養賢としては、身近な在家である林家にもどって不思議はない…」。養賢の死亡日時は昭和35年7月3日と書かれていました。