<「伊藤整全集」、伊藤整(前回と同じ)>
伊藤整は明治38年(1905)
1月17日(戸籍上は25日)に父、伊藤昌整、母、タマの長男として北海道松前郡炭焼沢村(現・松前町白神)に生まれます。上に姉(照)が一人いました。最初、北海道松前郡炭焼沢村(現・松前町白神)が何処にあるのか分らず、探してしまいました。函館から国道228号線を西へ車で87km、約2時間の距離でした。
「伊藤整全集 第十四巻 年譜」からです。
「 明治三十八年(一九〇五)
一月十六日(戸籍上は二十五日)、北海道の最南端、白神岬のある松前郡炭焼沢村(現・松前町字白神)百壱番地に伊藤昌整(明治四年九月二十八日生)、鳴海タマ(明治十七年十月五日生)の長男として生まれる。本名整。姉照(明治三十六年八月六日生)があり、大正十四年(整二十歳)までに弟妹十人が生まれた。母タマの人籍が遅れたため、照、整、次弟博(明治四十年一月二十日生)、三弟薫(同四十二年三月一日生)の四人は庶子として届出られ、明治四十二年五月、タマ入籍と同時に嫡出子となった。…」。
上記は伊藤整全集第24巻に掲載された年譜の最初に出てくるところです。それてしても詳細に書かれています。これだけ詳細に書かれている年譜は見たことがありません。父親の昌整さんがかなり詳細に書き残していたのではないかとおもいます。(生年月日については下記に別途記載)
伊藤 整(いとう せい、明治38年(1905)1月16日 - 昭和44年(1969)11月15日)
伊藤 整は、日本の小説家、詩人、文芸評論家、翻訳家。本名は伊藤
整(いとう ひとし)。北海道松前郡炭焼沢村(現松前町)で小学校教員の父の下に12兄弟の長男として生まれます。父は広島県三次市出身の下級軍人で、日清戦争の後、海軍の灯台看守兵に志願して北海道に渡っています。明治39年(1906)塩谷村(現小樽市塩谷町)役場転職に伴い小樽へ移住。旧制小樽中学(北海道小樽潮陵高等学校の前身)を経て小樽高等商業学校(小樽商科大学の前身)に学んでいます。小樽高商在学中の上級生に小林多喜二がいました。卒業後、旧制小樽市立中学の英語教師に就任。宿直室に泊まり込んで下宿代を浮かせたり、夜間学校の教師の副職をするなどして、1300円の貯金を蓄え、2年後に教師を退職し上京します。昭和2年(1927)旧制東京商科大学(一橋大学の前身)本科入学。内藤濯教授のゼミナールに所属し、フランス文学を学びます。又、下宿屋にいた梶井基次郎、三好達治、瀬沼茂樹らと知り合い親交を結んでいます。その後大学を中退し、戦前、戦後にかけて金星堂編集部、日本大学芸術科講師、新潮社文化企画部長、旧制光星中学校(現札幌光星高等学校)英語科教師、帝国産金株式会社落部工場勤務、北海道帝国大学予科講師等で働いています。戦後、東京に戻ってからは日本文芸家協会理事、早稲田大学第一文学部講師、東京工業大学教授、日本日本近代文学館理事長等を歴任します。チャタレイ裁判で有罪となったことはその社会的地位にほとんど影響はありませんでした。1969年11月15日、胃癌のため死去しています。(ウイキペディア参照)
★写真は新潮社版、昭和49年(1974)発行の伊藤整全集
第24巻です。写真は巻かれているパラフィン紙が糊付けされていて取れないので、パラフィン紙の上から撮影したため、少しぼけた写真になっています。


●伊藤整の北海道を歩く -3-
初版2015年2月7日 <V01L01> 暫定版
新企画、「伊藤整を歩く」を継続して掲載します。今回は「伊藤整の北海道を歩く -3-」として、大正6年の庁立小樽中学校(現 潮陵高校)入学から大正14年の小樽市中学校(現 長橋中学校)の教諭になるまでを歩きます。
<「若き日の伊藤整」、武井静夫(前回と同じ)>
伊藤整について書かれた伝記や年譜等の本は非常に多いです。伊藤整自信が父親のことや生まれ、学生時代にについて詳細に書いているため、伝記等が書きやすかったのではないかとおもわれます。今回はその中から北海道在住の武井静夫さんの「若き日の伊藤整」を参考にさせてもらいました。
武井静夫さんの「若き日の伊藤整」から「あとがき」です。
「 あとがき
昭和四十五年五月二十三日、塩谷ゴロダの丘で、伊藤整文学碑の除幕式があった。その丘に立って海を眺め、そこにより集う人たちの名を聞いた時、『若い詩人の肖像』の世界が、そのまま再現しているのにおどろいた。その誰もが、年老いながら健在であった。
そのおどろきは。やがて伊藤整にとって故郷とは何か、その故郷でどのように成長していったかの問いかけとなった。さいわいその年に転勤になった仁木町から、余市や塩谷は近かった。それをまとめたものが、『北方文芸』に連載した「伊藤整伝」である。
伊藤整の場合、事実と作品の世界とは微妙にいりくんでいる。いきおい客観的事実の追求というより、自らの問に対する解答という形をとらざるをえなくなった。そのなかから私なりの伊藤整の青春像を描いてみようとした。それに加筆したり、訂正を加えたものがこの作品である。
調査にあたり、星野照、北見恂吉、杉沢仁太郎、沢田斉一、田居尚、更科源蔵の諸氏をけじめ、数多くの人たちに御教示をうけた。
瀬沼茂樹先生、小笠原克氏には、常に御指導とはげましの言葉をいただき、出版にあたっては。関井光男、宮西忠正両氏のなみなみならぬお力添えをうけた。つつしんで感謝の意を申し上げる。
昭和四十九年一月
武井静夭」。
上記に”伊藤整の場合、事実と作品の世界とは微妙にいりくんでいる”と書かれています。作家が書いた私小説は全てが正しいとは限りません。やはり面白く書いていますので若干の脚色が入るのはやむを得ないとおもいます。それを、伝記等を書く作家が内容を検証して書く必要があるわけです。
★写真は、冬樹社版、武井静夫さんの「若き日の伊藤整」です。昭和49年が初版発行です。私が入手したのは昭和52年発行の第二版です。
伊藤整について書かれた伝記や年譜等の本は非常に多いです。伊藤整自信が父親のことや生まれ、学生時代にについて詳細に書いているため、伝記等が書きやすかったのではないかとおもわれます。今回はその中から北海道在住の武井静夫さんの「若き日の伊藤整」を参考にさせてもらいました。
武井静夫さんの「若き日の伊藤整」から「あとがき」です。
「 あとがき
昭和四十五年五月二十三日、塩谷ゴロダの丘で、伊藤整文学碑の除幕式があった。その丘に立って海を眺め、そこにより集う人たちの名を聞いた時、『若い詩人の肖像』の世界が、そのまま再現しているのにおどろいた。その誰もが、年老いながら健在であった。
そのおどろきは。やがて伊藤整にとって故郷とは何か、その故郷でどのように成長していったかの問いかけとなった。さいわいその年に転勤になった仁木町から、余市や塩谷は近かった。それをまとめたものが、『北方文芸』に連載した「伊藤整伝」である。
伊藤整の場合、事実と作品の世界とは微妙にいりくんでいる。いきおい客観的事実の追求というより、自らの問に対する解答という形をとらざるをえなくなった。そのなかから私なりの伊藤整の青春像を描いてみようとした。それに加筆したり、訂正を加えたものがこの作品である。
調査にあたり、星野照、北見恂吉、杉沢仁太郎、沢田斉一、田居尚、更科源蔵の諸氏をけじめ、数多くの人たちに御教示をうけた。
瀬沼茂樹先生、小笠原克氏には、常に御指導とはげましの言葉をいただき、出版にあたっては。関井光男、宮西忠正両氏のなみなみならぬお力添えをうけた。つつしんで感謝の意を申し上げる。
昭和四十九年一月
武井静夭」。
上記に”伊藤整の場合、事実と作品の世界とは微妙にいりくんでいる”と書かれています。作家が書いた私小説は全てが正しいとは限りません。やはり面白く書いていますので若干の脚色が入るのはやむを得ないとおもいます。それを、伝記等を書く作家が内容を検証して書く必要があるわけです。
★写真は、冬樹社版、武井静夫さんの「若き日の伊藤整」です。昭和49年が初版発行です。私が入手したのは昭和52年発行の第二版です。
<庁立小樽中学校>
伊藤整は塩谷尋常高等小学校、一年から六年まで全て甲ですから、当然、中学校に進学するわけですが、父親が良く許したとおもいます。当時の北海道の中学校は各都市に基本的には一つしか無く、小樽は庁立小樽中学校、札幌は二校で庁立札幌中学校、庁立札幌第二中学校、その他の都市では一校で、かなりの競争率だったとおもいます(他に旭川、函館等)。
武井静夫さんの「若き日の伊藤整」からです。
「… 大正六年三月二十四日、整は同級生四十四名とともに、塩谷尋常高等小学校尋常科を卒業した。一年から六年まで、「全甲」の成績であった。…
…
庁立小樽中学校
一
大正六年三月十四日、庁立小樽中学校の入学試験が行なわれた。志願者は三百十一名、倍率は三・一倍であった。整は、父の昌整に連れられてこの学校のすぐ下にある、潮見台町(小樽区)の宿屋に泊った。同級の人たちも一緒であった。昌整はすぐに帰った。
この宿屋に、村上時治(明治三三・一・二六生)がたずねて来る。彼はこの中学校の一年に在学していて、近くの寄宿舎にいた。父の村上市三郎は、塩谷村六十番地の網元で、時治は塩谷小学校の先輩であった。
この村上に連れられて、整は寄宿舎の村上の同室の人たちに会った。「中学生というのは皆大人で顎に鬚など生えていて怖ろ」(「自伝的スケッチ」)しいと思う。村上は、「受験生は三倍半あるぞ」とおどかし、中学の「算術」の教科書をとり出しては「試験問題はみなこの中から出るんだ」と言ったりした。
それから彼等を、「喬麦屋」へ連れて行く。整は「蕎麦屋」が「曖昧屋」の意味につかわれていろのを知っていたから、何を出されるかと気をもんだが、出されたのがソバだけだったのでホッとした。
試験の結果が発表されてみると。塩谷の小学校からは、整一人しか合格していなかった。その知らせを学校にもって行ったとき、担任の角田先生はひじょうに喜んだ。整は、いつも一番をつづけていた飯田左内が落ちたのが、不思議であった。翌年になって彼が人学してからも「心苦しい思い」のしどおしだったという。整十二歳の時である。
入学試験があって十日後の三月二十四日、塩谷尋常高等小学校の卒業式があった。
中学校は、北海道庁立小樽中学校といった。庁立とは、北海道庁によって建てられていたからで、現在の道立とか県立とかと同じである。明治三十五年三月二十七日に設置の告示があり、五月十五日に開校式が行なわれている。校舎はその年の十一月に、小樽区潮見台町に建てられる。現在の小樽潮陵高等学校である。
大正六年四月九日、午後一時より、第十七回の入学式が行なわれた。この年入学を許可された者は、二学級百名であった。…」。
当時の庁立小樽中学校は現在の道立小樽潮陵高等学校となっています。旧制小樽中学校は函館中(現北海道函館中部高等学校)、札幌一中(現北海道札幌南高等学校)に次いで道内三番目に設立された旧制中学校で、古い歴史をもつ名門の公立高等学校です。自由な校風が特徴とされ、北海道内では「潮陵(ちょうりょう)」の名で知られています。(ウイキペディア参照)
★写真は現在の道立小樽潮陵高等学校です。場所も当時と変っていません。場所は下記の地図を参照してください。
伊藤整は塩谷尋常高等小学校、一年から六年まで全て甲ですから、当然、中学校に進学するわけですが、父親が良く許したとおもいます。当時の北海道の中学校は各都市に基本的には一つしか無く、小樽は庁立小樽中学校、札幌は二校で庁立札幌中学校、庁立札幌第二中学校、その他の都市では一校で、かなりの競争率だったとおもいます(他に旭川、函館等)。
武井静夫さんの「若き日の伊藤整」からです。
「… 大正六年三月二十四日、整は同級生四十四名とともに、塩谷尋常高等小学校尋常科を卒業した。一年から六年まで、「全甲」の成績であった。…
…
庁立小樽中学校
一
大正六年三月十四日、庁立小樽中学校の入学試験が行なわれた。志願者は三百十一名、倍率は三・一倍であった。整は、父の昌整に連れられてこの学校のすぐ下にある、潮見台町(小樽区)の宿屋に泊った。同級の人たちも一緒であった。昌整はすぐに帰った。
この宿屋に、村上時治(明治三三・一・二六生)がたずねて来る。彼はこの中学校の一年に在学していて、近くの寄宿舎にいた。父の村上市三郎は、塩谷村六十番地の網元で、時治は塩谷小学校の先輩であった。
この村上に連れられて、整は寄宿舎の村上の同室の人たちに会った。「中学生というのは皆大人で顎に鬚など生えていて怖ろ」(「自伝的スケッチ」)しいと思う。村上は、「受験生は三倍半あるぞ」とおどかし、中学の「算術」の教科書をとり出しては「試験問題はみなこの中から出るんだ」と言ったりした。
それから彼等を、「喬麦屋」へ連れて行く。整は「蕎麦屋」が「曖昧屋」の意味につかわれていろのを知っていたから、何を出されるかと気をもんだが、出されたのがソバだけだったのでホッとした。
試験の結果が発表されてみると。塩谷の小学校からは、整一人しか合格していなかった。その知らせを学校にもって行ったとき、担任の角田先生はひじょうに喜んだ。整は、いつも一番をつづけていた飯田左内が落ちたのが、不思議であった。翌年になって彼が人学してからも「心苦しい思い」のしどおしだったという。整十二歳の時である。
入学試験があって十日後の三月二十四日、塩谷尋常高等小学校の卒業式があった。
中学校は、北海道庁立小樽中学校といった。庁立とは、北海道庁によって建てられていたからで、現在の道立とか県立とかと同じである。明治三十五年三月二十七日に設置の告示があり、五月十五日に開校式が行なわれている。校舎はその年の十一月に、小樽区潮見台町に建てられる。現在の小樽潮陵高等学校である。
大正六年四月九日、午後一時より、第十七回の入学式が行なわれた。この年入学を許可された者は、二学級百名であった。…」。
当時の庁立小樽中学校は現在の道立小樽潮陵高等学校となっています。旧制小樽中学校は函館中(現北海道函館中部高等学校)、札幌一中(現北海道札幌南高等学校)に次いで道内三番目に設立された旧制中学校で、古い歴史をもつ名門の公立高等学校です。自由な校風が特徴とされ、北海道内では「潮陵(ちょうりょう)」の名で知られています。(ウイキペディア参照)
★写真は現在の道立小樽潮陵高等学校です。場所も当時と変っていません。場所は下記の地図を参照してください。
<小樽区緑町一丁目三番地>
伊藤整が庁立小樽中学校入学後に下宿した場所です。中学校入学後の大正6年4月から大正8年7月までの間、姉と共に下宿を転々としています。家計が苦しく、少しでも安い下宿を転々とした結果ではないでしょうか。
武井静夫さんの「若き日の伊藤整」からです。
「… 小樽中学校に入学した整は、小林北一郎が養母とともに暮らしている小樽区緑町一丁目三番地の家に寄寓した。整はこの北一郎をチンチャと呼んで親しみ、尊敬していた。その後、そこを出て姉の照と自炊をした。照ははじめ小樽貯金局に勤めていたが、間もなくそこをやめて三井物産に移っていた。二人は中学校の下にあった潮見台町の小柳という人の家を借りた。
小柳は請負師で、その隣には、ドイツ人が日本人の女と住んでいた。整はそのドイツ人にかわいがられた。ときどきはスタイルブックをもらった。整が服装についての関心を持ちはじめたのは、この自炊生活を通してだったと言われている。
ついで二人は、小樽区緑町にあった石屋の奥座敷を借りた。照は勤めの都合で、帰りがおそくなることが多かった。そんな時、整が炊事の仕度をした。みそ汁作りは上手だったという。二人は大正八年まで自炊生活をするが、その年の七月、塩谷の自宅から中央小樽までを汽車通学することになる。中央小樽は、大正九年七月十五日に小樽駅と改称される。…」
大正6年4月以降の下宿で、住所地番が分っているのは小樽区緑町一丁目三番地だけです。潮見台町、緑町と移っていますが、地番が不明です。
★写真は現在の商大通り、緑一丁目交差点の大川町三丁目の交差点から東に50m程の地点から西を撮影しています。左側辺りが緑町一丁目三番地です。大正9年の「最新小樽区土地台帳」を見ましたが、”緑町一丁目三番地”という地番はありましたが小林という名前は書かれていませんでした。
伊藤整が庁立小樽中学校入学後に下宿した場所です。中学校入学後の大正6年4月から大正8年7月までの間、姉と共に下宿を転々としています。家計が苦しく、少しでも安い下宿を転々とした結果ではないでしょうか。
武井静夫さんの「若き日の伊藤整」からです。
「… 小樽中学校に入学した整は、小林北一郎が養母とともに暮らしている小樽区緑町一丁目三番地の家に寄寓した。整はこの北一郎をチンチャと呼んで親しみ、尊敬していた。その後、そこを出て姉の照と自炊をした。照ははじめ小樽貯金局に勤めていたが、間もなくそこをやめて三井物産に移っていた。二人は中学校の下にあった潮見台町の小柳という人の家を借りた。
小柳は請負師で、その隣には、ドイツ人が日本人の女と住んでいた。整はそのドイツ人にかわいがられた。ときどきはスタイルブックをもらった。整が服装についての関心を持ちはじめたのは、この自炊生活を通してだったと言われている。
ついで二人は、小樽区緑町にあった石屋の奥座敷を借りた。照は勤めの都合で、帰りがおそくなることが多かった。そんな時、整が炊事の仕度をした。みそ汁作りは上手だったという。二人は大正八年まで自炊生活をするが、その年の七月、塩谷の自宅から中央小樽までを汽車通学することになる。中央小樽は、大正九年七月十五日に小樽駅と改称される。…」
大正6年4月以降の下宿で、住所地番が分っているのは小樽区緑町一丁目三番地だけです。潮見台町、緑町と移っていますが、地番が不明です。
★写真は現在の商大通り、緑一丁目交差点の大川町三丁目の交差点から東に50m程の地点から西を撮影しています。左側辺りが緑町一丁目三番地です。大正9年の「最新小樽区土地台帳」を見ましたが、”緑町一丁目三番地”という地番はありましたが小林という名前は書かれていませんでした。
<小樽高等商業高校>
大正11年、伊藤整は小樽高等商業高校に入学します。北海道では旧制高等学校はなく、近いところでも仙台の第二高等学校でした。北海道帝国大学では優秀な生徒を確保するため、旧制高等学校と同等の”大学予科”がありましたが、理科のみで文科はありませんでした。ですから、文科を望む生徒は小樽高等商業高校に入学していていたようです。また、北海道帝国大学は農学部が中心で、工学部(大正13年)、理学部(昭和5年)と順次できますが、文学部が出来たのは、戦後の昭和22年になります。文科を望む生徒は東京に向かっていたわけです。
伊藤整文学碑の碑文です。
「… 大正十一年三月、小樽中学校を卒業した伊藤整は、小樽高等商業学校を受験した。入学試験は、一二月二十九日に行なわれた。受験者は六百八十三名で、そのうち百七十三名が人学を許可された。
彼はこの学校に、はじめからあこがれていたのではない。『若い詩人の肖像』には、物価の値上がりは、俸給生活者を困らせる、父は「官費の師範学校」(「自伝的スケッチ」では「師範学校の二部」となっている)へ入れるつもりでいたが、「私」は「官立の高等学校か札幌の官立大学予科」へ行くつもりであった、と書いている。文学に心を占められていながら、医者になりたいとも思っていたからである。しかし、それは実現しそうもなかったので、「妥協」して「自家から通える小樽の高等商業学校」を選んだのだという。
この「妥協」は、彼のその後の生き方にもつながっていくが、この場合、小樽自体が、それを容易にする土地柄であったということもあった。「自伝的スケッチ」では、この間の事情を、
「小樽は元来商業地であるから、商業学校が二つもあり、当時は中学校は一つしかなかった。そ
の上庁立商業は入学もいつも中学校より難かしく、庁立商業生は秀才意識を強く持っているとい
うような特殊な土地である。そのため、中学の卒業生も高等商業学校へ入ることを当然だと思っ
ているような傾きがあり、さしたる躊躇なしに私なども高等商業学校へ入ったものである。」
と説明している。緑町での下宿先であった同郷の小林北一郎も、小樽商業学校からではあったが、やはり高等商業学校に進んでいた。
小樽高等商業学枚は、明治四十三年三月二十七日、勅令第六十六号をもって文部省直轄諸学校官制を改正し、小樽高等商業学校を追加したことに始まっている。翌四十四年三月入学試験が行なわれ、五月五日に第一回の入学式が行なわれていた。
整の入学した大正十一年は、第十二回の入学式で、やはり五月五日に行なわれている。一年生は四組、百九十三名で、二年生には、小林多喜二、高浜年尾などがいた。…」
小樽商科大学は国立大学では唯一の社会科学系単科大学で、1学年500人ほどで、全学でも2000人強の学生数しかいない小規模な大学です。明治43年(1910年)に5番目の官立高等商業学校として設立され、小樽高等商業学校(1944年より小樽経済専門学校)を前身とします。旧制時代は北海道で数少ない文科系の高等教育機関であったため、文芸志向の者も入学し小林多喜二や伊藤整といった作家を輩出しています。一般的に道内では樽商(たるしょう)と略され呼ばれているが、小樽市内では商大と呼ばれている。(小樽市内で「樽商」というと小樽商業高等学校を指すことが多い。)(ウイキペディア参照)
★写真は現在の小樽商科大学正門です。当時の小樽高等商業学枚の絵葉書も掲載しておきます。
大正11年、伊藤整は小樽高等商業高校に入学します。北海道では旧制高等学校はなく、近いところでも仙台の第二高等学校でした。北海道帝国大学では優秀な生徒を確保するため、旧制高等学校と同等の”大学予科”がありましたが、理科のみで文科はありませんでした。ですから、文科を望む生徒は小樽高等商業高校に入学していていたようです。また、北海道帝国大学は農学部が中心で、工学部(大正13年)、理学部(昭和5年)と順次できますが、文学部が出来たのは、戦後の昭和22年になります。文科を望む生徒は東京に向かっていたわけです。
伊藤整文学碑の碑文です。
「… 大正十一年三月、小樽中学校を卒業した伊藤整は、小樽高等商業学校を受験した。入学試験は、一二月二十九日に行なわれた。受験者は六百八十三名で、そのうち百七十三名が人学を許可された。
彼はこの学校に、はじめからあこがれていたのではない。『若い詩人の肖像』には、物価の値上がりは、俸給生活者を困らせる、父は「官費の師範学校」(「自伝的スケッチ」では「師範学校の二部」となっている)へ入れるつもりでいたが、「私」は「官立の高等学校か札幌の官立大学予科」へ行くつもりであった、と書いている。文学に心を占められていながら、医者になりたいとも思っていたからである。しかし、それは実現しそうもなかったので、「妥協」して「自家から通える小樽の高等商業学校」を選んだのだという。
この「妥協」は、彼のその後の生き方にもつながっていくが、この場合、小樽自体が、それを容易にする土地柄であったということもあった。「自伝的スケッチ」では、この間の事情を、
「小樽は元来商業地であるから、商業学校が二つもあり、当時は中学校は一つしかなかった。そ
の上庁立商業は入学もいつも中学校より難かしく、庁立商業生は秀才意識を強く持っているとい
うような特殊な土地である。そのため、中学の卒業生も高等商業学校へ入ることを当然だと思っ
ているような傾きがあり、さしたる躊躇なしに私なども高等商業学校へ入ったものである。」
と説明している。緑町での下宿先であった同郷の小林北一郎も、小樽商業学校からではあったが、やはり高等商業学校に進んでいた。
小樽高等商業学枚は、明治四十三年三月二十七日、勅令第六十六号をもって文部省直轄諸学校官制を改正し、小樽高等商業学校を追加したことに始まっている。翌四十四年三月入学試験が行なわれ、五月五日に第一回の入学式が行なわれていた。
整の入学した大正十一年は、第十二回の入学式で、やはり五月五日に行なわれている。一年生は四組、百九十三名で、二年生には、小林多喜二、高浜年尾などがいた。…」
小樽商科大学は国立大学では唯一の社会科学系単科大学で、1学年500人ほどで、全学でも2000人強の学生数しかいない小規模な大学です。明治43年(1910年)に5番目の官立高等商業学校として設立され、小樽高等商業学校(1944年より小樽経済専門学校)を前身とします。旧制時代は北海道で数少ない文科系の高等教育機関であったため、文芸志向の者も入学し小林多喜二や伊藤整といった作家を輩出しています。一般的に道内では樽商(たるしょう)と略され呼ばれているが、小樽市内では商大と呼ばれている。(小樽市内で「樽商」というと小樽商業高等学校を指すことが多い。)(ウイキペディア参照)
★写真は現在の小樽商科大学正門です。当時の小樽高等商業学枚の絵葉書も掲載しておきます。
<小樽市中学校>
伊藤整は大正14年3月、小樽高等商業学校を卒業します。就職をしないとだめな訳ですが、東京への憧れか、村井銀行(詳細は下記)への就職に期待しますが、父親の反対に遭い、仕方が無く、地元の中学に教師として就職します。実家が生活苦で、整の給与に期待したのではないかとおもわれます。因みに、小樽区から小樽市になったのは大正11年8月1日です。
武井静夫さんの「若き日の伊藤整」からです。
「… 大正十四年三月三十一日、伊藤整は、北海道小樽市中学校教諭心得となり。俸給月百五円をもらうことになった。
「卒業の少し前に、僕は学生課へ呼ばれ、今商大にいる村瀬玄教授から。東京の村井銀行に口があるが、そこへ行く気はないか、と問われた。就職のことで、自分にもそういう機会があるだろうかと漠然と不安に思っていた時だったので、僕は非常に喜んだ。父に相談してみるとだけ答えて引き下ったものの、急に東京へ行けるという、願いもしなかったことが実現しそうな状態になったのでわくわくした。だが父に話をすると、父はどう思ったのか、東京へ行くことは絶対にならん、という強硬な意見であった。僕は今迄大抵のことは自分の思うとおりにやっており、父がそれに反対したことはなかった。それだけに僕は驚いたが、長男の僕に依頼する心も父の中で強くなっているだろうと思い、村瀬教授にはその旨を返事した。教授はもっての外という顔をし、この不況時に、東京で二流の銀行としてとおっている村井銀行の口を蹴るという法はない、と僕に強く説きつけた。」
「自伝的スケッチ」に出ている就職までの経過である。そして、さらにつづけて、「その少しあとに、この春から小樽に市立中学が建つという噂があって、父はそこへ入らないかと言っていた。村瀬教授に相談に行くと。その話はあるらしいがまだ校長もきまっていないのだから見込みはないという意見であった。更に小林象三教授に相談すると、市の教育課長の林田氏が広島高師の同窓生だから紹介してやるという事で林田氏に逢うと、ちょうど教員の銓衡をしていた時ででもあったのか、すらすらと決定してしまった。」というのである。…」
村井銀行は元々は明治37年に設立された銀行で大正6年に株式会社化されています。村井家は明治期に煙草生産で財をなし、国有化で多大な保証金を得て、それらを元手に銀行業を初めています。しかし、昭和3年には昭和銀行に回収され、昭和19年には安田銀行に回収されます。
★写真は現在の長橋中学校です。校舎が完成したのは大正14年12月ですから、それまでは小樽区稲穂小学校の校舎を借りていたようです(緑町一丁目の近くです)。写真は現在の正門ですが、昔の正門が東側にありました。
続きます!
伊藤整は大正14年3月、小樽高等商業学校を卒業します。就職をしないとだめな訳ですが、東京への憧れか、村井銀行(詳細は下記)への就職に期待しますが、父親の反対に遭い、仕方が無く、地元の中学に教師として就職します。実家が生活苦で、整の給与に期待したのではないかとおもわれます。因みに、小樽区から小樽市になったのは大正11年8月1日です。
武井静夫さんの「若き日の伊藤整」からです。
「… 大正十四年三月三十一日、伊藤整は、北海道小樽市中学校教諭心得となり。俸給月百五円をもらうことになった。
「卒業の少し前に、僕は学生課へ呼ばれ、今商大にいる村瀬玄教授から。東京の村井銀行に口があるが、そこへ行く気はないか、と問われた。就職のことで、自分にもそういう機会があるだろうかと漠然と不安に思っていた時だったので、僕は非常に喜んだ。父に相談してみるとだけ答えて引き下ったものの、急に東京へ行けるという、願いもしなかったことが実現しそうな状態になったのでわくわくした。だが父に話をすると、父はどう思ったのか、東京へ行くことは絶対にならん、という強硬な意見であった。僕は今迄大抵のことは自分の思うとおりにやっており、父がそれに反対したことはなかった。それだけに僕は驚いたが、長男の僕に依頼する心も父の中で強くなっているだろうと思い、村瀬教授にはその旨を返事した。教授はもっての外という顔をし、この不況時に、東京で二流の銀行としてとおっている村井銀行の口を蹴るという法はない、と僕に強く説きつけた。」
「自伝的スケッチ」に出ている就職までの経過である。そして、さらにつづけて、「その少しあとに、この春から小樽に市立中学が建つという噂があって、父はそこへ入らないかと言っていた。村瀬教授に相談に行くと。その話はあるらしいがまだ校長もきまっていないのだから見込みはないという意見であった。更に小林象三教授に相談すると、市の教育課長の林田氏が広島高師の同窓生だから紹介してやるという事で林田氏に逢うと、ちょうど教員の銓衡をしていた時ででもあったのか、すらすらと決定してしまった。」というのである。…」
村井銀行は元々は明治37年に設立された銀行で大正6年に株式会社化されています。村井家は明治期に煙草生産で財をなし、国有化で多大な保証金を得て、それらを元手に銀行業を初めています。しかし、昭和3年には昭和銀行に回収され、昭和19年には安田銀行に回収されます。
★写真は現在の長橋中学校です。校舎が完成したのは大正14年12月ですから、それまでは小樽区稲穂小学校の校舎を借りていたようです(緑町一丁目の近くです)。写真は現在の正門ですが、昔の正門が東側にありました。
続きます!
伊藤整の小樽地図 -1-
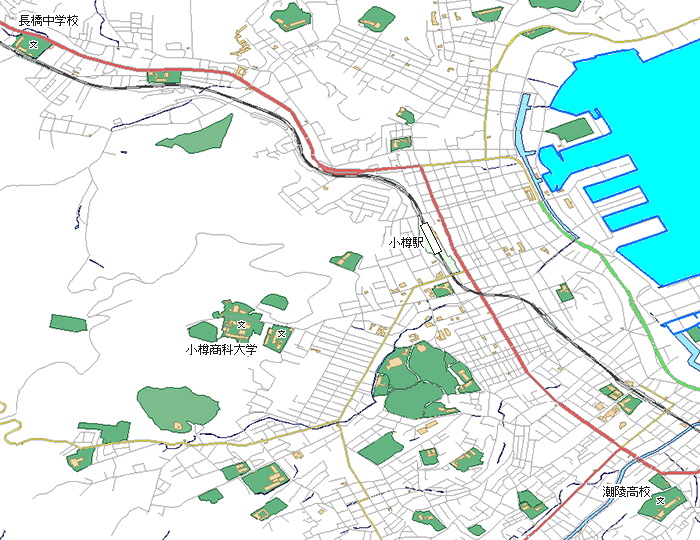
伊藤整年表
| 和 暦 | 西暦 | 年 表 | 年齢 | 伊藤整の足跡 |
|
明治38年
|
1905 | ポーツマス条約 | 0 | 1月16日(戸籍上は25日)松前郡炭焼沢村(現・松前町白神)百壱番地で出生 3月 旭川連隊第二区二条通り三番地一号の官舎に転居 |
| 明治39年 | 1906 | 南満州鉄道会社設立 | 1 | 1月 父親が余市高等小学校教員に転職、余市町大川町三百九十四番地に転居 4月 伍助沢分教場に移る |
| 明治42年 | 1909 | 伊藤博文ハルビン駅で暗殺 | 4 | 8月 父親 塩谷村役場書記に転職 10月 塩谷村八十五番地(現・塩谷1-13)に転居 |
| 明治43年 | 1910 | 日韓併合 | 5 | 1月 父親 陸軍少尉として退役 |
| 明治44年 | 1911 | 辛亥革命 | 6 | 4月 塩谷尋常高等小学校入学 |
| 大正6年 | 1917 | ロシア革命 | 12 | 3月 塩谷尋常高等小学校卒業 4月 北海道庁小樽中学校(現・潮陵高校)入学 |
| 大正11年 | 1922 | ワシントン条約調印 | 17 | 3月 北海道庁小樽中学校(現・潮陵高校)卒業 4月 小樽高等商業高校(現・小樽商科大学)入学 8月 小樽区から小樽市となる |
| 大正14年 | 1025 | 治安維持法 日ソ国交回復 |
20 | 3月 小樽高等商業高校(現・小樽商科大学)卒業 4月 小樽市中学校(現・長橋中学校)教諭となる |





