●司馬遼太郎の「本所深川散歩」 初版2001年4月21日 V01L02
三名の作家で歩く”深川”の最終回として、司馬遼太郎の「本所深川散歩・神田界隈」の中から”深川木場”、”江戸っ子”、”深川の富”に沿って歩いてみたいと思います。この「本所深川散歩」は墨東地区の深川から本所まで広い範囲について書かれていましたので、特に深川に関する所を中心に紹介したいと思います。
 司馬遼太郎の「本所深川散歩・神田界隈」の書き出しは、材木問屋が多い木場の成り立ちと、おきゃんな深川芸者の話から始まります。この”おきゃん”という言葉は明治以降、樋口一葉の「たけくらべ」や夏目漱石の「ぼっちゃん」(マドンナも余っ程気の知れないおきゃんだ)等にも使われいますが、本来の意味は江戸時代の深川芸者の心意気をあらわす言葉だった様です。 司馬遼太郎の「本所深川散歩・神田界隈」の書き出しは、材木問屋が多い木場の成り立ちと、おきゃんな深川芸者の話から始まります。この”おきゃん”という言葉は明治以降、樋口一葉の「たけくらべ」や夏目漱石の「ぼっちゃん」(マドンナも余っ程気の知れないおきゃんだ)等にも使われいますが、本来の意味は江戸時代の深川芸者の心意気をあらわす言葉だった様です。
<紀ノ国屋文左衛門>
「ともかくも、江戸第一期の繁栄期である元禄時代(1688〜1704)には、深川木場は大いににぎわった。とくに江戸中期までは経済社会の密度も粗かったから、巨利を得る者が多く、ときににわか成金も出た。そういう者が、色町で財を散じた。色町では、大づかみで散財してくれる者を??お大尽″とよび、下にもおかぬもてなしをした。十七世紀の紀州人で、紀伊国屋文左衛門などは、その代表だったろう。略して”紀文”とよばれたこの人物は、材木商として巨利を博した。かれのあそびの豪儀さを讃美して、二朱判吉兵衛という野間が、「大尽舞」という囃子舞をつくって大いにひろめた。歌詞は、まことにばかばかしい。そもそもお客の始まりは、高麗もろこしは存ぜねど、今日本にかくれなき、紀ノ国文左でとどめたり」と紀伊国屋文左衛門について書かいていますが、墓も深川の成等院に残っています。紀伊国屋文左衛門については皆様よくご存知の通り紀州の人で、若海三浦実誠著『墓所一覧遺稿』に、「紀伊国屋文左衛門、別所氏、俳名千山、享保三年正月二日没、年五十四、法号本覚院還誉到億西岸信士、葬深川霊巌寺中成等院」と書かれています。江戸に出てきて材木商となり、老中柳沢吉保と結び、上野寛永寺の建築材納入で、多大の財をなしたと伝えられています。また一方で文人墨客と交遊があり、宝井其角の門人となって、俳名を千山と号しています。正徳(1711〜1715)の頃には、家運も衰え、深川八幡一の鳥居付近(現門前仲町一丁目)に住み、そこで死去したようです。(江東文化財より)
★左の写真が紀伊国屋文左衛門の碑です。碑の左側に小さなお墓がありますがこれが紀伊国屋文左衛門の墓です。成等院の右側にありますのですぐに分かります。
 <奈良屋茂左衛門> <奈良屋茂左衛門>
お大尽にもう一人”奈良屋茂左衛門”についても司馬遼太郎は書いています。「紀文とならんでにわか分限になったのが、通称”奈良茂”とよばれた奈良屋茂左衛門だった。奈良茂は、深川の裏店にすんでいた木場人足の子としてうまれた。少年のころから利発で、界隈ではめずらしく読み書きに長じていたという。はじめ宇野という材木問屋に奉公して商いのことを見習い、二十七、八で暇をとって独立した。といって、問屋は免許制だからそうそう店をひらけるわけでもなく、わずかな丸太や竹などを扱っていた。さきの紀文が上野寛永寺の中堂の普請でもって財をなしたといわれるが、奈良茂が頭をもたげたきっかけは、日光山東照官の普請だった。」、奈良屋茂左衛門は、姓を神田氏といい、紀伊国屋文左衛門と豪遊を競った富豪の材木商であったといわれています。
★右の写真は奈良屋茂左衛門のお墓があった雄松院です。雄松院にあった墓石は、大正12年の関東大震災で失われてしまい、現在過去帳のみが残っているそうです。それによると茂左衛門は数代あり、何代目の茂左衛門が紀文と競ったかはよくわからないようです。(江東文化財より)
 <深川江戸資料館> <深川江戸資料館>
司馬遼太郎は深川江戸資料館についても書いています。「「深川江戸資料館」 というのである。そこに、江戸時代の深川の町家のむれが、路地・掘割ごと、いわば界隈ぐるみ構築され、再現されており、吹抜けの三階からみれば屋根ぐるみ見えるし、また階下におりれば、店先に立つこともできる。春米屋とその土蔵、八百屋、船宿から、各種の長屋もある。火の見櫓もそびえており、また掘割には猪牙舟もうかんでいる。水茶屋もあれば、屋台も出ており、すべて現寸大である。」、実際に深川江戸資料館に入ると、地下1階、地上2階の吹き抜けの中に、江戸天保時代(明治まで僅か20年)の(1842年)の江戸深川佐賀町下之橋の橋際一体を、そのままここに再現しています。深川佐賀町とは、先週の泉鏡花の「深川浅景」の中で紹介していますが、永代橋を越えて角の交番の所をすぐに左に曲がった所から清洲橋までの地域です。永代橋に近い所から下之橋、中之橋、上之橋とあり、ここで再現しています下之橋は首都高速9号線と交わる辺りです。当時の資料を元にして実物大のスケールで再現したのがこの深川江戸資料館で、階段を下りると深川佐賀町の表通り、左側に油問屋の大店(おおだな)、右側に長屋の裏木戸をはさんで八百屋と米屋が並んでいます、少し先に進むと船宿が2軒並び火の見やぐらに”いなり”や”天ぷら”の屋台など、クギ一本まで当時のままに再現されています。ここを見ずに深川を語るなかれですね。300円は安い!!
★左の写真の右側の建物が深川江戸資料館です。今回は車で訪問したのですが無料の駐車場がありました。深川江戸資料館の向こう側は有名な霊巌寺があります。往時ほどの境内をもっていませんが、境内の墓地には白河の地名の発祥になった白河候松平定信の墓もあります。
 <富岡八幡宮> <富岡八幡宮>
「深川が市街化しはじめるのは、三代将軍家光の寛永(1624〜1644)のころからである。長盛とやらいう法印が発願し、幕府の許可をえて富岡八幡宮を建てたことによる(富岡は、『江戸名所花暦』では富賀岡と表記されている。鎌倉の鶴岡八幡宮を意識してそうよばれていたのだろう)。この神社は誕生早々から江戸市民の関心をよび、寛永二十年(1643)には、はじめて祭礼がおこなわれた。その後、??深川の祭礼″ は江戸市民のたのしみの一つになった。当然ながら、門前に茶屋がならび、妓をかかえ、色をひさがせた。」、富岡八幡宮は江戸時代の”富くじ”と”勧進相撲”で有名ですが、現在では8月15日に開催されます”深川八幡祭り”が特に有名です。赤坂の日枝神社の山王祭、神田明神の神田祭とともに「江戸三大祭」の一つに数えられ、3年に1度、八幡宮の御鳳輦が渡御を行う年は本祭りと呼ばれ、大小あわせて120数基の町神輿が担がれ、その内大神興ばかり54基が勢揃いして連合渡御する様は「深川八幡祭り」ならではのものです。
★右の写真が富岡八幡宮の正面です。富岡八幡宮には元禄時代に豪商として名を馳せた紀伊国屋文左衛門が奉納したとされる総金張りの宮神輿が3基ありましたが関東大震災でも焼失しています。平成3年に日本―の黄金大神輿が奉納され宮神輿が復活しています。(富岡八幡宮ホームページより)
最後に川柳を一つ
「江戸っ子の 生まれぞこない かねをため」
深川付近地図
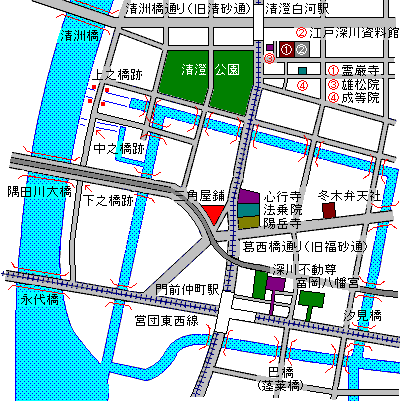
【参考文献】
・本所深川散歩・神田界隈:朝日文庫、司馬遼太郎
・江東区の文化財:江東区教育委員会
・江東区辞典:江東区教育委員会
・文人悪食:新潮文庫 嵐山光三郎
【交通のご案内】
・都営大江戸線「清澄白河駅」下車 徒歩3分
【住所紹介】
・成等院:東京都江東区三好1-6-13
・雄松院:東京都江東区白河1-1-8
・江東区深川江戸資料館:東京都江東区白河1−3−28 ?Z03-3630-8625
・富岡八幡宮ホームページ
|