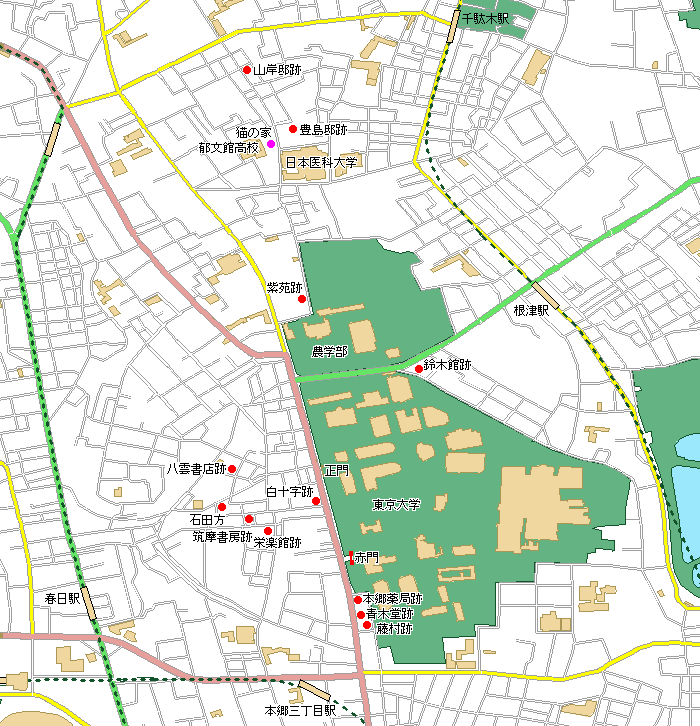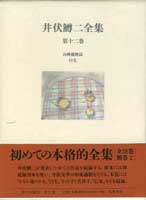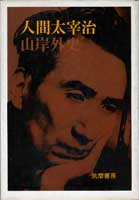<井伏鱒二全集>
太宰治の鎌滝時代については、井伏鱒二、山岸外史、長尾良の三人がそれぞれのおもいで書いています。井伏鱒二は「亡友 ―鎌滝のころ―」として、山岸外史は「人間
太宰治」の中で”鎌滝時代”として、長尾良は「太宰治」に書いています。この鎌滝時代はちょうど”小説家としての太宰治の変化点”ではなかったのかとおもいます。まず最初は井伏鱒二の「亡友 ―鎌滝のころ―」からです。
「…太宰の食客たちは、中畑さんと北さんが見まはりに行くと、女中の取次ぎをきいて逃げ出すのである。玄関と反対側の出入口から逃げ出して、やがて中畑・北の二人が帰ったころを見はからつて引返して来る。これは月に一回だけの行事だが、北さんは東京の人だから不時にやって来る。しかし北さんは私の裏切りを警成して、私のうちには寄らないで、いきなり鎌滝を訪ねて太宰の部屋にはひつて行く。……
…「いま、鎌滝に行ってみました。ところが貴方、どうでせう。修治さんは、窓に腰をかけて雑誌を読んでゐる。それはまあ、それでいいが、日中だといふのに寝床が敷いてある。その寝床に誰かしらぬが若い男が二人背中を向けあって寝てる始末だ。まあ、それはそれでもいいとして、厚紙の将棋盤をチャブ台にして、二人の賓客が酒をのんでる。何たることだね。これはどうしても、貴方にお頼みしたいのですがね。ときどき貴方が鎌滝に行って、居候がゐたら追ひかへして下さい。金を送れば、無駄づかひする。送らなければ、惰気こんで死ぬと云ったりする。やっぱし、これはどうしても居候を追ひ返して頂くことですな。」
私はその役目を辞退した。「そんなにまで、他人の生活に立ち入るつもりはない」と私は答へた。たとひ私が云っても、太宰の食客たちは私をせせら笑ふだけである。…」。
太宰の友人たちが、太宰の下宿「鎌滝」に朝から晩まで入り浸っています。中畑さんと北さんは津島家の番頭さんですから、津島家から依頼されて津島修治(太宰治)の監督にきているわけです。この後、井伏鱒二と番頭さんたちは、津島修治を見きれず、結婚させて奥様に監督させようと考えます。この第一候補が阿佐ヶ谷のピノチオという小料理の主人(二代目)の娘さんでしたが、結局、うまくいきませんでした。
★写真は筑摩書房板、井伏鱒二全集(12)です。「亡友 ―鎌滝のころ―」他の太宰治関連の記述が多く掲載されていました。定価は6千円ですが、古本ではかなり安く購入することが出来ます。一読の価値があります。

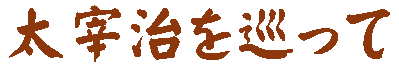
●太宰治の荻窪を歩く 鎌滝編
初版2009年4月4日
二版2009年4月19日
三版2009年7月1日 西荻の阿部合成を追加
四版2009年7月17日<V01L02> 「太宰と地平」を追加
二版2009年4月19日
三版2009年7月1日 西荻の阿部合成を追加
四版2009年7月17日<V01L02> 「太宰と地平」を追加
今回は「太宰治を巡って」の鎌滝編を掲載します。太宰治の鎌滝時代は今まで掲載しておりませんので、新規掲載となります。初代と離婚してから御坂峠の天下茶屋に移るまでの約一年三ヶ月間、昭和12年6月から昭和13年9月までの鎌滝に下宿していた期間です。
<人間太宰治 山岸外史>
鎌滝の下宿にたびたび訪ねていた友人の一人が山岸外史てす。でも山岸外史は井伏鱒二には信頼されていたようです。この頃の山岸外史は本郷の千駄木に住んでおり、太宰治も時折訪ねていたようです。山岸外史の「人間太宰治」には”鎌滝時代”として詳細に書かれています。
「…「壁の衣紋かけに、ただ、中味のない羽織がぶらさがっているようなものなんだ」
この言葉を太宰が、この四等下宿の鎌滝のひどく古びた四畳半の室でいったことがあるが、壁にさがっている羽織を坐ったままの恰好でちょいと拇さした。肩だけ怒らして中身なしにぶら下っているその羽織の説明を、ぼくは、太
宰は例によって巧い言い方を知っていると思いながら闘いていたものである。……
…この下宿というのは、たしかにひどく古くなった下宿で、太宰の住んだことのある室のなかでは最もわびしい室であった。それまで初代さんといた碧雲荘は、それでも小さいながらアパートで、室も八畳だったとおぼえているが、鎌滝下宿は、なぜ、こんな下宿に転居したのかと思われるくらいひどい下宿だった。廊下の板もきしむし、襖のあけたてもガタガタしていた。隙間だらけであった。年数がひどく経っている家だった。室数は二階と階下で十室くらいあったように思う。…」
”壁の衣紋かけに、ただ、中味のない羽織がぶらさがっているようなものなんだ”とは旨いことを言います。さすがに後の人気作家です。こうゆう表現が太宰治は旨いのです。この一年三ヶ月間の鎌滝時代が物書きになる変化点だったのでしょう。それにしてもこの鎌滝下宿は、ひどい下宿だったようです。この友人たちは食事もこの鎌滝下宿ですましており、食事代は全て太宰治が負担していたようです。
★写真は筑摩書房版、山岸外史の「人間太宰治」です。山岸外史は太宰と最も近い友人の一人だったとおもいます。奥様の美智子さんに「山岸さんがいれば、太宰は死ななかった」と言わせしめた友人でした。
鎌滝の下宿にたびたび訪ねていた友人の一人が山岸外史てす。でも山岸外史は井伏鱒二には信頼されていたようです。この頃の山岸外史は本郷の千駄木に住んでおり、太宰治も時折訪ねていたようです。山岸外史の「人間太宰治」には”鎌滝時代”として詳細に書かれています。
「…「壁の衣紋かけに、ただ、中味のない羽織がぶらさがっているようなものなんだ」
この言葉を太宰が、この四等下宿の鎌滝のひどく古びた四畳半の室でいったことがあるが、壁にさがっている羽織を坐ったままの恰好でちょいと拇さした。肩だけ怒らして中身なしにぶら下っているその羽織の説明を、ぼくは、太
宰は例によって巧い言い方を知っていると思いながら闘いていたものである。……
…この下宿というのは、たしかにひどく古くなった下宿で、太宰の住んだことのある室のなかでは最もわびしい室であった。それまで初代さんといた碧雲荘は、それでも小さいながらアパートで、室も八畳だったとおぼえているが、鎌滝下宿は、なぜ、こんな下宿に転居したのかと思われるくらいひどい下宿だった。廊下の板もきしむし、襖のあけたてもガタガタしていた。隙間だらけであった。年数がひどく経っている家だった。室数は二階と階下で十室くらいあったように思う。…」
”壁の衣紋かけに、ただ、中味のない羽織がぶらさがっているようなものなんだ”とは旨いことを言います。さすがに後の人気作家です。こうゆう表現が太宰治は旨いのです。この一年三ヶ月間の鎌滝時代が物書きになる変化点だったのでしょう。それにしてもこの鎌滝下宿は、ひどい下宿だったようです。この友人たちは食事もこの鎌滝下宿ですましており、食事代は全て太宰治が負担していたようです。
★写真は筑摩書房版、山岸外史の「人間太宰治」です。山岸外史は太宰と最も近い友人の一人だったとおもいます。奥様の美智子さんに「山岸さんがいれば、太宰は死ななかった」と言わせしめた友人でした。
<太宰治 長尾良>
”鎌滝の下宿に朝から晩まで入り浸っている居候”と井伏鱒二に言われた友人たちの一人がこの長尾良です。あとの二人は緑川貢と塩月赳です。塩月赳は太宰治の「佳日」のモデルなっていて有名です。太宰治が入水自殺する少し前に亡くなっています。今回は長尾良の「太宰治」を参考にしながら、杉並や本郷を歩いてみました。
「昭和十三年の六月の初め、私は荻窪の沓掛町にいた河村の屋敷の前に立っていた。
河村は母方の親戚で、西ノ宮の大地主であったが、昨年、子供の教育のために東京に引越しできたとは聞いていた。しかし、私が河村を訪ねるのは初めてであった。
私は一通のハガキを持っていた。…」
長尾良の「太宰治」の書き出しです。長尾良は当時東京帝国大学の学生で、どうゆう分けか、荻窪駅から北に400〜500mのところに下宿していました。上記は親類の家を訪ねるところです。
★写真は宮川書房板の「太宰治」です。この本は新書版で、元々は「太宰治その人と」のタイトルで出版したものを新書版で再出版したものです。居候として、太宰治との付き合いを詳細に書いています。非常におもしろい読み物です。
”鎌滝の下宿に朝から晩まで入り浸っている居候”と井伏鱒二に言われた友人たちの一人がこの長尾良です。あとの二人は緑川貢と塩月赳です。塩月赳は太宰治の「佳日」のモデルなっていて有名です。太宰治が入水自殺する少し前に亡くなっています。今回は長尾良の「太宰治」を参考にしながら、杉並や本郷を歩いてみました。
「昭和十三年の六月の初め、私は荻窪の沓掛町にいた河村の屋敷の前に立っていた。
河村は母方の親戚で、西ノ宮の大地主であったが、昨年、子供の教育のために東京に引越しできたとは聞いていた。しかし、私が河村を訪ねるのは初めてであった。
私は一通のハガキを持っていた。…」
長尾良の「太宰治」の書き出しです。長尾良は当時東京帝国大学の学生で、どうゆう分けか、荻窪駅から北に400〜500mのところに下宿していました。上記は親類の家を訪ねるところです。
★写真は宮川書房板の「太宰治」です。この本は新書版で、元々は「太宰治その人と」のタイトルで出版したものを新書版で再出版したものです。居候として、太宰治との付き合いを詳細に書いています。非常におもしろい読み物です。
<鎌滝への道>
長尾良は太宰治の鎌滝下宿を探すのに苦労しています。
「…今日は鎌滝の在りかぐらい探しておこうと、番地の数の増して行く東の方に向って、二軒二軒、表札の番地を覗きながら、歩いて行った。
二一〇番地になったとき、道路の左側に垣根のある広い屋敷があった。夕霧が漂っている暗いひいらぎの生垣に、白い花が二つ三つ、ぼっ、ぼっと浮んでいた。垣根の隙間から覗くと、庭には夏草が茫々と茂っていた。その中に、工員寮か、鉄道員の寮のような、鍵形になった大きい二階家が空家のようにひっそりと鎮まり返っていた。…」。
昔は表札の横に住所を書いていたとおもいます。当時は住居表記のラベルなどは無かったわけです。
★写真は四面道交差点から荻窪駅方面に青梅街道を150m程歩いた北側の路地入口です。上記に書かれた天沼一丁目二一〇番地は写真路地入口の左側になります。この路地をまっすぐに100m歩くと左側が鎌滝下宿跡となります。
長尾良は太宰治の鎌滝下宿を探すのに苦労しています。
「…今日は鎌滝の在りかぐらい探しておこうと、番地の数の増して行く東の方に向って、二軒二軒、表札の番地を覗きながら、歩いて行った。
二一〇番地になったとき、道路の左側に垣根のある広い屋敷があった。夕霧が漂っている暗いひいらぎの生垣に、白い花が二つ三つ、ぼっ、ぼっと浮んでいた。垣根の隙間から覗くと、庭には夏草が茫々と茂っていた。その中に、工員寮か、鉄道員の寮のような、鍵形になった大きい二階家が空家のようにひっそりと鎮まり返っていた。…」。
昔は表札の横に住所を書いていたとおもいます。当時は住居表記のラベルなどは無かったわけです。
★写真は四面道交差点から荻窪駅方面に青梅街道を150m程歩いた北側の路地入口です。上記に書かれた天沼一丁目二一〇番地は写真路地入口の左側になります。この路地をまっすぐに100m歩くと左側が鎌滝下宿跡となります。
<杉並区天沼一丁目二一三番地 鎌滝方>
太宰治が昭和12年6月から13年9月まで下宿した鎌滝方です。長尾良の「太宰治」からです。
「…玄関のすぐ前にある階段を上って行くと、暗い廊下に沿って、小さい部屋がいくつも竝んでいた。少女の言った階段の右側を見ると、電灯の点っている部屋が二つあった。そして、階段に近い、手前の方の部屋は襖の戸が半分ばかり開いていて、部屋の明りが暗い廊下に流れ出ていた。何となく、この部屋が太宰の部屋のような気がした。私はそっと廊下を歩いて行った。そして、開いている襖の蔭から、部屋の中を覗いた。っていた。太宰は以前には共産党の党員だったから、何か秘密謀議でも擬しているのかとさえ思ったほどであった。部屋の中に入るのが躇われた。だから、廊下から部屋の内を覗きながら、「太宰さんの部屋は、ここでしょうか」と、訊ねてみた。
返事は、すぐ、
「はい。ここですよ。どうぞ」
入口から見て、真正面に坐っている。黒いロイド眼鏡の男が答えた。頭は禿げていたが、学生服の黒いズボンをはいており太宰よりも年長とは思えなかった。
しかし、三人とも相変らず、下を見凝めたまま、誰も私の方に目をやる者はいなかった。未知の訪問者に馴れているのだろうと思った。
「失礼します」
こう言って、私は部屋の中に入って行った。…」。
ここに書かれている太宰治を除いた二人は緑川貴と塩月赳です。又、書いている人によって鎌滝の下宿の様子が少し違います。井伏鱒二は下宿の広さを八畳程と書いていますが、長尾良は四畳半とも書いています。ひどい下宿だったのは共通していますね!!
★写真は当時の番地で杉並区天沼一丁目二一三番地の鎌滝方です。現在はアパートと言うのか、マンションなのかはわかりせんが、三階建ての立派な建物になっていました。
太宰治が昭和12年6月から13年9月まで下宿した鎌滝方です。長尾良の「太宰治」からです。
「…玄関のすぐ前にある階段を上って行くと、暗い廊下に沿って、小さい部屋がいくつも竝んでいた。少女の言った階段の右側を見ると、電灯の点っている部屋が二つあった。そして、階段に近い、手前の方の部屋は襖の戸が半分ばかり開いていて、部屋の明りが暗い廊下に流れ出ていた。何となく、この部屋が太宰の部屋のような気がした。私はそっと廊下を歩いて行った。そして、開いている襖の蔭から、部屋の中を覗いた。っていた。太宰は以前には共産党の党員だったから、何か秘密謀議でも擬しているのかとさえ思ったほどであった。部屋の中に入るのが躇われた。だから、廊下から部屋の内を覗きながら、「太宰さんの部屋は、ここでしょうか」と、訊ねてみた。
返事は、すぐ、
「はい。ここですよ。どうぞ」
入口から見て、真正面に坐っている。黒いロイド眼鏡の男が答えた。頭は禿げていたが、学生服の黒いズボンをはいており太宰よりも年長とは思えなかった。
しかし、三人とも相変らず、下を見凝めたまま、誰も私の方に目をやる者はいなかった。未知の訪問者に馴れているのだろうと思った。
「失礼します」
こう言って、私は部屋の中に入って行った。…」。
ここに書かれている太宰治を除いた二人は緑川貴と塩月赳です。又、書いている人によって鎌滝の下宿の様子が少し違います。井伏鱒二は下宿の広さを八畳程と書いていますが、長尾良は四畳半とも書いています。ひどい下宿だったのは共通していますね!!
★写真は当時の番地で杉並区天沼一丁目二一三番地の鎌滝方です。現在はアパートと言うのか、マンションなのかはわかりせんが、三階建ての立派な建物になっていました。
<盛山館>
長尾良は荻窪駅北側の下宿から、光明院裏の下宿に変わります。この下宿については長尾良は太宰治が一時下宿していたと書いています。
「…七月の終わり頃であったか、四面道の交差点から南の踏切の方へ、砂利道をぶらぶらと降りていった。……
…三叉路に来て、どちらに行こうかと、ふと顔を上げたとき、玄関脇のヒマラヤ杉に白いボール紙が引っ懸ったように下がっていた。見ると、細い墨で、「空室アリマス、盛山館」と、書いてあった。……
…苗字が倉股という奇妙な名前では、下宿屋では都合が悪いので、何かいい屋号をつけたらと思って、姓名判断の占い師に頼んだところ、盛山館とつけてくれた、…」。
上記には下宿名が「盛山館」と書かれています。この下宿の名前で探してみたのですが、見つからず、「苗字が倉股」で探してみました。すると、光明院裏近くに「倉股」を見つけることが出来ました。太宰治は昭和11年11月に光明院裏の照山荘アパートに二、三日宿泊しています。長尾良は太宰治自信が”この下宿に宿泊したと言っている”と書いています。”照山荘アパート”の名前が出てくるのは井伏鱒二の「十年前後 ――太宰治に関する雑用事――」です。「照山荘(しょうざんそう)」と「盛山館(せいざんかん)」、下宿(アパート)の名前としては、発音は似ているようです。どちらが正しいのかは分かりません。地図を見て探しましたが、どちらの名前のアパート(下宿)も見つけることが出来ませんでした。ただ、「苗字が倉股」の住居は見つけることが出来ました。普通は余り見かけない名字なので間違いはないとおもいます。
★正面のマンションのところが「苗字が倉股」の住居跡です。光明院からは北に二筋目です。場所的にも丁度いいところです。
長尾良は荻窪駅北側の下宿から、光明院裏の下宿に変わります。この下宿については長尾良は太宰治が一時下宿していたと書いています。
「…七月の終わり頃であったか、四面道の交差点から南の踏切の方へ、砂利道をぶらぶらと降りていった。……
…三叉路に来て、どちらに行こうかと、ふと顔を上げたとき、玄関脇のヒマラヤ杉に白いボール紙が引っ懸ったように下がっていた。見ると、細い墨で、「空室アリマス、盛山館」と、書いてあった。……
…苗字が倉股という奇妙な名前では、下宿屋では都合が悪いので、何かいい屋号をつけたらと思って、姓名判断の占い師に頼んだところ、盛山館とつけてくれた、…」。
上記には下宿名が「盛山館」と書かれています。この下宿の名前で探してみたのですが、見つからず、「苗字が倉股」で探してみました。すると、光明院裏近くに「倉股」を見つけることが出来ました。太宰治は昭和11年11月に光明院裏の照山荘アパートに二、三日宿泊しています。長尾良は太宰治自信が”この下宿に宿泊したと言っている”と書いています。”照山荘アパート”の名前が出てくるのは井伏鱒二の「十年前後 ――太宰治に関する雑用事――」です。「照山荘(しょうざんそう)」と「盛山館(せいざんかん)」、下宿(アパート)の名前としては、発音は似ているようです。どちらが正しいのかは分かりません。地図を見て探しましたが、どちらの名前のアパート(下宿)も見つけることが出来ませんでした。ただ、「苗字が倉股」の住居は見つけることが出来ました。普通は余り見かけない名字なので間違いはないとおもいます。
★正面のマンションのところが「苗字が倉股」の住居跡です。光明院からは北に二筋目です。場所的にも丁度いいところです。
<太宰と地平>
2009年7月17日 「太宰と地平」を追加
”鎌滝の下宿に朝から晩まで入り浸っている居候”と井伏鱒二に言われた友人たちの住まいを歩いてみました。森永国男の「太宰と地平」の中にヒントが書かれていました。森永国男の「太宰と地平」からです。
「…この「鎌滝の時代」 の年譜で、取巻き連の主役に上げられている三名の中では、塩月赳は、別格で、大学は一年先輩であるが歳は、太宰と同年である。太宰との付合も昭和八年二月の同人誌『海豹』 の第一回同人会からと思われる。緑川貢は、檀一雄とのつながりで、太宰の碧雲荘で何度か会っているが、親しくなったのは、鎌滝に移ってからの十二年八月末頃からである。長尾良は、「鎌滝の時代」も終ろうという昭和十三年七月から九月十三日までの二ケ月の付合である。
太宰の取巻きという言葉で思い出すのは、山岸と太宰との絶交問題である。山岸は、前後十四年に亘る太宰との交友の中で、絶交しようと考えたことが三回あるという。その最初の絶交状を送ったのが、昭和十二年の「鎌滝の時代」 のころで、太宰が一部の人々から注目されかけたころである。…」
山岸外史は下記に掲載しましたので、残っているのは塩月赳、緑川貢と長尾良になります。今回は塩月赳と緑川貢を歩きます。
★写真は森永国男の「太宰と地平」です。昭和60年発行ですから太宰が亡くなってからかなり時間が経過してから書いたようです。
2009年7月17日 「太宰と地平」を追加
”鎌滝の下宿に朝から晩まで入り浸っている居候”と井伏鱒二に言われた友人たちの住まいを歩いてみました。森永国男の「太宰と地平」の中にヒントが書かれていました。森永国男の「太宰と地平」からです。
「…この「鎌滝の時代」 の年譜で、取巻き連の主役に上げられている三名の中では、塩月赳は、別格で、大学は一年先輩であるが歳は、太宰と同年である。太宰との付合も昭和八年二月の同人誌『海豹』 の第一回同人会からと思われる。緑川貢は、檀一雄とのつながりで、太宰の碧雲荘で何度か会っているが、親しくなったのは、鎌滝に移ってからの十二年八月末頃からである。長尾良は、「鎌滝の時代」も終ろうという昭和十三年七月から九月十三日までの二ケ月の付合である。
太宰の取巻きという言葉で思い出すのは、山岸と太宰との絶交問題である。山岸は、前後十四年に亘る太宰との交友の中で、絶交しようと考えたことが三回あるという。その最初の絶交状を送ったのが、昭和十二年の「鎌滝の時代」 のころで、太宰が一部の人々から注目されかけたころである。…」
山岸外史は下記に掲載しましたので、残っているのは塩月赳、緑川貢と長尾良になります。今回は塩月赳と緑川貢を歩きます。
★写真は森永国男の「太宰と地平」です。昭和60年発行ですから太宰が亡くなってからかなり時間が経過してから書いたようです。
<松嵐荘>
2009年7月17日 「太宰と地平」を追加
太宰の取り巻きの緑川貢からです。森永国男の「太宰と地平」には下記のように書かれていました。
「…緑川は荻窪の松嵐荘に移り住んだ。太宰の鎌滝とは目と鼻の先である。以来、緑川の太宰通いは繁しくなるのである。…」。
緑川貢が”荻窪の松嵐荘”移り住んだ時期は、昭和12年8月頃のようです。檀一雄が召集を受けた時期(昭和12年7月)と重なっていますで、間違いないとおもいます。
★写真の左側に”荻窪の松嵐荘”がありました。当時の地図にも”松嵐荘”と記載されていましたので間違いないとおもいます。”鎌滝”のすぐ傍になります。戦後も”松嵐荘”があり、最近の地図にも掲載されていました。
太宰の取り巻きの緑川貢からです。森永国男の「太宰と地平」には下記のように書かれていました。
「…緑川は荻窪の松嵐荘に移り住んだ。太宰の鎌滝とは目と鼻の先である。以来、緑川の太宰通いは繁しくなるのである。…」。
緑川貢が”荻窪の松嵐荘”移り住んだ時期は、昭和12年8月頃のようです。檀一雄が召集を受けた時期(昭和12年7月)と重なっていますで、間違いないとおもいます。
★写真の左側に”荻窪の松嵐荘”がありました。当時の地図にも”松嵐荘”と記載されていましたので間違いないとおもいます。”鎌滝”のすぐ傍になります。戦後も”松嵐荘”があり、最近の地図にも掲載されていました。
<慶山房>
2009年7月17日 「太宰と地平」を追加
次に塩月赳です。荻窪駅を挟んで鎌滝の反対側になります。森永国男の「太宰と地平」には下記のように書かれていました。
「…実母の死は、赳にも一つの転機になったのか、それは、丁度、「鎌滝の時代」でもあり、赳も、小さな雑誌社「政界往来」を経て、「東洋経済新報社」に入社した。母の死後、彼は、杉並区荻窪三ノ二〇二慶山房に移った。…」。
塩月赳が転居してきた時期は、昭和12年9月に母親が亡くなっていますので、10月頃かなとおもっています。
★写真の左側のマンションの所が杉並区荻窪三ノ二〇二です。正確には角から右に二軒目だったのですが、現在は一つのマンションになっています。右側は桜井第二小学校です。
次に塩月赳です。荻窪駅を挟んで鎌滝の反対側になります。森永国男の「太宰と地平」には下記のように書かれていました。
「…実母の死は、赳にも一つの転機になったのか、それは、丁度、「鎌滝の時代」でもあり、赳も、小さな雑誌社「政界往来」を経て、「東洋経済新報社」に入社した。母の死後、彼は、杉並区荻窪三ノ二〇二慶山房に移った。…」。
塩月赳が転居してきた時期は、昭和12年9月に母親が亡くなっていますので、10月頃かなとおもっています。
★写真の左側のマンションの所が杉並区荻窪三ノ二〇二です。正確には角から右に二軒目だったのですが、現在は一つのマンションになっています。右側は桜井第二小学校です。
太宰治の荻窪地図
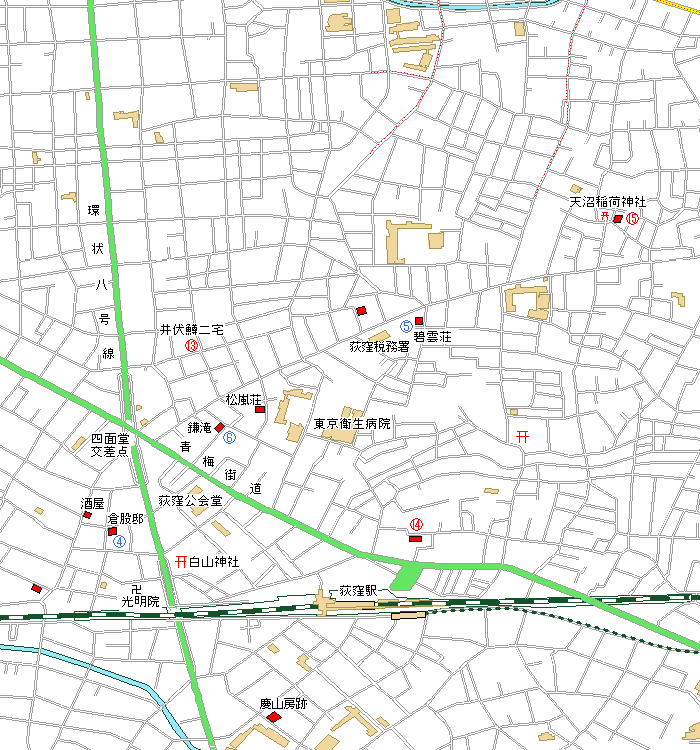
太宰治年表
| 和 暦 | 西暦 | 年 表 | 年齢 | 太宰治の足跡 |
| 昭和11年 | 1936 | 2.26事件 | 28 | 2月中旬 芝済生会病院に入院 8月群馬県谷川温泉 川久保屋に宿泊 10月13日 江古田の東京武蔵野病院に入院 11月12日 杉並区荻窪の光明院裏の照山荘アパートに転居 11月15日 天沼一丁目238番地の碧雲荘に転居 |
| 昭和12年 | 1937 | 蘆溝橋で日中両軍衝突 | 29 | 3月下旬 群馬県谷川温泉 川久保屋に宿泊 6月 初代と離婚成立 6月21日 天沼一丁目213の鎌滝方に転居 |
| 昭和13年 | 1938 | 関門海底トンネルが貫通 岡田嘉子ソ連に亡命 「モダン・タイムス」封切 |
30 | 9月13日 杉並区天沼から御坂峠の天下茶屋に転居 9月18日 石原美智子とお見合い 11月6日 太宰、石原美智子と婚約 11月 甲府市西竪町の寿館に下宿 |
|
昭和14年
|
1939 | ドイツ軍ポーランド進撃 | 31 | 1月8日 杉並の井伏鱒二宅で太宰、石原美智子と結婚式をあげる。甲府の御崎町に転居 9月1日 東京府三鷹村下連雀百十三番地に転居 |
| 昭和17年 | 1942 | ミッドウェー海戦 | 34 | 12月 今官一が三鷹町上連雀山中南97番地に転居 |
| 昭和19年 | 1944 | マリアナ海戦敗北 東条内閣総辞職 レイテ沖海戦 神風特攻隊出撃 |
36 | 1月10日 上野駅でスマトラに向かう戸石泰一と面会 |
| 昭和20年 | 1945 | ソ連参戦 ポツダム宣言受諾 |
37 | 4月 三鷹から妻美智子の実家、甲府市水門町に疎開 7月28日 津軽に疎開 |
<ピノチオ>
2009年4月19日 ピノチオを追加
昭和12年、初代と離婚してから昭和14年1月に美智子さんと結婚するまでに、お見合いの話が無かったわけではありません。井伏鱒二の「亡友 ―鎌滝のころ―」からです。
「…そのころ私は阿佐ヶ谷のピノチオといふ小料理の主人と懇意にして、しげしげその店を訪ねてゐた。…
…或る日この店でビールを飲んでゐると、おかみさんが大型の写真を出して来て私に見せた。おかみさんの長女の写真だが、誰でもいいから、小説家志望または劇作家志望の青年に、娘をやりたいとおかみさんが云つた。次女の縁談がまとまったので、長女の方の話を急いでゐたのである。
私は太宰のことを対象に考へて、おかみさんにかう云った。
「誰でもいいと云ふのは、ほんとに誰でもいいことだね。再縁する人でもいいのだね。」
店の主人もそこにやって来て、
「よろしくお願ひいたします。無論、どなたでも結構です。妙な云ひかたですが、後がつかへてゐるから、急ぐのです。」
と云つた。
私は新聞紙をもらって写真を包んだ。太宰も結婚が出来るぞと私は思った。
「いま当人の名前は云はないが、当人もきつと承諾するだらう。では、前祝ひだ、大いに飲まう。青柳瑞穂を呼んで来てくれ。但し、青柳君にはまだ秘密だ。」
主人は料理の出前をするので青柳君のうちを知ってゐた。自転車で駆けつけてくれた。
翌日、太宰の下宿へ行く途中、私のうちへ来る太宰に遭った。私は新聞紙の包みを太宰に手渡して、
「下宿に帰ってから、中味を見てくれないか。妙齢の子女の肖像だ。君がお嫁さんに貰ひたい気が起ったら、貰ひたいと云つてくれ。」…」。
太宰治は井伏鱒二から紹介された阿佐ヶ谷「ピノチオ」の長女の話を受けることにします。しかし、井伏鱒二がピノチオの夫婦に太宰治から了解を得た話を持って行くと、断られてしまいます。もっといい話がきていたようです。結局、太宰治はふられたことになりました。
★写真正面左の東急のところに阿佐ヶ谷「ピノチオ」がありました。詳細は下記の地図を参照してください。赤いところが「ピノチオ」跡です。下記の地図は、昭和12年の阿佐ヶ谷駅前地図に、現在の地図を重ねたものです。昭和12年の地図がイマイチ正確でないため、重ねるとピッタリ合いません。又、区画整理で中杉通りが広がって道の両側の家が削られています(特に杉並第一小学校側が削られてお店が無くなっています)
昭和12年、初代と離婚してから昭和14年1月に美智子さんと結婚するまでに、お見合いの話が無かったわけではありません。井伏鱒二の「亡友 ―鎌滝のころ―」からです。
「…そのころ私は阿佐ヶ谷のピノチオといふ小料理の主人と懇意にして、しげしげその店を訪ねてゐた。…
…或る日この店でビールを飲んでゐると、おかみさんが大型の写真を出して来て私に見せた。おかみさんの長女の写真だが、誰でもいいから、小説家志望または劇作家志望の青年に、娘をやりたいとおかみさんが云つた。次女の縁談がまとまったので、長女の方の話を急いでゐたのである。
私は太宰のことを対象に考へて、おかみさんにかう云った。
「誰でもいいと云ふのは、ほんとに誰でもいいことだね。再縁する人でもいいのだね。」
店の主人もそこにやって来て、
「よろしくお願ひいたします。無論、どなたでも結構です。妙な云ひかたですが、後がつかへてゐるから、急ぐのです。」
と云つた。
私は新聞紙をもらって写真を包んだ。太宰も結婚が出来るぞと私は思った。
「いま当人の名前は云はないが、当人もきつと承諾するだらう。では、前祝ひだ、大いに飲まう。青柳瑞穂を呼んで来てくれ。但し、青柳君にはまだ秘密だ。」
主人は料理の出前をするので青柳君のうちを知ってゐた。自転車で駆けつけてくれた。
翌日、太宰の下宿へ行く途中、私のうちへ来る太宰に遭った。私は新聞紙の包みを太宰に手渡して、
「下宿に帰ってから、中味を見てくれないか。妙齢の子女の肖像だ。君がお嫁さんに貰ひたい気が起ったら、貰ひたいと云つてくれ。」…」。
太宰治は井伏鱒二から紹介された阿佐ヶ谷「ピノチオ」の長女の話を受けることにします。しかし、井伏鱒二がピノチオの夫婦に太宰治から了解を得た話を持って行くと、断られてしまいます。もっといい話がきていたようです。結局、太宰治はふられたことになりました。
★写真正面左の東急のところに阿佐ヶ谷「ピノチオ」がありました。詳細は下記の地図を参照してください。赤いところが「ピノチオ」跡です。下記の地図は、昭和12年の阿佐ヶ谷駅前地図に、現在の地図を重ねたものです。昭和12年の地図がイマイチ正確でないため、重ねるとピッタリ合いません。又、区画整理で中杉通りが広がって道の両側の家が削られています(特に杉並第一小学校側が削られてお店が無くなっています)
阿佐ヶ谷のピノチオ地図
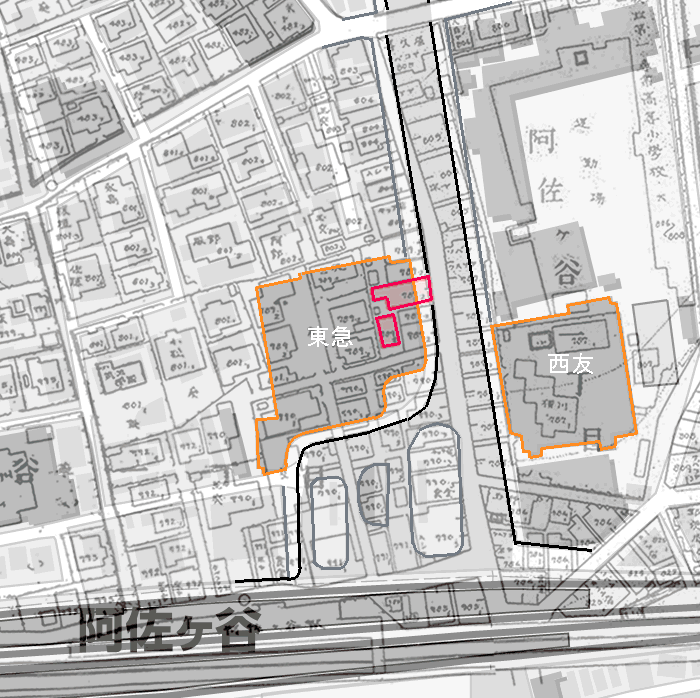
<西荻の阿部合成>
2009年7月1日 西荻の阿部合成を追加
阿部合成は昭和12年7月、杉並区大宮前にアトリエを建てます (腹違いの兄が土地を買ってくれた)。太宰が鎌滝に引っ越したのが昭和12年6月ですから、丁度重なります。鎌滝から大宮前のアトリエまで直線で1.6Km、歩いて30分程ですから二人はよく合っていたとおもいます。
「…「昭和十二年に西荻窪に私どもが移り住んだ頃から、太宰さんとのおつきあいが繁しくなりました。その頃太宰さんは初代夫人と別れられて、一人で杉並の天沼の方に住んでおられ、さびしい自由の中で安定を失いかけておられたようです。歩いてこられる距離もあって、来だすとそれが続き、いつ来ていつ帰ったのか遠慮深い方なのでいつもこそこそ、出たり入ったりの時期がしばらくございました。 (中略)
ある空白を経て逢った二人は、一人のときはまことにやさしい気の弱い人たちなのに、二人になると俄然自信がつき、三倍位の力がでてきたようです。かねてから津軽言葉のひけめももっていましたから、”光は北方より”などとわめいて、破滅型の下地を着々と歩きはじめていたように思われます。」…」
と阿部合成の前夫人である阿部なをさんは合成と太宰の再会を書いています。 (注 阿部なを 『紅』‥P2太宰治さんと私)。
出典は梅原猛の「阿部合成と太宰治」からです。阿部合成の名前を初めて聴く方のために、”阿部合成は太宰治と青森中学校の同級生で、山岸外史と三人トリオ”となっていました。
★写真の少し先の右側辺りと推定しています。当時の地番で杉並区大宮前六丁目427番地なのですが、この付近一帯が427番地なので、番地からは詳細の場所は分かりませんでした。ただ、”細長い土地に建てたアトリエ”との事なので、推定しました。
阿部合成は昭和12年7月、杉並区大宮前にアトリエを建てます (腹違いの兄が土地を買ってくれた)。太宰が鎌滝に引っ越したのが昭和12年6月ですから、丁度重なります。鎌滝から大宮前のアトリエまで直線で1.6Km、歩いて30分程ですから二人はよく合っていたとおもいます。
「…「昭和十二年に西荻窪に私どもが移り住んだ頃から、太宰さんとのおつきあいが繁しくなりました。その頃太宰さんは初代夫人と別れられて、一人で杉並の天沼の方に住んでおられ、さびしい自由の中で安定を失いかけておられたようです。歩いてこられる距離もあって、来だすとそれが続き、いつ来ていつ帰ったのか遠慮深い方なのでいつもこそこそ、出たり入ったりの時期がしばらくございました。 (中略)
ある空白を経て逢った二人は、一人のときはまことにやさしい気の弱い人たちなのに、二人になると俄然自信がつき、三倍位の力がでてきたようです。かねてから津軽言葉のひけめももっていましたから、”光は北方より”などとわめいて、破滅型の下地を着々と歩きはじめていたように思われます。」…」
と阿部合成の前夫人である阿部なをさんは合成と太宰の再会を書いています。 (注 阿部なを 『紅』‥P2太宰治さんと私)。
出典は梅原猛の「阿部合成と太宰治」からです。阿部合成の名前を初めて聴く方のために、”阿部合成は太宰治と青森中学校の同級生で、山岸外史と三人トリオ”となっていました。
★写真の少し先の右側辺りと推定しています。当時の地番で杉並区大宮前六丁目427番地なのですが、この付近一帯が427番地なので、番地からは詳細の場所は分かりませんでした。ただ、”細長い土地に建てたアトリエ”との事なので、推定しました。
太宰治の西荻窪地図
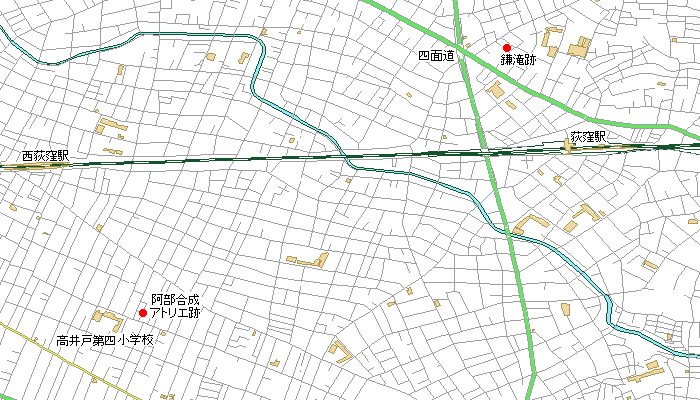
< 豊島寓>
豊島寓>
荻窪から少し離れて、長尾良が太宰治に連れられて本郷の豊島与志雄宅を訪ねた時のことを書いていますので、そのまま歩いてみました。
「…正午過ぎに鎌滝を出て、荻窪駅から省線に乗った。電車の座席に坐ると、太宰は懐から「文章世界」という明治時代の古雑誌を出して読み出したので、別段に話はしなかった。御茶ノ水で省線を降り、そこから本郷の方へ歩いて行った。
山岸外史氏が本郷のアパートにいると言っていたから、多分山岸氏のところじゃないかと思った。
「山岸さんのところじゃないのか」と、訊ねてみた。
しかし、太宰は、
「いや、いや、さにあらず」と微笑うばかり。
大学の前をどんどん東に歩いて行って、農学部の柵に沿って右に曲った。
暫く行くと、太宰は突然立ち停って道路の真ん中で襟もとを直したり、帯を締め直したりし始めた。そして、身繕いが終ると、幾分硬直した姿勢で、しずしずと歩いて行き、正面のトタン葺きの平家の前で停った。ガラス障子の締っている門口に立って、いかにも恭々しい態度でベルを押した。
私は太宰から五、六歩離れて立っていたが、表札を見ると、「豊島寓」と書いてあって、どうも豊島与志雄氏の家であるらしかった。…」。
この日は残念ながら豊島与志雄氏は不在でした。豊島与志雄氏は後に「太宰治との一日」を書いています。時期的には戦後の事で、山崎富栄と太宰治が二人で訪ねてきたときのことが書かれています。
★右の写真は文京区千駄木の日本医科大学の西側の道です。夏目漱石の猫の家で有名です(写真の少し先右側)。豊島与志雄邸は本郷区千駄木五七番地で、現在の文京区千駄木一丁目2番です。写真の先を左に曲がった右側になります(直接の写真は控えさせて頂きました)。
荻窪から少し離れて、長尾良が太宰治に連れられて本郷の豊島与志雄宅を訪ねた時のことを書いていますので、そのまま歩いてみました。
「…正午過ぎに鎌滝を出て、荻窪駅から省線に乗った。電車の座席に坐ると、太宰は懐から「文章世界」という明治時代の古雑誌を出して読み出したので、別段に話はしなかった。御茶ノ水で省線を降り、そこから本郷の方へ歩いて行った。
山岸外史氏が本郷のアパートにいると言っていたから、多分山岸氏のところじゃないかと思った。
「山岸さんのところじゃないのか」と、訊ねてみた。
しかし、太宰は、
「いや、いや、さにあらず」と微笑うばかり。
大学の前をどんどん東に歩いて行って、農学部の柵に沿って右に曲った。
暫く行くと、太宰は突然立ち停って道路の真ん中で襟もとを直したり、帯を締め直したりし始めた。そして、身繕いが終ると、幾分硬直した姿勢で、しずしずと歩いて行き、正面のトタン葺きの平家の前で停った。ガラス障子の締っている門口に立って、いかにも恭々しい態度でベルを押した。
私は太宰から五、六歩離れて立っていたが、表札を見ると、「豊島寓」と書いてあって、どうも豊島与志雄氏の家であるらしかった。…」。
この日は残念ながら豊島与志雄氏は不在でした。豊島与志雄氏は後に「太宰治との一日」を書いています。時期的には戦後の事で、山崎富栄と太宰治が二人で訪ねてきたときのことが書かれています。
★右の写真は文京区千駄木の日本医科大学の西側の道です。夏目漱石の猫の家で有名です(写真の少し先右側)。豊島与志雄邸は本郷区千駄木五七番地で、現在の文京区千駄木一丁目2番です。写真の先を左に曲がった右側になります(直接の写真は控えさせて頂きました)。
< 山岸外史邸>
山岸外史邸>
太宰治と長尾良は豊島与志雄氏が不在だったため、近くに住む山岸外史宅を訪ねます。
「…「じゃ、山岸のところへ行ってみよう」
やはり千駄木町で、ほんの五、六分しか離れていない山岸外史氏のアパートに行ったが、階下の玄関の脇にある六畳の部屋には、ただ書き潰した原稿用紙が散乱しているだけであった。…」。
山岸外史は鎌滝の太宰治をたびたび訪ねていますが、太宰治も本郷の山岸外史を訪ねていたようです。山岸外史、太宰治とも東京帝国大学ですから、本郷界隈は勝手知ったる界隈だったはずです(山岸外史はちゃんと卒業しています)。
★正面の少し先の左側に本郷区千駄木五〇番地、山岸外史宅がありました。もっとも、奥様の実家で、自宅ではありませんでした。写真の道は上記の豊島与志雄宅の道と同じ道で、北に300m弱歩いたところです。
阿部合成も追加する予定です。
太宰治と長尾良は豊島与志雄氏が不在だったため、近くに住む山岸外史宅を訪ねます。
「…「じゃ、山岸のところへ行ってみよう」
やはり千駄木町で、ほんの五、六分しか離れていない山岸外史氏のアパートに行ったが、階下の玄関の脇にある六畳の部屋には、ただ書き潰した原稿用紙が散乱しているだけであった。…」。
山岸外史は鎌滝の太宰治をたびたび訪ねていますが、太宰治も本郷の山岸外史を訪ねていたようです。山岸外史、太宰治とも東京帝国大学ですから、本郷界隈は勝手知ったる界隈だったはずです(山岸外史はちゃんと卒業しています)。
★正面の少し先の左側に本郷区千駄木五〇番地、山岸外史宅がありました。もっとも、奥様の実家で、自宅ではありませんでした。写真の道は上記の豊島与志雄宅の道と同じ道で、北に300m弱歩いたところです。
阿部合成も追加する予定です。
太宰治の本郷地図