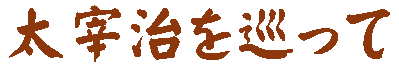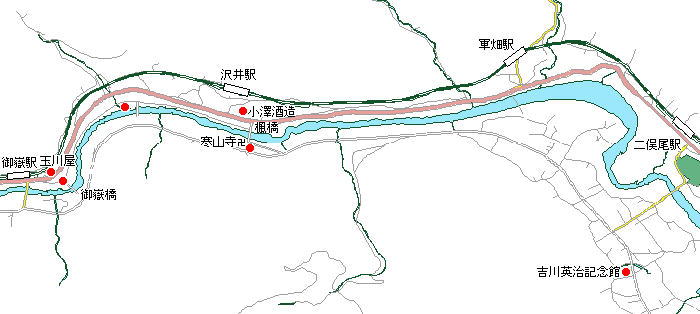「阿佐ヶ谷会」については、村上護の「阿佐ヶ谷文士村」が有名ですが、近年になって青柳いづみこさんが書かれた「青柳瑞穂の生涯」や、川本三郎氏と青柳いづみこさんが監修した「阿佐ヶ谷会文学アルバム」が相次いで出版されています。インターネットでも「阿佐ヶ谷会」について書かれているのも多く見かけます。ここでは太宰治を中心にした「阿佐ヶ谷会」を掲載したいとおもいます。まず最初は「阿佐ヶ谷会文学アルバム」の”あとがき”からです。
「あとがきにかえて
「新・阿佐ヶ谷会」縁起…
…過去七回の会の中で、とりわけ忘じがたいのは第三回(二〇〇三年六月二十八日)の”奥多摩篇”だろう。昭和十七年、阿佐ヶ谷文士たちが、奥多摩の御嶽にゆき、玉川屋という蕎麦屋で懇親会を開いたことが知られている。
玉川屋は今も健在。そこで、川本さん以下のわれわれ常連メンバーは、かつての奥多摩行と同様、十二時半、立川駅に集合。御嶽渓谷を散策し、玉川屋に向かった。…」。
”あとがき”から始まって申し訳け分けないのですが、今回のテーマである昭和17年の”御嶽”について書かれていましたので取り上げました。私と考えることは同じようです。この「阿佐ヶ谷会文学アルバム」は「阿佐ヶ谷会」のメンバーが「阿佐ヶ谷会」について書いたものを選んで集めた特集本になっています。少々お高い(3800円税別)ですが、一読の価値がありますので是非とも読んでいただきたいとおもいます。
★写真は幻戯書房板の「阿佐ヶ谷会文学アルバム」です。写真や阿佐ヶ谷の地図も掲載されています。「阿佐ヶ谷会」を知るには必読の一冊です。