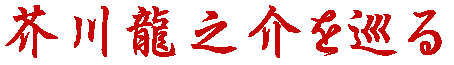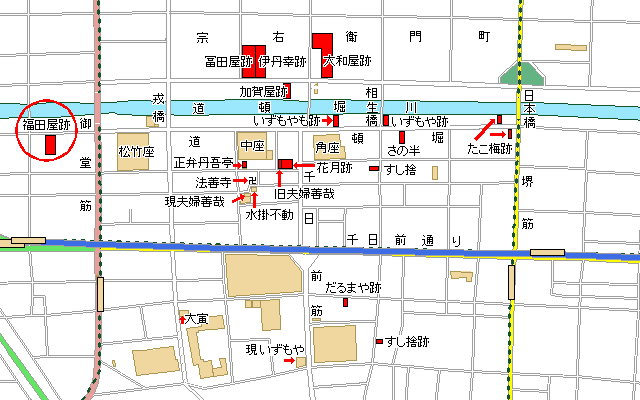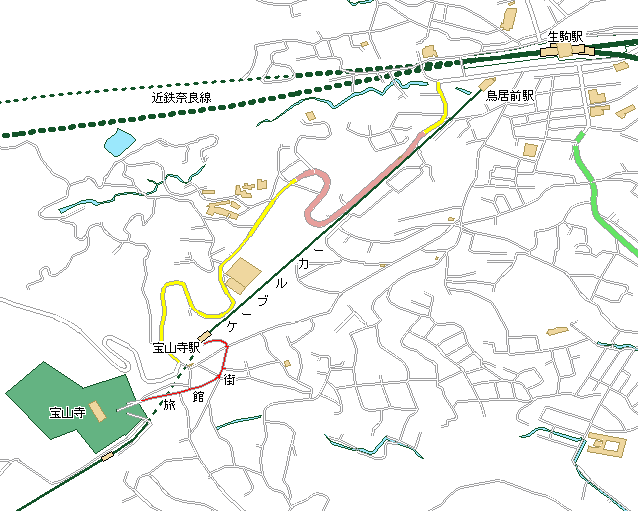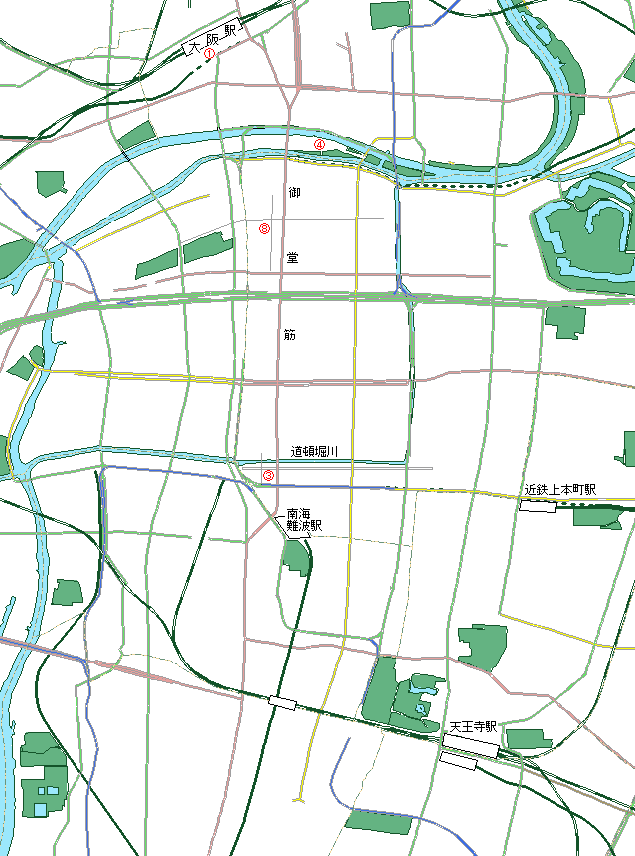今回の芥川龍之介の大阪訪問は大正9年です。「大阪の宿」を書いた水上龍太郎が大阪に転勤したのが大正6年、梶井基次郎が第三高等学校に入学したのが大正8年ですから、当時の大阪のイメージとしては何か分かります。「…京都から大阪までのあひだの二等車のなかは閑散であった。その時分の二等車は、今の都電や省線の電車のやうに、車の両側に座席がついてゐて、その座席もふかくクッションもやはらかく、座席や座席のあひだの通路もひろかった。 さて、汽車の中がすいてゐたので、私たち五人の連中は、すこしづつはなれて、腰をかけた。私たちが腰かけたのは河内の国のはうの側であったが、その反対の側には、汽車のすすんで行く方の隅に、市村羽左衛門(十五世羽左衛門)と五十あまりの女が、席を、しめ、反対の隅のはうに近い席に、『くろうと』らしい女が二人つつましく、腰を、かけてゐた。「……汽車にのる前に、ぼくは、見たんだが、羽左衛門は、まだ五十前だらうが、顔ぜんたい縮緬皺だね、あれは、白ろい粉のせゐだよ、」と、私が、いふと、「色の黒いのも、白粉のせゐだよ、」と、芥川が、いった。 その時、ふと、見ると、羽左衛門も、そのつれの女も、座席の上にすわつて、窓の外をながめながら、なにか、しきりに、話しあってゐた。「……あのつれの女は、細君ぢやないね、」と、私が、いふと、「林家のおかみだよ、」と、芥川が、いった。「君は、妙なことまで、知ってるね。……ところで、こっちの隅にゐる女は、芸者だらうが、ちょいとキレイだね。」「君はじつに目がはやいね。」「さういふ君は、僕より早く見てゐたかもしれないから、どっちが早いか、わからないよ。」 私たちがかういふくだらない話をしてゐた時、(いや、その前から、)座席のほとんどまん中へんに腰をかけてゐた、菊池は、直木が、いつのまにか、どこかで、買ってきた、パンやかき餅を、ムシャムシャと、たべてゐた。…」。前回も書きましたが、”はかない記憶”と書いていますが、よく覚えているものとおもいました。芥川龍之介はお茶屋の女将を覚えているのですからたいしたものです。二等車に乗っていますが当時は三等制で二番目の等級に乗っています。それにしても昔の人は座席の上に座っていたのですね。
★左上の写真が二代目「大阪駅」です。一代目「大阪駅」は明治7年5月に建てられていますが、二代目は明治34年にゴシック様式で建てられます。今回の大阪訪問は大正9年ですから芥川龍之介はこの大阪駅に降り立ったわけです。三代目の「大阪駅」は昭和15年です(三階建ての鉄筋コンクリートの建物)。